第9回地域包括ケア病棟研究大会
【シンポジウム】
地域包括ケア病棟、あるべき姿への挑戦

【座長】小熊豊(公益社団法人全国自治体病院協議会会長)
皆様、こんにちは。
午前の2演題、それからただいまのパネルディスカッションが終わって、お疲れかと思いますけれども、最後のこのシンポジウムで5名の方からお話しいただきたいと思います。
実は、最初の特別発言をされる鈴木先生ですけれども、茨城県の医師会長としてのお仕事でほかのところへ行かねばならないということで、ビデオでお話しいただく予定になっております。演者の各先生は、それぞれ日本を代表する医療関係者の方ばかりでございますので、当初から、鬼塚大会長がディスカッションは要らないということで、その先生方のお話を十分に聞いてほしいという御要望と伺っておりますので、万が一、今日のお話を終わった時点でお時間があれば、講演の先生にお話し、質問をいただくという形を取らせていただきたいと思います。
早速ですが、鈴木先生のビデオを始めていただけますでしょうか。
「地域包括ケア病棟と地域密着型中小病院としての在宅療養支援病院の必要性」
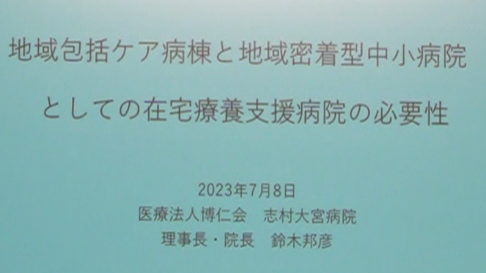

鈴木邦彦(医療法人博仁会、社会福祉法人博友会、学校法人志村学園理事長/ 元中央社会保険医療協議会委員)
皆さん、こんにちは。医療法人博仁会志村大宮病院理事長・院長の鈴木邦彦です。
このたびは、発表の機会をいただきありがとうございました。
本来は、直接出席させていただくつもりでしたが、茨城県医師会長として、長野市で開催される関東甲信越静地区の医師会長と保健福祉部長の会合に出席することになり、録画で参加させていただくことをおわび申し上げます。
COIはありません。さて、2025年が近づいてまいりました。ポスト2025年に向けて、引き続き医療提供体制の改革が必要だと思います。地域包括ケアシステムの構築、地域医療構想の実現、かかりつけ医機能の充実・強化は、三位一体で取り組む必要があると考えております。
これはその三者を一つの図にまとめたもので、最近使われるようになりました。
右側は地域包括ケアシステムです。そこに、かかりつけ医機能を有する医療機関として病院が入っています。左上は地域医療構想、左下はかかりつけ医機能になります。これら全てに関わるのが地域密着型中小病院、我々は在支病と考えております。そして、その多くが地域包括ケア病棟を持っています。
話は少しさかのぼりますが、平成25年(2013年)8月8日に、その2日前の8月6日に発表された社会保障制度改革国民会議報告書を受けて、日医・四病協合同提言を行いました。その2つの柱が、かかりつけ医機能の充実・強化と、地域包括ケアを支援する中小病院・有床診療所の必要性です。かかりつけ医機能の充実・強化のほうは、平成28年度に日医かかりつけ医機能研修制度につながりました。
地域包括ケアを支援する中小病院・有床診療所の必要性については、平成30年度の前回の同時改定時の診療報酬改定で、地域包括ケア病棟の病棟機能として部分的に実現いたしました。当時のかかりつけ医とかかりつけ医機能は、今でも中医協で保険局医療課の資料として使われております。
3か月後の11月18日に、四病協に追加提言をしていただきました。そのとき、病院類型3として地域包括ケア支援という病院機能を加え、地域医療・介護支援病院という仮称をつけて提言いたしましたが、それはまだ実現しておりません。当時から、病床規模別に見た病院の方向性として、400床、当時は500床以上の大病院は高度急性期から急性期に特化してください、200床未満の中小病院は、単科専門病院以外は地域包括ケアを支える病院になってくださいと言っておりました。
地域密着型の中小病院や有床診療所の役割ですが、従来の急性期大病院との連携や診療所の在宅支援だけではなく、行政や介護との連携、介護は自ら行うこともあります。さらに、医師会や地域への人材派遣、そしてまちづくりへの参画が考えられます。そして、平成30年度診療報酬改定において、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1と3に、地域包括ケアに関する実績が200床未満の中小病院のみに認められました。これはあくまでも病棟機能としての評価であり、我々としては病院機能を確立したいと考えておりますので、これではまだ不十分だと考えております。
一方、これは平成30年5月23日の前期の在宅医療及び医療介護連携に関するワーキンググループに出た図ですが、これが、私が四病協から出させていただいている今期のワーキンググループに出てまいりました。私は、この図が出たときは、日医からこのワーキンググループに出ておりましたが、その時期は体調を崩して休んでおり、ここで私としてはつながったことになります。
左下には、在宅医療において積極的な役割を担う医療機関として、在支病、在支診という言葉が入っており、右下には、在宅医療に必要な連携を担う拠点があります。これらが第7次医療計画までは位置づけることが望ましいとされていたため、8割、9割の都道府県で決められておりませんでした。それが、第8次医療計画からは、在宅医療圏の設定とともに位置づけられることになります。
在支診、在支病ですが、私は在支病にも深く関わらせていただいております。私は、平成22年度診療報酬改定の途中から中医協委員に就任いたしましたが、そのときには平成20年度改定でできた在支病は当初全国に4か所しかなく、その後も、7か所、11か所と非常に限られたものでした。当時、同じ中医協委員であった全日病の西澤前会長ともう少し在支病を増やしましょうと話して、許可病床数200床未満の中小病院にも認めていただくことになりました。その結果、現在では1,600か所以上に増えております。
在支病は、医療型、医療・介護型、医療・介護・生活型に分けられると考えております。そして、昨年3月に、四病協の支援をいただいて、一般社団法人日本在宅療養支援病院に連絡協議会を設立させていただきました。在支病に関するアンケート調査結果を見ますと、訪問看護ステーションは65%、居宅介護支援事業所は79%が設置していることがわかりました。また、地域包括ケア病棟は74%が持っており、地域包括支援センターの受託も40%が受けていました。
救急告示は59%、二次救急については49%が指定を受けており、救急搬送件数は平均値で678件、中央値で294件でした。平均値が高いのは、1,000件以上受けている医療機関が22%あるためです。
また、在宅医療において積極的な役割を担う医療機関を担う意向は72%、在宅医療において積極的な連携を担う拠点となる意向も68%になっています。なお現在、在宅医療・介護連携推進事業の相談窓口を担っている医療機関も36%ありました。さらに、介護予防や生活支援サービスにも取り組んでいるところがあり、特に介護予防に取り組んでいる医療機関は61%ありました。このように、在支病は既に医療だけでなく、介護分野にも積極的に取り組んでいることがわかりました。
超高齢社会に必要な病院機能としては、大病院と中小病院に分けて考えますと、高度急性期大病院、これはICUなどの高機能病床が10%以上あるような病院で、人口50万から100万人に1か所の集約化が必要です。それとともに、地域包括ケアを支える病院、我々は在支病を考えておりますが、それは人口2万から4万人に1か所と、分散化が必要だと考えております。2040年に向けて地域共生社会を実現するための医療3条件としては、高度急性期大病院の計画的整備による集約化、地域包括ケアを支える地域密着型中小病院の分散化、そしてかかりつけ医機能のさらなる充実・強化の三位一体の取り組みが必要だと考えております。新たなかかりつけ医機能報告制度におきましても、慢性疾患を有する高齢者に対するかかりつけ医機能として、外来医療の提供、休日夜間の対応、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等との連携が上げられております。在支病はこれら全てを満たすことができます。
今後のかかりつけ医機能の担い手としては、次の4つのグループが考えられます。一つは地域密着型中小病院ですが、我々は在支病を考えています。もう一つが有床・無床の在支診、そして総合診療医の先生方がやっておられるようなグループプラクティス診療所と、現在我が国に多いソロプラクティス診療所のグループ化が考えられます。
このように、かかりつけ医機能を持った診療所、有床診療所、中小病院が地域で連携し、介護分野を支援しながら、連携拠点や積極的医療機関を中心に地域包括ケアシステムを構築していくことになると思います。そして、二次医療圏の広域急性期大病院や三次医療圏の高度急性期大病院を実現するためには、地域医療構想をさらに推進することが必要です。また、地域包括ケア病棟については、平成26年度診療報酬改定で中医協委員として創設に関わらせていただきましたが、もともと、軽症急性期の病床としてDPC病床を維持できなくなったような中小病院のためにつくったものです。現在は高齢者救急の対応なども求められるようになりましたので、地域の中で役割分担をしていくのがよいのではないかと思います。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
小熊豊
ただいま鈴木先生の御講演を賜ったわけでございますが、これからの超高齢者の地域医療をどう展開するかということで、鈴木先生のお考えは、高度急性期の大病院、それから広域急性期の病院、それから地域包括ケアを支えるような病院。
地ケア病棟は広域急性期病院に入るのか密着型の病院に入るのか、ちょっと立場によって変わる可能性はあるとは思うんですけれども、鈴木先生はそこに在支病の働きを持たせて、有床診の方とかあるいは無床診の方と、かかりつけ医機能、在宅医療を責任を持って展開すべきではないかというお考えだったと思います。このことにつきましては、眞鍋課長が朝方言われましたけれども、地域に必要とされる医療を地域で、みんなで分担して考えていくべきだと、助け合ってですね。その一つの考え方ではないかと思って聞いておりました。
残念ながら、鈴木先生はお越しにならないので御質問にはなれませんけれども、その他の演者の方のお話と併せて、もし時間があれば、後ほど疑問点をお尋ねいただければと思います。
「日本在宅救急医学会の挑戦:在宅医療と救急医療の一つの病院連携」
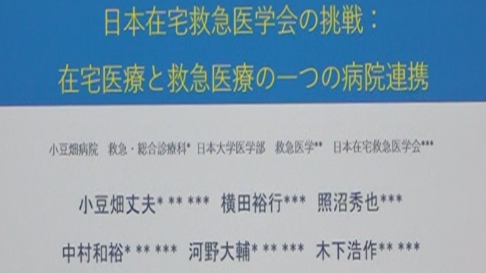

小豆畑丈夫(医療法人社団青燈会小豆畑病院理事長・院長)
茨城県水戸市から参りました、小豆畑丈夫(あずはたたけお)と申します。
私は大学卒業後に消化器外科を10年勉強し、その後救急医学を10年勉強しましたので、急性期外科・外傷とか急性腹症というのを大学病院で専門にしておりました。しかし、2011年東日本大震災に、茨城県の私の実家の病院が被災しました。その時の病院復興が自分のふるさとの医療を見つめ直すきっかけとなり、8年前に茨城に帰りました。現在、茨城県で「在宅医療と救急医療の病院連携」というのを行っております。今日は、そんなお話をさせていただきたいと思います。
COIはございません。
本日の内容です。最初に私達の施設の紹介、イントロダクションとして「高齢化における救急医療と在宅医療の現状」の紹介。それから、私たちが日本在宅救急医学会でやってきた2つの研究についてお話しさせていただきまして、最後に、地ケアについての私の考察を述べさせていただき、最後に全体の総括をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
私達は医療法人と社会福祉法人を持っていて、地域の医療・ケア・福祉を担当しています。
これが私どもの病院の全景ですけれども、ここに42床の急性期病院があり、48床の医療療養病床があります。後ろに100床の老健がありまして、50床の特養があります。その隣に地域密着型の小規模多機能施設があります。ここに薬局があり、歯科医院もあります。私はこの病院の隣の家で育ちましたので、ずっと父親の背中を見ながら医者になりました。
私達の施設の変遷を簡単にまとめますと、赤で示した部分だけが私がやったことで、あとは全部、私の父の仕事です。1980年に急性期病院として始まりまして、医療療養病棟、老健施設、そして在宅医療も細々と20年前ぐらいから父がやっておりました。そのあと、在宅医療と救急医療に私が力を入れました。最近では地域医療連携推進法人を、茨城県で2番目ですけれども、新たに創設しました。
日本の高齢化と救急医療、在宅医療の現状をまとめてみました。私なりに日本の高齢化を理解するために、こんなグラフを自分でつくって考えています。全人口に対する65歳以上人口の割合を高齢化率といって、7%というのが高齢化社会と最初に定義されました。そして、その倍々ということで、14%で高齢社会、21%で超高齢社会というふうに定義されてきたわけですが、次の倍にいくと28%です。今の日本はもうこの28%に達していますが、これに対しての名称がなくて、いわば超趙高齢社会という状況なのだと思います。そして、今日本は30%程度まで高齢化が進んでいます。高齢化で考えなきゃいけないのは、このスピードが日本では非常に速かったということです。戦後、日本はさほど高齢化の社会ではなくて若い社会でした。しかし、ものすごいスピードで高齢化していって、そして今や単独トップで高齢化の社会を形成している。しかし、アジアに目を向けますと、これから日本を超えるようなところもあって、アジアの国々は、日本の高齢化医療をどんなふうに乗り超えていくのかということを見ていて、うまくいけば真似をするし、うまくいかなければ違う方法を選ぶという見方をしているのかなと思います。
私は救急医なので、気になるのが救急搬送の件数です。令和3年までプロットしてあります。令和3年はコロナの影響で少し救急搬送件数が減っていますが、基本的にはずっと救急搬送件数は増えています。
ところが、5年ごとの年齢比で救急搬送を見ていきますと、先ほどの総数では令和3年から少し減っていますが、実は65歳未満でいいますと、平成18年をピークに救急搬送件数はかなり減っているのです。それに対して、高齢者の救急搬送件数がずっと増え続けているので、先ほどのような上り調子のグラフになっているわけです。
実数を見てみますと、65歳の救急搬送件数は、平成7年は100万件ぐらいだったのですが、令和3年には340万件で全体の62%に達しています。イメージでは、救急車で運ばれている患者さんの3分の2が高齢者だということです。このような高齢者の医療に対応するために、日本は在宅医療に力を入れて進めてまいりました。これは、2018年に厚労省が発表して、みんながちょっと驚いた記事です。2025年には在宅医療が必要な患者さんが年間100万人になるでしょうという内容でした。そのときは、それはちょっと言い過ぎじゃないのというぐらいの反応だったのです。しかし、実際には訪問診療件数はずっと増え続けていて、2022年の時点で90万件を超えています。これは先ほどの新聞の予想のスピードよりちょっと速いぐらいのスピードで進んでいるのかなと思います。15年で5倍という、すごい増加です。
日本の医療は、今は、「在宅医療と病院・診療所の医療」、見方を変えると、「医療者が移動する医療と、患者さんが移動する医療」の2つが基礎構造として存在すると私は考えます。この2つが機能しないと日本の医療は成り立たないのではないかと思っています。
では、在宅医療がうまくいけば日本の医療は大丈夫かというと、そんなことはないようです。これも厚労省からの報告ですが、訪問診療を専門にやられている先生が、自分の患者さんが入院が必要だというで病院入院先を探したときに、どこにも入院できなかったことがありますか?というアンケート調査があります。結果は、大体4分の1の先生が、入院させられなかった経験があると答えています。しかも、それが何回もあるという医師が多いのです。そこで浮かび上がってくるのは、在宅と病院の医療と両方必要なのだけれども、2者の連携はまだちょっとうまくいっていないところがあって、今もその傾向は残っていると思います。
まとめです。日本の高齢化は著しく、高齢者医療に関して手本となる国はありません。高齢者の救急搬送患者は増え続けています。高齢社会に対応するためには、病院医療だけではなく、在宅医療の充実が必要であると思います。在宅医療と病院医療の連携が求められているが、まだ十分とは言えないのではないかと考えています。
この問題をみんなで考えようということで、2017年に救急医療の医療者と在宅医療の医療者が集まって日本在宅救急研究会が設立されました。2018年には医学会になっております。
この研究会発足の趣意です。当研究会は、在宅患者が急性増悪したときに生じる問題を、在宅医療に関わるスタッフと(これは医師ではなくてスタッフです)、病院(救急)医療に関わるスタッフとが同じテーブルについて検討することで、在宅患者にとって“本当のいい医療”の構築を目的とする。
実際に、2022年まで学会が取り組んだ内容を紹介します。毎年学術集会をやっております。ここに上げたのが、この学会がメインで行ってきたいろんな検討ですけれども、今日は、このうちの2つを紹介したいと思います。
色々なことをやってきましたが、一貫したテーマは一つだけで、在宅医療と病院医療をつなぐ、ということです。その中で、この「在宅医療と救急医療の一つの病院連携」が、研究会発足のもととなった茨城県の検討です。
茨城県北部の地図で、上から下までで50kmぐらいです。水戸市以北は医療過疎の地域です。そこの入口に私たちの病院があります。私たちの病院は在宅医療と病院医療をセットで提供することを行っているので、自分たちが在宅から入院まで全部診ているのですね。そのときには全く発生しない問題が、在宅専門のクリニックの先生から、救急として僕らが患者さんをお受けするときに、何でここまで悪くなっちゃったのかなとかいろいろ考えることが生じるのです。それならば、自分たちが在宅から病院まで診るのと同じ環境をつくれば、在宅専門の先生から患者さんを受けるときでも、状況が好転するかもしれないという仮説を立てたんです。
それで、私どもの病院は、この検討のときには、ただ急性期病院として、僕ら救急医5人いるので救急として患者さんを受けることを担当しました。周りの5つの医療機関はいばらぎ診療所といいまして、訪問診療を専門にやられている医療法人です。一つの医療法人が5つの診療所をやっているんですね。こちらが在宅医療の担当者です。
実際、「一つの病院連携」とは何かというと、簡単なことです。これは、患者さんの依頼を受けるときに、必ず在宅の医師と病院の医師が直接、最低でも電話、もしできれば在宅の先生も病院に来てもらって、一緒に患者さんを診るっていう、これだけを徹底してくださいということにしたんです。医療者じゃない人がこれを聞くと、そんなのは当たり前じゃないのって言われるんですけれども、僕ら長いこと救急医をやっていて、在宅医療を受けている患者さんの急変対応を行って、その時に在宅医療の先生とお話しできた経験はほとんどないんですよ。それがやっぱり問題だと思っていて、医師同士が話をする、一緒に診る、ということを徹底してもらいました。あとは、本当に古いやり方かもしれませんけれども、顔がわかる関係をつくるということを一生懸命やりました。
もうちょっとお話ししますと、まず、在宅から病院に患者さんを紹介するときは、なかなかファクスとか使えないものですから、できるだけ簡単な紹介状をつくろうということで、こんな紹介状をつくりました。患者さんの情報はここだけ書いてもらって、あとは、誰先生に何を診てほしいっていうところだけチェックしてもらいようにしました。
在宅から患者さんが入ってきて、その患者さんが在宅に帰るときの多職種のカンファレンスの様子です。必ず病院側からはいろんなスタッフが出ると同時に、在宅医療の方も参加してもらう。僕らが大切にしたのは、患者さんの家族もここに入ってもらうことです。在宅に帰るけれども、具合が悪くなったらいつでもまた病院に来ていいんだからねっていう話をしてきました。それから、こんなふうに、本当に100人ぐらい集まって在宅医療側と病院医療側で一緒にカンファレンスを繰り返してきました。
実はこういう連携をする前に、この在宅医療のいばらぎ診療所から小豆畑病院には結構患者さんの紹介はあったのです。なので、連携前と連携後で患者さんの何が変わったのか、実際に在宅から小豆畑病院に紹介してくださった先生にアンケート調査をしました。その結果をお示ししたいと思います。
こちらが連携前の2015年、こちらが連携後の2016年ですが、まず、紹介患者さんが約2.5倍に増えました。そして、特徴的なことは、入院する確率が90%から70%まで減りました。実際に入院した患者さんの転帰がどうなったのかということを比較してみますと、入院期間が36日から22日、在宅復帰率が7割から9割、生存で帰れる確率が8割から9割と、転帰が全てよくなっているんです。これは何故か?ということで、僕らの腕がよくなったのかなって期待したんですけれども、そうではなくて、入院した患者さんの重症化スコアが半分になっていたのです。簡単に言いますと、在宅医が、患者さんが具合悪くなる前に紹介してくださっているので、入院する比率も下がりましたし、入院した患者さんの重症化スコアが低いので転帰がよくなったということだと考えています。
アンケート調査をしました。実際に紹介してくれた先生に答えて頂きました。連携救急病院に期待することは何ですか?ということを聞いて、私は最初、「患者さんが在宅に戻ってくること」かなと思ってたのですね。でも、全然違っていて、「素早い対応」と「紹介する上での気楽さ」だったんです。これを裏返すと、今までがいかに、入院させてねって言われても、なかなか僕らがああだこうだ言って対応しなかったということと、入院以来がどんなにストレスフルだったのかを示しているのだと思います。これが顔を知った状態になって、一緒に診療するっていうことでハードルが下がったので、このように連携後の紹介が円滑化して、ストレスも減って、結構満足できたので、これからも小豆畑病院で診れるような患者さんであれば紹介したいですというお返事になったんだと思います。
まとめです。この「一つの病院連携」は、在宅から救急への紹介ストレスを軽減して、重症化する前に病院へ紹介されてきました。その結果、患者さんの転帰が改善したものと考えています。 「一つの病院連携」は新聞でも取り上げて頂くことがありました。これは非常に絵がわかりやすいので時々使わせてもらっているんですけれども、在宅の患者さんが具合悪くなったときに在宅医と救急医が一緒に診ることによって、患者さんにとっていい医療が少しできているんじゃないかなということを評価していただいています。
次に、Oncologic Emergency(腫瘍緊急)というお話をさせていただきたいと思います。私はもともと消化器外科から救急医学に進んだので、割と腫瘍緊急が得意なんです。なので、うちの病院は私が病院長になってからこういうことを結構一生懸命やっておりまして、そのお話をさせていただきます。
腫瘍緊急は、がんを持っている患者さんが何かしらの理由で急変して急性期の医療が必要になる、その病態の総称をOncologic Emergencyと言います。社会が高齢化するとがんの罹患率が高くなることはよく知られています。このグラフのように悪性新生物で亡くなる人が今トップの状態になっています。それから、がんは日本人の国民病と書きましたけれども、今、2人に1人が亡くなるまでにがんにかかっていて、男性の4人のうちの1人、女性の6人のうちの1人ががんで亡くなっているという状況です。
これは今回、消防庁の発表データから調べてきたのですが、救急搬送要請を受けたときに病態が何って書くところに、新生物っていうのがあるんです。この新生物で救急搬送された件数を調べてまいりますと、19年で1.5倍。この患者さんがOncologic Emergencyの患者さんの一部だと思っています。そういう患者さんが今非常に増えてきているということで、我々の病院で訪問診療が始まって、どんどん件数が増えてきている。その期間を前期と後期に分けて、我々の病院で見たOncologic Emergencyの患者さんの件数とか、どんな治療したとか、そんなことを見る検討をいたしました。
前期が2014年から2017年、後期が2018年から2021年ですけれども、うちで受けたOncologic Emergencyの入院患者数は約2倍に増えていました。そのうち、救急搬送されるまでどこでがんの治療を受けていたかというのを見ますと、病院で受けていた人は半分以下に減っています。診療所で受けていた人はゼロになってしまいました。驚くべきことに、今まで在宅医療で診てもらってのちに病院に搬送された人が30倍、施設で診ていて搬送された人が13倍に増えていました。昔は病院でがんの患者さんのケアがされていたのが、今は在宅医療にシフトしている結果だと思います。
当院に来たときにどんな症状で来たのかを見てみました。食事摂取不良・脱水、それからがん性疼痛は減っています。それに対して、消化管閉塞、消化管出血、黄疸、痙攣・意識障害、ショックというのが3倍に増えていました。そして、症状の変化によって治療も変わります。輸液や疼痛コントロールという治療は大きく減っていました。内視鏡的治療(止血とかステントとか胆道ドレナージ)と手術(手術は緩和的外科治療、人工肛門造設、消化管バイパス、胃ろう造設)が7.5倍に増加しました。それから、ショックの治療などというのが増えています。
この変化の原因を考察しました。脱水や疼痛コントロールは在宅医療で非常に上手にされてくるようになったんだと思うのです。なので、そういう患者さんは減った。ただ、在宅で対応できないような病態が出てきたときに僕たちの病院に運ばれるというふうにシフトチェンジしてきたのではないかなと考えています。
まとめです。Oncologic emergency症例数は2倍に前期と後期で増えていた。背景は在宅医療と施設が急増して、在宅で緩和治療が行われていたけれども、在宅で限界に達した患者さんが病院に運ばれるようになってきた。そして、点滴・疼痛コントロールは在宅で上手にされるようになってきて、我々の病院では内視鏡的治療とか手術治療が増えているという結果だと思います。
言い忘れましたけれども、私の病院は地域包括ケア病棟をやっておりません。それなのに、仲井先生に発表してくれとお声をかけていただいたのと、鬼塚先生からこのような機会をいただいたので、私たちも「小豆畑病院と地ケア病棟の親和性」について検討してまいりました。その中で、在宅救急医療と、先ほどの鈴木邦彦先生の在宅療養支援病院(小豆畑病院は在宅療養支援病院です)、それから地ケア病棟の関連性について考えてみました。
くしくも鈴木先生のスライドと一緒になってしまいました。在宅医療の体制についての厚労省の資料をみますと、在宅医療を受けている患者さんの急変時の対応が病院に求められていることがわかります。しかも、今度の第8次医療改定では、「在宅患者の急変対応を担当する病院の指定」を市町村ごとに義務づけますという話があるようです。これこそ、私たちが学会で考えている在宅救急医療だと思っています。
では、これを担当するのはどんな医療機関なのかっていうことを考えました。在宅医療において積極的役割を担う医療機関と、24時間体制で在宅医療をやりながら病院医療が必要になったときに24時間体制で取り組むという医療機関は、やはり在宅療養支援病院になるのだと思います。
続いて厚労省は在宅救急医療をどのような病院に期待しているのかを調べて参りました。厚労省はこれからの医療を、高度急性期、急性期、回復期、慢性期っていう厚労省の分け方になります。急性期は「状態の早期安定化に向け医療を提供する医療」と「急性期の患者さんの在宅復帰に向けた医療」と定義されていて、在宅救急医療を行うべき病院はこの急性期病院になると考えます。では、急性期医療のこの2つの医療を担当するのは、地域包括ケア病棟と厚労省は示しています。従って、在宅療養支援病院で、かつ、在宅救急医療に注力している小豆畑病院にとって至適な病棟区分は地域包括ケア病棟になるわけです。
たまたま我々、先ほどお話ししましたように、地域医療推進連携法人を提携することができまして、14床の病床を新たに使わせていただけることになりました。2025年の新病院のときに追加病床をオープンする予定ですので、その時に地ケア病棟開設を考えていきたいと考えています。
まとめです。2024年の第8次医療計画では、「在宅医療-病院医療の連携の拠点」という医療機関が指定される可能性があります。そして、在宅救急を行う医療機関は在宅療養支援病院で、病棟は地域包括ケアが適当となる可能性があると考えています。
最後のスライドになります。総括させて頂きます。
日本は現在、世界で最も高齢化が進んだ国であり、高齢者医療に関して他国に手本はありません。自らが考えて構築していかなくてはいけません。社会の高齢化に対応するために、日本の医療は「在宅医療と病院医療」の両方が必要で、その連携(在宅救急医療)は必須であると考えています。在宅救急医療を行う医療機関は在宅支援病院が適しており、病棟は地域包括ケア病棟が適していると考えられると思っています。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
小熊豊
先生、ありがとうございました。
先ほどのパネルディスカッションで在宅医療と地ケアの話をされた水野先生、ただいまの発表を聞いて何か御意見ございませんか。――いないかな。いないみたいです。残念ですが。
お二人とも、在宅と急変時の対応ということで、新たな展開を我々にお見せいただいたと思っています。
実は、某県で県立病院が合併しまして巨大病院をつくったと。そうしたら、その巨大病院に患者さんが行き過ぎて、地域密着型の民間の病院が、7件中5件だったかな、急性期を廃業したということで、高度急性期の大病院の役割は何だと。これから高齢者が非常に増えるのに、地域分散型である程度密着した急性期病院が必要ではないかという意見が民間の先生方からは主張されていると。確かにそのとおりだと思うんですけれども。そのことについては、後ほど山本先生がちょっとコメントいただけるものだろうと僕は思っているんですけれども。
やっぱり医療は地域でするものですから、地域に一番必要な医療をどうやって提供するか。先生のように在宅と救急とに焦点を当てて、しかも、がんですね、非がん患者とがん患者の立場でそれぞれのことを取り組まれる、これはすばらしい、新しい試みだと思って私は感動してというか、――そこまで言うとオーバーかな、聞いておりました。
後ほどまた、会場の先生方で御質問があればお願いしたいと思いますので、先生お待ちいただいて。
ありがとうございます。(拍手
「最大で最強の地域包括ケア病棟 ver. 2.0」


仲井 培雄(地域包括ケア病棟協会会長/医療法人社団和楽仁芳珠記念病院理事長)
皆さん、こんにちは。
小熊先生、過分な御紹介いただきまして、ありがとうございます。今日は、皆さんとても系統的なお話が多いので、逆に、僕は思っていることを言ってみることにしました。
地域包括ケア時代の患者像はこんな方が多いですよと。
複数疾患を持って、ADLと栄養状態、認知機能が落ちて、ポリファーマシーになりやすい。入院前から継続して、入院中も包括的な生活支援とか意思決定支援が必要な患者が多くなる。リハビリは、社会復帰を目指す脳卒中モデルよりも、生活復帰を目指す廃用症候群・認知症モデルが主となる。QOLとQODの価値観は、人それぞれ異なる上に、介入のエビデンスが乏しいため、ACPや多職種協働によるカンファレンスは必須になるということをいつも言っております。これがどうもマルチモビディティというものに非常に近いということに2年前に気づいたわけです。
複数の慢性疾患が一個人に併存している状態であり、中心となる疾患を特定できないというものがマルチモビディティで、スライドはシステマティックレビューで抽出された重要論文において、マルチモビディティを定義する際に含める対象とした疾患ということで上げられていますが、本当に普通の疾患ですね。(改行なし)トップ5だけ言うと、COPD、DM、高血圧、がん、脳血管障害。これは高齢化とともに増えまして、性別、貧困、フレイル、精神疾患合併。死亡率上昇、QOL低下。受診回数が増える、ケアの分断、ポリドクター、ポリファーマシー。救急受診、予定外入院、医療費の上昇。疾患別ガイドラインに基づく介入は当然エビデンスの裏づけありませんから。通常の疾患別ガイドラインは、高血圧なら高血圧の人、せいぜい心不全ですかね、そういうものがあって、Aという薬とBという薬、どっちが効くんですかっていうランダマイズド・コントロールド・トライアルしますけれども、こんなに疾患があったら、それはできませんよねという話です。ですから、アウトカムは患者のQOLの向上になるんです。
エビデンスはない疾患というか、先ほども水野先生が、マルチモビディティになると疾患の意味がなくなってくるんだって言われていましたけれども、そもそもエビデンスがない疾患というか患者を扱うわけですから、後でもちょっと言いますけれども、地域包括ケア病棟にエビデンスを求めることはなかなか難しいんじゃないかというのが最近の思いです。だから、地域包括ケア病棟の評価はもっとふわっとしていてもいいんじゃないかなというところですよね。
実はこれ、東大の秋下先生がつくられたのをお借りしているんですけれども、同じ80の高齢のマルチモビディティでも、メタボ型の元気いっぱいの人は、どっちかというと心血管疾患を予防して、生活習慣病の厳格な管理と多剤服用もやむなしというところにいくんです。けれども、フレイルの人は、逆に老年症候群の予防とQOLの維持、もっとたんぱく質を食べてよっていう話で、生活習慣病の緩やかな管理、ポリファーマシー対策がメインになっていって、すーっと徐々に落ちていくのを、QOLを何とか高めようという話になります。全然違うわけです。
地域包括ケア病棟の経緯ですけれども、先ほどから松本会長や眞鍋課長が詳しく言われておりますので、私はさっといきますけれども、H26年度にできました。3つの役割があります。H28年度は手術・麻酔が包括から外れて、500床以上はだめと。
このスライド、うちの協会ではこのように、1番はポストアキュートと呼んでいて自院と他院に分けていますし、2番はいわゆるサブアキュートとして緊急と在宅等予定に分けています。在宅復帰支援は院内と地域内の多職種協働ということで、3つの病棟機能というふうに呼んでおります。
この段階で、地域包括ケア病棟って一体どんな病棟なのか一言で言ってくださいと言われて困っていました。当時、できたばっかりのときは、10対1以上の急性期を持つ病院とそうでない病院では地域包括ケア病棟の使われ方が全然違ったんですね。前者だと院内ポストアキュートばっかり、後者だと他院とかサブアキュートも入ってくるということでありました。なので、このような定義をしたんですね。在宅復帰支援機能を基軸に、自院が御当地ニーズに寄り添えるように、自院の他病棟の機能が生きるようにカスタマイズできる。カメレオンみたいに、本当に使い勝手のいい、懐の深い病棟だということで言っておりました。このときは、やっぱり自院ポストアキュートばっかりはいかがなものかという話があったんですけれども、7対1や10対1が減るならよかろうということで、ある程度黙認していただいた。
そのため、 H28年度は手術・麻酔が出来高算定となった。一説によると、当時、これ言っていいのかな、何かこれを入れるのを忘れてたっていう話があったんですけれども。いわゆる「なんちゃって地域包括ケア病棟」っていう言葉も出てきまして、高度急性期で400床500床、7対1が空いてきたから地域包括ケア病棟でも取ってみるか。これはやっぱり我々としてもあまりおもしろくなかったですね。
なぜかというと、リハビリしないんですもん。それで質が高くないんですね。そうすると連携先の後方病院との信頼関係も崩れることになって、後方病院から私のほうにかなりクレームが入ってきたことを覚えております。案の定、500床以上はだめよということになって、その後、400床以上もだめになったということになります。
その後、ここからはH30年度、迫井先生が課長をされていたときにこの入院料・管理料1‐4に見直して、ACPを一部要件化するという大改革が行われて、そのときに在宅医療や介護サービスの提供が地域で求められる、そういった指標が入ってくるようになりました。そうすると、このときに病院としてどんな機能を持てばいいかということと病棟としてどんな機能を持てばいいかということがはっきりしまして、その中には、救急や在宅や訪問、それから介護施設や、いろんなことが入ってくるようになりました。
ただ、やっぱり患者さんがこんなふうに治ったらいいという指標は今もないんですね。先ほど言いましたように、マルチモビディティの患者さんを診るということにおいては、なかなかそういうエビデンスを持った指標を出すことは難しいんじゃないかと思います。
それから、R2年度、4年度はコロナ禍の改定になりました。R2年度、DPC対象病院での入院料の算定方法が変わり、地域包括ケア病棟でのDPC算定中のリハビリテーションは出来高算定ということになりましたので、地域包括ケア病棟入院料のDPC対象から、自院から来た患者さんが出来高のリハビリが取れるというのは少しインパクトがあったように思います。R4年度の診療報酬改定では、一物多価が激増したわけですね。
ちょっと話は変わりますけれども、2021(R3)年に潮目が変わりました。地域包括ケア病棟入院料2がそれまでトップだったんですが、5月の届出。これ、6月って書いてありますが、チェックしたときが6月ですが、実際の届出は5月なんですね、マイナス1か月。地ケア1が逆転して、そこからどんどん増えていって、R4年6月の届出が半分を超えました。それからどんどん1が増えています。これが、潮目が変わったと思っております。
このときは、やっぱりコロナがあって在宅からの直接入院減少の危機ということで、在宅医療の充実や、在宅看取り、訪看、かかりつけ医機能とデジタルトランスフォーメーション、在宅医療進化、そして今、事前のACPによる救急不搬送も増加しております。介護施設での医療提供が充実しております。高度急性期病院の充実で、こちらは期待感があるんですね、やっぱり高度急性期には。我々中小病院にはない、何か期待感がある。ここに行ったら治るんじゃないか。そうすると、在宅で診る・介護施設で診る・高度急性期病院を受診っていうことで、どうも何かちょっと患者さんが減らないかなと、立ち位置が揺らぎませんかという話をしました。なので、コロナも受け入れたらどうかと。
一方、他院からの入院減少も、初発の脳卒中はやっぱり回復期リハビリテーションですよね。私もそのほうがいいなと思ったので、自分の病院に回復期リハビリテーション病棟をつくってみました。というか、ずっと地ケアで頑張っていたんですけれども、とてもつくりたくなりました。後で言います。それから、急性期一般病床の心不全、誤嚥性肺炎というのは直接在宅へ帰る。これは産業医大の松田先生のデータですけれども、もうポストアキュートで地ケアへ行かないんですね。そのまま在宅、介護施設に帰っちゃう。コロナ回復患者はしっかり受け入れましょうということです。あとは、自院の一般病床からの転棟の制限が400床以上から22年に200床以上になったということで、これらもみんな制限がかかってきて、じゃあどうしましょうと。上からも下からも地域包括ケア病棟は立場が緩んできた。
そこで私が考えたのは、前半の部分、地ケアシステムと地域医療構想とか人口ビジョンとかは一緒ですけれども、やるべき医療として、総合診療や老年医学のマインドを持つ医師とともに急性期後や在宅療養中のマルチモビディティ患者を病棟で受け入れる、在宅で診る地域診療拠点にしたらどうかと。それも病棟じゃないんですね、病院なんですね。地域包括ケア病棟を持っている病院。特にマルチモビディティの中でも、高齢虚弱患者、先ほどの秋下先生のスライドですね。その上でやりたいことをやればどうだっていうことであります。
地域包括ケア病棟が新設当時、2014年、2016年のときに、急性期なのか回復期なのかっていうのがすごくお話が出てきまして、僕すごく困ったんですね。あるときは急性期、あるときは回復期みたいな。でも、今は、こういうふうにするとはっきり言えるんですね、急性期でも回復期でもない地域包括ケア病棟ですと。アイデンティティがすごく定まります。ですので、カメレオンからコウモリにしました。なぜコウモリかというと、ちょっとコロナと関係ないんですけれども、四つ足歩行の哺乳類でもないんですね、それから鳥類でもないんです。コウモリって空飛ぶ哺乳類ですから、唯一無二です。ムササビとかモモンガはだめですよ、あれは滑空しているんですから。飛んでいるのはコウモリだけです。地域包括ケア病棟もこのくらいのアイデンティティを持たないと立ち位置ができないでしょっていうのが私の思いで、これをずっと言っている次第です。
実際に2014年度から、8年目の4回目の改定のときにすごいことになったんですね。入院料・管理料1‐4はH30年度になりましたけれども、200床以上・未満、一般病床・療養病床、DPC対象病床の有無、減算要件充足の有無、プラスコロナ特例、山のように一物多価になってしまいました。多分、医事課の専門職でも、本を持たないと一発で答えは出せないと思います。
もう一つは、先ほども言いましたが、病院としての機能はどうかと。これは早くから言っていまして、これはおととしの3月31日の状況で見たものですけれども、急性期ケアミックス型がまだ一番多いんですけれども、急性期一般病床以上を持っていて、施設全体で急性期機能を最も重視している。先ほどのパネルディスカッションでいうと、石川先生のところですね、200床以上かつ入院料2‐4、ICUとかもあるところが2割、6割がコロナ重点・協力、地ケア病棟は自院ポストアキュートが多目だと。
ポストアキュート連携型は、定義としては、施設全体として、実患者数がおおむね半分以上が他院からのポストアキュート患者ということで、これは入院料・管理料1・3が6.5割強で、199床以下がものすごく多いです。半分弱が大都市部に開設されています。あとはコロナ回復患者が5割強。
地域密着型は、そのどちらでもないという定義でして、これはもっと小さい病院が多いです。入院料・管理料1‐3が7割強、6割弱が医療療養を持っていて、4割強がコロナ回復患者のみと。ポストアキュート連携型と地域密着型は訪問とか通所が多いということになっています。それぞれ5.5割、1割、3.5割となっておりますが、今地域密着型が増えていて、急性期ケアミックス型が減っています。
地域包括ケア病院というのもすごく増えていまして、ここでは80と書いてあるけれども、今84施設ですね、つい最近調べたところ。水野先生のところもそうですし、全病棟病室が地域包括ケア病棟という形態分類になります。機能分類は、地域密着型やポストアキュート連携型となります。
次、回復期リハビリテーションとどう違うんだという話をしたいと思います。
これは私の全くの私見なので、さっと流していただいてもいいんですけれども、回リハはやっぱりエビデンスに基づく脳神経科学、社会復帰を目指す回復期リハビリテーションを要する患者さんを診る、ランダマイズド・コントロールド・トライアルでアウトカムを定義して、きっちりかっちりリハビリをやっていく。1日9単位、60日、180日、それぞれの疾患によって違うわけですけれども、ばっちり治していく。
一方、地域包括ケア病棟は、患者の価値観に基づく総合診療や老年医学がメインで、生活復帰を目指す高齢虚弱マルチモビディティ患者、患者のQOLとQODの向上がアウトカムになります。エビデンスによる裏づけは不十分になります、いろんなことの。どちらかというと回リハは退院したときに介護保険を取るみたいな感じですけれども、地ケアは最初から介護保険のある人が多いと思います。地ケアと回リハの違いはこういうことで、急性期が、いわゆるサブアキュートがあるか、在宅復帰支援機能があるかということと、回復機能が違うということであります。
両方の病棟を持つ病院にアンケート調査を2015年度にしたんですけれども、受け入れ患者の選択基準はどうですかと聞きますと、回復期リハビリテーション病棟は、当然要件がある方で、高いADL改善率を獲得できるような脳血管障害や整形外科疾患を念頭に置いて5単位以上、61日以上の十分な機能回復リハで社会復帰を目指す。一方、地ケアのほうは、多様な疾患群の治療と、リハビリ・栄養・認知症・ポリファーマシーに対する対策が必要な患者に、1日2単位から4単位ぐらいの効率のよい生活回復リハで60日以内に在宅復帰を目指すということでありました。
最近、この疾患が地ケアと回リハ出てないんですけれども、ぜひ回リハの疾患も知りたいところです。これは最新のデータ2017年度ですけれども、そうするとやっぱり地ケアのほうは、骨折はあるんですけれども、悪性腫瘍とか心不全とか肺炎というのが回復期リハに比べると随分と多くなっております。一方、回リハは脳血管障害が多いですね。
例えば、高齢虚弱のマルチモビディティ患者が地域包括ケア病棟に入ってくると、骨折、肺炎、心不全、脳梗塞、がんに罹患した高齢虚弱マルモの方ですね。その際、マルチモビディティのための治療方法には明確なエビデンスがないので、QOLの向上になると。リハビリは2単位の包括、様々な検査、処置が包括、これも臨機応変に介入できる強みだと。これは先ほど富家先生も言われていました。
特に我々は補完代替リハビリテーションというものを提唱しておりまして、いわゆる疾患別リハにはない。短時間の疾患別リハに近い、20分未満のリハビリを行うPOCリハとか集団リハとかデイケアとか集団運動療法とか、そういうことをやっております。これはこういった高齢虚弱のマルチモビディティの方には非常にいいですね。
救急と在宅、これは小豆畑先生が言われたとおりですけれども、救急・災害医療提供体制に関するワーキンググループというのが第1次医療計画のもとでやられておりまして、2022年10月に取りまとめがありました。その中で、救急医療機関の役割は何だと。高齢者の救急が増えていく中で、初期はちょっと置いておいて、第二次救急医療機関は、地域で発生する高齢者救急の初期診療と入院治療を主に行う。まさに小豆畑先生がされているようなことですね。三次救急は、重篤な人や、ここに書いてあるようなもっと難しい人。
高齢者の患者が帰宅する際には、生活上の留意点に関する指導や必要な支援へのつなぎをすすめる。下り搬送もやりましょうと。高次の医療機関からの下り搬送を促進する。これは、あらかじめ受け入れ先といろんな情報を共有しておきましょうと。
これは、先ほど小豆畑先生が見せられたとおりですが、付け加えていうと、右下のほうですね、疾病分類別搬送人員のうち、特に高齢者の症状・徴候・診断名不明確というのが増加している。これは恐らくマルチモビディティだと思われます。
あと、下り搬送ですね。下り搬送すると三次救急がふん詰まりにならなくていいですということと、三次救急にとってはあまり得意な分野でない生活支援、在宅復帰支援、ここができる病院へ送ってはどうだ。これはまさしく我々地域包括ケア病棟の他院ポストアキュートとしての非常に大きな役割を感じております。
課題と論点として、中医協の中で、これも先ほど出ましたので最後の論点だけ言いますと、地域包括ケア病棟は急性期入院医療にも回復期入院医療にも出ています。急性期入院医療とは、急性期病棟と比べてどうか。回復期入院医療としては、在宅患者に対する救急を含めてその役割はどうなのか。回リハとの役割分担はどうなのかというところ、今お話ししたようなことがここに書いてあると思います。
ここはエビデンスとして出しておいただけですけれども、中医協の総会の医療計画についてというところでは、地ケアでは不安だという意見が結構出ておりまして。でも、言ってみると、例えばうちの病院なんか急性期一般1と地ケアを診ている医者は一緒です。看護師もローテーションしますし。地ケアは今、看護師の配置加算取っていますから、13対1じゃなくて、10対1です。あまり変わらないような気がして。救急車はそこそこ受けています。
逆に、医療・介護の意見交換会の高齢者の急性期入院医療については、ここはもっと地ケアがやったり介護施設がやったりしたらどうだということで、両方の意見が書いてありまして非常に興味深いですね。ここら辺の答えを出せるのは、きっと地域包括ケア病棟であったり在宅療養支援病院であったりするのかなと思います。ただ、実際にはあまり受け入れていないというのが現状です。
それから、高齢者の救急医療をどうするか。ACP、それから心肺停止になったときに不搬送もありだねっていうことが言われています。
あとは、トリアージのジレンマっていうことも考えないといけないのかなと。救急隊とか外来医師、看護師も、アンダートリアージの結果三次救急に行ったり、再搬送したり、高次機能の院内転棟はできれば本当は避けたいですよね。なのでオーバートリアージになりやすい。その結果、搬送時は高度急性期病院に行きがちになりますし、入院時は急性期病棟を選びがちになると。であれば、トリアージを精緻化するのはどうかという話であります。
そうなると、臨床能力を向上させるっていうこともあれですけれども、いつも外来で診ている、いつも在宅で診ている人ならば、いわゆるなじみの高齢虚弱のマルチモビディティ患者なら体調の変化に気づきやすいし、トリアージの精緻化にもつながると思いました。
先ほど小豆畑先生が言われたのは、ちょっと意味は違いますけれども、軽い状況で受け入れれば、それは救急なんだけれども、早く治して早く帰せる、重症度も低い。まさしく僕はこれが、この答えが先ほど小豆畑先生が言われたと私は思っております。三次救急からの下り搬送も積極的にやればいいということであれば、これは重症疑いのトリアージは自院で行わないっていうことになるので、あらゆる意味でいろんな精緻化が、ちょっと見方を変えるといろんな方法でできるのかなということを思いました。
あとは、これはちょっとややこしいですけれども、救急医療と在宅医療を提供する体制の要件というのがございまして。これは病院としての要件ですよね、地域包括ケア病棟が必要としている。令和2年度は、救急としては二次救急、救急告示。在宅医療としては在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院で年3件の実績、訪看ステーションの同一敷地内設置というものだったんですが、令和4年基準では、ちょっとわかりにくいんですが申し訳ございません。一般病床であればこの救急告示または二次救急は絶対取らなくちゃいけません。ただし、200床未満、199床以下は救急外来を有す、または救急患者を24時間受けているでもいいということになっております。
一方、ここを忘れていた方が結構いらっしゃるんです。僕も昨年の秋頃まであまりきちんと気づいていなかったんです。在宅医療を提供する体制として、この3つのうちどれかを選ばないといけないんです。この中の救急の2つは必須要件化されましたので、このうちのいずれかを満たすということであれば、残りこの3つのうちから1つを選ぶということになっていたんですね。
これを見逃した方がいっぱいいらっしゃって、どうなったか。今年4月の経過措置終了で今の要件が、経過措置なくなったものですから、何と115病院、4月の経過措置で落としまして、そのうちの77%が急性期一般1-6に戻した。逆になりましたね。地ケアから急性期一般1-6に戻した。ただ、恐らくですけれども、この半分以上の方々はまた地ケアに戻られると思います。今もわかっているんですけれども、訪問看護ステーションを取られて、特に自院でやらない、他法人の訪問看護ステーションを敷地内につくられてクリアしているところは、私のところにも幾つか情報が入ってきております。
もう一つは、地域包括ケア病院にすると問題点は、一生懸命救急車を受けても、看護職員処遇改善評価料の申請にはならないんですね。これは眞鍋課長にもいろいろ質問したんですけれども、なかなか難しいということになっております。これは何とかしていただくと、何となくですけれども、今の話の中でちょっとうれしいかなというところです。
コロナですけれども、2020年度、コロナはほとんど受け入れてなかったです。回リハほぼゼロ、地ケアは5%ぐらい、回復患者は両方とも受け入れていました。しかし、そのうち、先ほど井川先生が、コロナの変異前はちょっとひどかったけれども、受け入れられないけれども、今のコロナなら受け入れられると言われましたけれども、そういう形で少しずつ落ち着いてきたし、ワクチンも薬も手に入ったし、地域包括ケア病棟で診られるようにということでコロナ特例がいろいろ出ました。
これから5類になって、ここにぽっと、地域包括ケア病棟などということで、高齢の介護施設の方のコロナを受け入れてくれるとうれしいなということで、点数が950点つきました。
コロナ特例がいろいろ変わったので、これ、もしかしたら皆さん御存じないかもしれないので、4月6日の事務連絡をぜひ御覧ください。今までの、その26だったかな、と全然内容が違ってきています。またはまることのないように、10月に向けて御準備をしてください。
最後になります。
第8次医療計画ですけれども、ここは持続可能な社会保障制度の構築云々ということで、骨太の中に、物価高騰・賃金上昇云々というところを対応してくださるというお話が入っておりますが、この直前に、今そちらにいらっしゃる日病協の山本議長と、私、副議長しておりますが、厚生労働省で記者クラブで提言しておりまして。ほかの団体もいっぱいされています、もちろん日医・四病協も含めて本当に山ほどの団体、皆さんで勝ち得たものだと思うんですけれども、これがこのままなるかどうかちょっと。なると信じたいんですけれども、何とかなればいいなと。
そんな中で、やっぱり今後地域包括ケア病棟としては、第8次医療計画を見据えて、総合診療医や老年医学、特定行為研修修了看護師等と地ケア病棟を届け出る病院の組み合わせは、生活者としてのマルチモビディティ患者・利用者のQOLだけでなく、我々の働き方改革や病院経営にも好影響をもたらすのではないかと予想しております。そのときはDXは必須だろうと思います。
あとは、在宅療養支援病院との兼ね合わせです。これも僕は非常に魅力的だろうと思います。松本会長も最後に言われましたけれども、地域包括ケア病棟と在宅療養支援病院を取って機能強化型加算を取ると、これはステータスだと言われていましたので、そのとおりじゃないかなと思います。当院はまだ取れていないんですけれども、早く取りたいなと思います。
そうこうしているうちに2040年になります。高齢者だけの地域包括ケアシステムから障害者、生活困窮者、子ども・子育て家庭、本当はここに外国人が入ってくると本物になると思うんですけれども、そこにはきっとこの地域包括ケア病棟がカメレオンからコウモリになって、バージョン1から2に変わることによっていろんな化学反応が起こってくるんじゃないかということを期待しております。
そして、ちょっと宣伝になりますけれども、2023年度地域包括ケア病棟認定医養成アカデミー(今期は最少遂行人数に満たず開催中止となりましたことをお詫び申し上げます。)というのが、うちの地域包括ケア病棟協会の教育研修委員会が、こういうカリキュラムをつくってくれましたので、もしよろしかったら、また9月から3月まで一緒に勉強できたらなと思います。よろしくお願いします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
小熊豊
先生、ありがとうございました。先生、1つだけ聞いていいですか。
地ケア病棟と急性期一般病棟と、先生のところも持っていらっしゃるし、石川先生のところも持っていらっしゃるし、そこは看護配置10対1に。先生もそうですよね、10対1ですよね。
13対1のままではちょっとやっぱり対応できないっていうふうに考えたほうがいいですか。
仲井培雄
そういう考え方もありますが、夜勤を看護師二人で揃えると病棟の病床数によっては10対1でも13対1でも同じ人数でできてしまうことがありますね。当院もそうですし、看護配置加算も取っています。
小熊豊
自然になっちゃう。
13対1のままで急性期一般病棟というのを対応できるかという問題が、先ほども言いましたけれども、もめていますので、先生はどうお考えですか。
仲井培雄
ただ、13対1の地域一般病棟で、救急を受け入れていない病院ばっかりなのかというと、そんなことないんじゃないかと思うんですけれども。
小熊豊
それは、データはお持ちですか。
仲井培雄
今は持っていないですけれども。御存じないですか。
この中で、13対1の地域一般病床で、一番川上で、救急車をいっぱい受けていらっしゃる方っていらっしゃいますか。
小熊豊
やっぱりあまりいないですね。
仲井培雄
いらっしゃらない。
わかりました。ありがとうございます。
小熊豊
やっぱり物理的にちょっと無理じゃないかと思うんですね。地ケア病棟を持って、なおかつ回復期も持って、療養型あるいは在宅支援、それが理想じゃないかと僕自身は勝手に思ってるんですけれども、いかがでしょうか。
仲井培雄
ありがとうございます。地域包括ケア病棟も看護配置加算をとって10対1であれば安心ですよね。急性期の2以下は10対1ですから。
小熊豊
あとほかに、今会長にお聞きしたいことがあればお受けしますけれども、いかがでしょう。よろしゅうございますか。
どうもありがとうございました。(拍手)
「ポストアキュート?サブアキュート?」
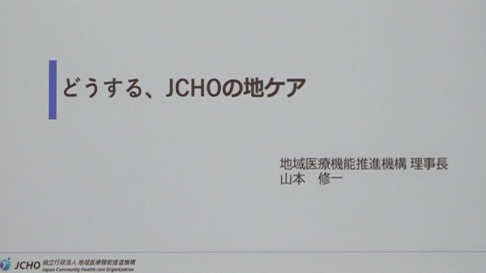

山本修一(独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)
ありがとうございます。
皆さん、こんにちは。JCHOの山本でございます。「挑戦」がこのシンポジウムのタイトルらしいんですけれども、私、スライドをつくっているうちにぼやきばっかりで、「どうする家康」状態になっておりますので、皆さんの御意見いただければなと思う次第です。
そもそもこのJCHOっていうと、地域医療機能推進機構って書いてあるように、この10年間、お題目に地域包括ケアシステムの構築あるいは地域包括ケアシステムの要っていうのが入っちゃっているんですね、最初から。だもんですから、私は今これはJCHOの呪縛というふうに言っておりますが、ここにとらわれ過ぎちゃって、本当にやるべきことが何だかわからなくなってきちゃっているなというのが、今、パンドラの箱を開けたところでございます。
今御紹介いただきましたけれども、私、もともとは眼科でございまして、手術が好きなので手術をばんばんやって、開業してがんがん稼ごうというのが夢だったんですが、どんどん道を外れてまいりまして、ここに至ります。
JCHOはもともと、社会保険病院、厚生年金、船員保険病院という成り立ちの違う団体が独法にしようということになったというところであります。
病院は全国に57施設で病床数1万5,000、職員数は2万7,000強というところでございます。
さて、JCHOの病院の立ち位置というのはどういうところにあるかというと、いろんな病院がありますけれども、急性期中心の病院から、あるいは地ケア、回リハ中心の病院というところに位置しています。ただ、ちょっと特異なのは老健を持っているということ、あるいは訪問看護ステーションを持っているというところで、上から下まで結構幅広くカバーしておりますが、それゆえにいろんな問題があるところでございます。
これは、横軸に病床数、縦軸に入院診療単価を取っておりますが、急性期に非常に特化した病院もある一方で、300床以下で入院診療単価もちょぼちょぼというような、急性期と回復期がミックスした病院が大半を占めているところであります。
これらの病院は、御多分に漏れず、病床利用率はコロナ前から70%台というところで、それがさらにまたずるずる下がってきているという状況で、コロナが抜けてどうするっていうところがまさに問題となっています。
経常収支でありますが、ずっと1%台の黒字を維持してきて、補助金でぼんぼんぼんっと歪んでしまったという状況ですが、実際、医業収支だけを見ますと、実は結構健診が強い病院が多いものですから、そこを外した正味の本業で見ると、黒赤ぎりぎりのところでずっときて、コロナに入ったらもう真っ赤っかという状況になっているということであります。
直近のデータで比較しますと、新外来患者数はコロナ前と比べると25%ダウン、入院患者数も10%ダウンというところです。手術件数は約4%ダウンというところで、ここは少し戻ってきていますが、エネルギー費の高騰は御覧のとおりであります。
さて、本題の、うちの地ケアの病棟の状況でありますが、57病院中48病院、全病床の14.7%が地ケアになっているところです。入院料の内訳は御覧のとおりです。そのほか、在宅、在支病が4病院、在宅療養後方支援病院が11病院、訪問看護ステーションは32病院に設置されている状況です。
この地域包括ケア病棟の設置状況を、公立、公的病院の中で比較するとこのようになります。緑の部分が地域包括ケアでありまして、都道府県立だと4%ぐらいですが、KKRが11%で、JCHOは15%というところで、同じような公的病院の中ではかなり地ケアをたくさん持っている状況でございます。ちなみに、この辺のデータは、千葉大学病院の副病院長で、今JCHOの経営戦略顧問をしてくれている井上貴裕先生がつくってくれた資料であります。
この辺は、皆さん御存じのように、人口10万当たりの地ケア病床数は都道府県別に見るとこれだけばらつきがあると。関東は非常に少ないよねっていうところは御承知のとおりであります。
また、これは、横軸に一般病床の平均在院日数を取って、縦軸に人口当たりの地域包括ケア病床数を取ったものですが、やはり一般病床の平均在院日数が長いほうがこの地域包括ケア病床が多いというところで、この在院日数のコントロールのために必然的に地域包括ケア病床が増えたのではないかなという分析もあるところであります。
これは、横軸に人口当たりの地域包括ケア病床数、縦軸に1人当たりの実績医療費を取りますと、正の相関があるということで、ここもいろんな解釈があるかと思いますが、地ケアの病床を置いておくと経営的にはいいよねっていうところになるのかもしれないなというところであります。
これも井上先生がつくった全国のデータですが、横軸に地ケアの院内転棟率で、縦軸に病床稼働率を取ると、負の相関が見られるというデータであります。
さて、DPC参加病院における地ケア病棟の保有割合を見ていくと、これもやはり都道府県によって差が大きくて、秋田県だとDPC病院の8割に地ケア病棟を持っていますが、例えば私がいた千葉県だと31%にしかないというデータがございます。
これは、同じようにDPC病院における地ケアの保有率と院内転棟率を比較してございますが、ここにもやはり正の相関が見られるところでございます。
JCHO病院の地ケア稼働状況。今40数病院ございますけれども、病床稼働率は、最高は95だけれども最低で27。ここはコロナ直前、令和2年のデータです。
自宅からの入院割合も、最高は74だけれども、最低ゼロというところがある。一方で、院内転棟、ちょうど逆の関係になりますが、100%院内転棟でやっているところと、最低は0%で、外からちゃんと取っているところもあるところであります。
これは、令和3年度のJCHO病院の地ケアの入院単価を並べたもので、かなりいいところもあるんですが、例えばこの一番左の7.4万というところは短期手術で使っていますし、地ケアの病棟をコロナ病棟に転用したところは単価が高い状況であります。
ここから先が今頭を悩ませているところですが、自院からの転棟率を見ると御覧のとおりで、これは令和4年のデータですので、最近になってようやくここを何とかクリアしようという病院が、この辺はこの間までこの上にいたんですけれども、一生懸命ここを頑張って、何とかぎりぎり隙間をつくり始めている状況であります。右側のほうの病院はもともと院内転棟がそれほど多くなかったという状況であります。
これは、JCHOにおける地ケアの病床率を横軸に取って、縦軸に院内からの転棟率を見ますと、このグループ、赤点で囲ったところは、一生懸命院内転棟させているんだけれども、それでも地ケアの稼働率が低いところであります。要するに、外から全然引っ張ってこれないところで、こういう病院にこれからどう指導しようかなって。今、実際に私も病院を回って、いろいろ現場の状況も聞いて回っている状況ですが、かなりやばいよねというところであります。
一方、これは、横軸に地ケアの平均在院日数を取って、縦軸に自院からの転棟率を取ると、こういう何か極端に平均在院日数が短いグループもあるのがわかってまいりました。ここは皆さんお気づきと思いますが、短期入院の手術をここに一生懸命入れて、白内障であったり形成外科であったり、あるいは整形の短い人を入れて、ここを何とか回転させているところかなと思います。
今度これは、横軸に訪問看護ステーションの算定回数を取って、縦軸に自院からの転棟率を取っています。この左上、院内転棟がやたら多くて、でも、自院訪問看護ステーションがほとんど機能していないところが多々ありますので、この辺は、先ほどお話ありましたけれども、急ごしらえで慌てて訪問看護ステーションをつくったりしているところが多くありますので、この辺がやっぱり今さら、つくったけれども間に合ってないよねみたいな。実際に連携の病院、連携担当者の話を聞くと、既にいっぱいほかの病院の根が張っちゃっているので、今からうちがやっても間に合いませんというところ、正直な答えも返ってきたりしているところであります。
これは、JCHO病院において自宅からの緊急患者の受入数を見ますと、50件を下回る病院が半分ぐらいある。要件36未満、要件未満ということが、大半の病院がここに入ってしまうということで、なかなか地ケアで救急を受け入れるということは、JCHO病院ではほとんどできていない。
ちなみに、左上、飛び出しているところは、地ケアと療養病床だけ持っている病院が1つだけありますので、ここは地ケアが一番上流なのでここで受けていますが、それ以外はやはり難しいというところがあります。これはここのところ物議を醸している資料でありますが、高齢者救急は軽症・中等症でも、症状、徴候、診断名不明確が増えているよねという、ここであります。
ここも先ほど来お話が出ていますけれども、高齢者の救急は地ケアでいいんじゃないかという非常に乱暴な議論が起きていて、これは一昨日の中医協の入院分科会での資料でありますけれども、この真ん中の部分は、救急搬送後、他病棟を経由して地ケアに来た人と直接地ケアに来た人で入院医療の必要性を比較してみると、やっぱり直接入棟の人のほうが不安定である、あるいは不安定である状況のパーセンテージが高いというところが出ています。この上は一旦急性期病棟で診た後で地ケアに来た人たちですから、結構落ち着いてきているということがわかります。
これは、レセプトの請求点数を、自宅等からの入棟割合が8割以上、ほぼほぼ自宅から入っている病院と、自院の一般病棟からの入棟割合が8割以上、つまり、院内転棟が多いところのレセプトで比較すると、この自院から入っているところには圧倒的に手術の点数が乗ってきているということがわかります。この意味するところは何なのか、今後解釈の深掘りが必要とは思いますけれども、こういうデータの差がある。
自宅から入棟した場合と院内転棟が多い場合で、リハビリの包括出来高換算した場合で比較すると、リハビリの点数が全然違うというデータも出ています。つまり、ここをどう解釈するか、これもいろんな検討が必要かと思いますけれども、やっぱり一旦急性期で受けて院内転棟させたほうがリハをしっかりやっているって言えるんじゃないかなと私は思います。
これは今週JCHO本部に上がってきたインシデントで、200床未満のケアミックスの病院での救急事例です。どちらも中等症ぐらいで受けて、晩様子見ましょうと言って入院させたものの、3日目には急変してお亡くなりになったという症例でう。
私が大学病院にいたとき、大学病院って実は患者さんはあまり院内で亡くならないんですよね、亡くなる前に帰しちゃうので。しかしJCHOのような一般病院では、こういうふうに来てすぐ亡くなる患者さんが実際たくさんいらっしゃる。しかも、何だかよくわからないで入ってきて、その時は重症ではないのに、入院中に急変するということが少なくありません。
先ほど仲井先生も出されましたけれども、下り搬送で三次救急から地ケアが受けるということは全然問題のないところでありますが、一方で、うちのようにケアミックスの場合には、一旦急性期で受けて、ある程度落ち着かせた状態で地ケアに受けるというのがやはり現実的なのではないかと。両方の設備を持っている場合には、患者や家族はもちろん、職員にとっても安心できると思います。
昨日もとあるJCHO病院に行ってきて、循環器内科の部長ともしゃべってまいりました。とりあえず救急車で知らない人が来たらどうするって、そりゃ当然急性期で受けますよと。全く迷うことなく一旦急性期で受けた上で、落ち着けば地ケアに流しますということを言っておりますので、ここは、院内転棟が確かに、ケアミックスの病院が急性期病棟の逃げ口に使っているということがないわけではないけれども、救急で来た患者を落ち着かせるという役割はやっぱり見捨てないでいただきたいなと。それによって結局被害を被るのは患者であり、家族なんじゃないかなと思うところでございます。
最後、これは、私がJCHOの57病院長を集めたときの会議で使っている資料ですけれども、コロナジャングル。大変な思いを皆さん3年間して、これが抜けたらバラ色だぜ、お花畑だぜってみんな思ってるんじゃないかって。確かに、各病院からいろんな計画を出すと、コロナ前に戻せばこんな収支でいけますなんて甘い話が来ていますが、私は、そうじゃなくて、恐らくこれから先は未知の異次元空間が訪れるんじゃないか。
一番は、やはり地域医療構想が本格化すると、法律で縛るという話も出てきています。それから、何よりも来年医師の働き方改革。誰もやったことない。大学病院が今大変な思いをしていますが、実際に一般医療にどれだけの影響が出るか全然わかっていない。だから、私は、これは医療の地殻大変動と呼んでいます。それ以外、先ほど申したように患者は減っている、診療経費は高騰している、一方で医療費財源は縮小していてにっちもさっちもいかなくなっている、医療人材も不足しているということで、この先何が起こるかわからないけれども、しっかり患者さんのことを見据えて、いい医療を提供するために頑張らなきゃいけないんだなということで、まとまりのないぼやきでございました。
御清聴どうもありがとうございました。(拍手)
小熊豊
山本先生、どうもありがとうございました。
JCHOの苦しいところもお話しいただいて。あとは、今の日本の医療の厳しいところを、病院を代表するお立場で御発言いただいたと思います。
どうしても今山本先生にお聞きしたいことがある方はお受けしますが、いかがですか。よろしいですか。
先生、どうもありがとうございました。(拍手)
「地域包括ケア病棟、あるべき姿への挑戦」
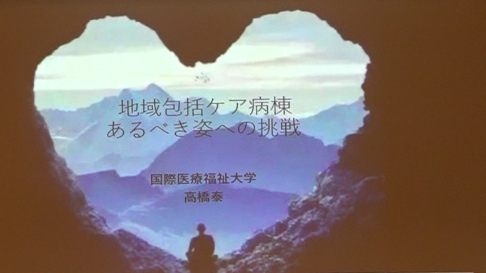

高橋泰(国際医療福祉大学大学院教授)
皆さん、こんにちは。
国際医療福祉大学の高橋です。
私、ピンで話すことが多くて、シンポジウムはどちらかというと座長が多くて、シンポジストで話すことがあまりなくて。最初だったらいいんですけれども、最後って、大体皆さんが話したことがダブるという形で、このお題を受けたときに最初に考えたのは、ダブらないようにするにはどうすればいいかなということから、全く違う視点からお話をすることを最初に決めました。とはいいながら、地ケアの話なのであまりずれてもいけないなということで。
それで、何に焦点を当てたかといいますと、団塊の世代が今から高齢者になっていくと。山本先生の最後のスライドがとっても好きで、僕もああいう世界観を持っているんですけれども、先生の世界観の中に入っていなかった、特にこの地ケアとか療養の経営のところにすごく影響がある、それから高齢者施設に影響があるのが、団塊世代の人たちが今までの高齢者と全く違いそうだなっていう、その辺のところから結論を先に言っておきますと、そこに対応できる一番可能性が高いのがこの地域包括ケア病棟かなと。だから、地ケアっていうのは、結論からいうと、これからの団塊世代が目指す老い方、死に方の望むところに近いところのサービスを提供する病棟であってほしいというのが最後の落ちになるというところを目指して、これから25分ほどお話しさせていただきます。
最初の話としましては、私の一つの継続してやっている仕事として、高齢者施設の需要予測をずっとやっております。
2014年、2016年にこの仕事を始めまして、それまでサ高住とか有料老人ホームの総病床数のデータがなかった。それを、高齢者の地域ごとの全部の施設データをダウンロードして、自分たちで出すということをやりまして、全部の施設数をつくりました。
地方都市と大都市と過疎地に分けて、各年齢が何%ぐらい施設を使うのかっていうことから必要需要数を予測して、2016年までのデータをつくって、2018年にこれまでの介護保険施設の提供はどうだったかということを調べました。
医療の西高東低っていうのは皆さん御存じだと思うんですけれども、介護の世界に西高東低があるかどうかって、ほとんどの人が知らないと思いますけれども、実は、驚くほど地域差はないんです。人口75歳以上の高齢者に対する施設数っていう形で見ると、ほとんど全国べたーっと一律にできている。大都市、地方都市、過疎地、差がなくて、しかも増加率に合わせてきれいに出ているっていう結果が出ました。
今は次官になりましたが、当時老健局長だった大島さんのところにこのデータを持っていって、これすごいよと。これは新幹線が今まで人身事故がなかったに匹敵するぐらいで、日本の高齢者施設の提供はその地域ごとの需要に応じてぴったり合って、これはある意味ものすごい成功事例だよって話をしたらすごい喜ばれて。老健局全員に配れってその場で言われました。
その後どうなるかっていうことも調べていたんですけれども、この頃から少しずつワニの口が開き始めまして、乖離し始めてきていると。要は、高齢者の増え方に合わせて施設がつくれなくなってきているということがはっきりしてきたんです。これから増えるからえらいことになりそうだなっていう形で、そういう文書を書いていた。
2014、2015ぐらいまでは4%ぐらいで伸びていたのが、真ん中の灰色の各年の増加率を示しております。ちょうどその頃、増田さんと一緒に日本創成会議に出て、首都圏大変だから、移住しないと介護施設がなくなるかもしれないみたいな物騒な発言をするのに加担したこともあったんですけれども、それを聞きまして、2018年、2019年ぐらいに上がったのは、あれは間違いなく効いたかなっていう形で、一時的にちょっと高齢者施設が増えたんですが、その後減っているんですね。
えらいことになりそうだなって思っていて。これ、特養と有老が増えて、老健はほとんど増えていないとか、こういう増加を見ていたんです。ところが、高齢者は増えていて施設はつくれなくて、施設が足りなくなるかなと思って見ていると、老健とかがらがらなんですよね。90%超えないと採算合わないんですけれども、86とか87ぐらいで、施設のほうでいうと特養が4割ぐらい、老健が3割以上赤字みたいな形で。
結構いろんなところに電話をかけて話を聞くんですけれども、先月聞いた非常に印象的なのは、特養の施設長が病院に、患者さんを回してくれっていう挨拶に来たと。20年間院長をやっているけれども、そんなことないって話を3件聞きました、同じような話を。だから、特養今空いているんですよ。
高齢者は増えて施設も足りないはずなのに、何でがらがらかっていう形で、一生懸命データで調べたんですけれども、びっくりしたことの一つが、施設の95歳以上を占める比率が急激に上がって、90歳から94歳まで、85から90歳が横ばいで、ほかのところはすごく減っている。この10年間ぐらいは高齢者施設の高齢化が猛烈に進んでいるんですね、入るのが遅くなってきている。それから、各年代の使う比率ががんがん下がってきているんです。今まで、例えば85歳以上の人が2015年に1,000人いたら、178人使っていたのが、167人に下がってるし、75から84歳も、34人使っていたのが27人っていう形で、下がってきているんですね。この傾向は今後もどうも続きそうだなと。
高齢者が増えるから施設をつくらないといけないって話していたんですけれども、入るのが遅くなっていて、しかも使う人も減ってきているという傾向があって。これは、ほかの施設群の有料のところへ行っている可能性もあるんですけれども、既存の施設に関しては、間違いなく高齢者は増えているのに空いているっていうことが起きているわけです。この辺、高齢者の動向として注目しないといけないかなというところであります。私、2002年に初めて、団塊の世代が高齢者施設に入っちゃったらえらいことになるんじゃないかっていう文書を書きました。要は、ビートルズ世代が高齢者になったときにどうなるだろうか。それから20年ぐらいずっと気にしている問題ですけれども、ついに現実になってきたんですね。
昭和元年頃に生まれた人は二十歳で終戦を迎えていて、それより上はみんな戦争経験者で耐乏生活に慣れているわけです。私、若かりし頃、明治、大正の人の死亡診断書を結構書きまして。「○○さん、ここのところ調子いいですね」って明治生まれの人に聞くと、「生き残った者の務めとして、少しでも長く生きたいね。頑張って最期までしっかり治療してくれ」って言われていた。医者も生かすのが当然で、患者も長く生きたいって、これが高齢者の平均像だったわけです。
10年たちまして昭和2桁になりますと、この人たちは60年安保を闘って、三丁目の夕日のときに二十歳を迎えているぐらいの方たちになります。
問題は団塊の世代であります。私のちょうど10年先輩ぐらいになるんですけれども、この世代は、うちの学生でいうとおばあちゃんになるんです。うちの学生にいつも言うのは、皆さんのおばあちゃんは、皆さんの年齢のとき、皆さんより10cm短いスカートをはいて、ゲバ棒を振って暴れまくっていたんだと。この人が今までと同じ高齢者と思うなと。どうなるかっていうお話なんです。まさにビートルズ世代で、安田講堂を占拠していた人たちなんですね。この人たちが今後どうなるか。
突然フランスの話になりますけれども、私は、2008年から2019年まで12年連続でフランスを視察して、フランス人の価値観とか死に方とかずっと追っています。
フランスは、1990年の頃は日本以上にがんがん延命治療で胃ろうをつくりまくっていた。一番わかりやすいのが、私が医者の活動をした1900年頃は積極的に胃ろうを、胃ろうを入れますか入れませんかという質問をする余地もなく入れていたという話です。2008年に行ったときは、胃ろうなんかなくて、自然死の形になっていて、その間に何かが起きているわけです。結構この問題にこだわっていて、正確な数字はフランスにもないんですけれども、話を聞くと、2000年前後でどうも減ってそうだなと見えてきました。ここで何があったのかっていう話です。
フランスはもともとカトリックの国で、家族も延命を望んでいた形が、全く死に方がこの間で変わってきている。2002年に患者保護、2005年にレオネッティ法という有名な法律があったんですけれども、1つ目、これフランス人は絶対に言わないですけれども、絶対に関係あるなとずっと思い続けているのが、フランスで実は、今度起きる働き改革と同じことがこの頃にあったんです。35時間労働法って、1968年だったかな、できたと思うんですけれども、2001年に医療現場にも適用されるっていう形になって、全く日本と同じことが起きたんです。このときに3万人から5万人の医者が足りなくなってきて、35時間体制でかなりばたばたした。
日本とフランスの大きな違いって、あの人たち、本当に休むことが好きなので、せっかく休める形だったのに、何とかしないといけないと。何かやめないといけないよなという感じで、あうんの呼吸で、どうもこの頃にぱたーっと胃ろうがなくなっているんじゃないかなと思えるわけです。もう一つは、2003年に猛暑が襲いました。最近は大分変わってきましたけれども、当時のパリってクーラーがなかったんですよ。突然40度みたいな形。若い人はバカンスに行って、高齢者は残って、何と1万5,000人もパリで熱中症で亡くなった。すごいなと思うのは、バカンスから帰ってこなかった人が非常に多かったっていう話もあるんです。このときの医療提供体制が大きな問題になって、これが何かやっぱりフランス人の死生観を結構変えたような事件だったんじゃないかなという形になっているわけです。何を言いたいかっていうと、フランス人もやっぱり何かのきっかけがあって死に方がどうも大きく変わった。
人生の終末期をじっと眺めていると、御飯を食べなくなる時期がある。自分で食べなくなりましたといったとき、ともかく頑張って食べさせてくださいと家族が言うのが日本で、大変な食事介助が始まる。今、世界の趨勢というか、欧米の趨勢は、間違いなくこの段階で食事介助しない。そうすると枯れていって、脱水から高カリウム血症になって、2週間ぐらいで亡くなる。食事介助は虐待と見られていることはほぼ間違いないっていうのが欧米の状況になっています。
むせて大変になったときに、胃ろうを入れるのがフランスでも当たり前だったんだけれども、これがもう間違いなく2000年前後で、話を聞いているとどうもその辺でなくなったような感じが。統計的数字はないんですけれども、なくなったことは事実なんですね。
私は、2008年にフランスの死に方が日本と違うということを発見して、いろんなところで言い始めて、2011年から日本も胃ろうがなくなったんですよね、突然。あれは実は震災がすごく利いていて。どうもその直前に、NHK、読売、朝日とかいろんなものが胃ろうってどうもよくないみたいっていうキャンペーンを張っていて、それに直面している家族がその記事を読んで、震災で生死を考えるようになって、胃ろう要りませんっていう話になって、急速に減り始めたということがあります。
今後急速に変わる日本の死生観という話で、先ほど言いました、生き残って頑張ろうっていう人たちがいて、その後、2010年代、昭和2桁の高齢者、私の母親の世代ですけれども、私は100人ぐらいうちの母親世代の人たちに、おむつを替えられたり食事介助されても生き続けたいかって。まっぴらごめんだっていう人がほとんどでした。できることならこれなしでって言っていたんですけれども、ここの世代まであまり変わらなかった。ここの劇的な価値観の変化っていうか、ここは生きたいっていうか、こう思ったんだけれどもまだ実現していなかったんですね。
ヨーロッパと日本の話を比較すると、実はヨーロッパで一番うるさいのがカトリックの神様で、プロテスタントの国はもともと延命をしないっていうのが伝統であって、イタリアとかフランスとかやっていたのが変わり始めた。東アジアは家という考え方があって、個が非常に弱い。結婚とか、どう親を死なせるかっていう話に関しては家の問題だった。ところが、まず結婚が変わったんですね。仲人付き結婚式が私の世代にはありまして、私の10も下の世代なんて仲人付きは全くやらなかった。仲人付き結婚式の撲滅運動もなかったけれども、これが突然なくなっちゃった。最近、葬式が劇的に変わっているのを皆さん感じていると思う、家族葬。周りがやったら、これでいいんだという話になると、あっという間にこういうのが広がっちゃうんですよね。
結局何を言いたいかっていうと、生き方として、自立的な形でトイレに絶対に行きたいという話と、あとは自分の望むように老いを実現したいっていう形になってきて、樹木希林さんの「死ぬときぐらい好きにさせてよ」っていう話が出てくるんじゃないかなと。
団塊の世代のときできなかったけれども、団塊ジュニアのところが何でできたかというと、親が団塊の世代なんですよ。この人たちって、主張したって親は親、子は子っていう形になってきているから、親が望むようなこういう死に方を望む人が今後増えてきて、子どもも認めるようになって、それがトレンドになったら、あっという間に変わるんじゃないかなと。そうすると、施設のあり方も病院のあり方も大きく変わるということです。
残念ながら時間になって、ビデオを見せられないですけれども、「かっこよく老いて、かっこよく死のう」っていうのが団塊世代の基本的な意見かなと。
これを実現できるところってどこかなって考えていたら、地域包括ケアのポイントオブケアとかの自立をさせるっていう考え方、それから、仲井先生が言うところのほどよいファジーさっていうのがこういうものに対応する、一番吸収する可能性があるんじゃないかなっていうことで、団塊の世代が望むような老い方、死に方をぜひ実現してほしいなっていうのが私なりの地域包括ケア病棟のあるべき姿ということで、ダブらないようなお話ができたかなと思いますけれども、これから急激に変わっていくんじゃないか、それから施設のあり方は根本的に変わっていくんじゃないかなっていうその可能性を指摘して、私のお話を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。(拍手)
小熊豊
どうもありがとうございました。
死生観、価値観の違いが医療の体制にどう影響するかっていう、本当に新しいお話を聞いたように思います。どうもありがとうございました。
コメント
小熊豊
司会の不手際で、もう10分ほど遅れてしまいました。
最後に、厚労省の眞鍋課長がいらっしゃるんですけれども、我々のこういう話をお聞きになって、何か我々を勇気づけてくれるような話ありませんか。
眞鍋馨
御指名ありがとうございます。
まずは、今日は本当にありがとうございます。
私も、この立場に立ってからこういうシンポジウムにたくさん呼ばれていますけれども、最初から最後までいたのは、実はここが初めてです。そういうことがまずは一つメッセージだと思います。
あともう一つは、高橋先生の講演、いつ聞いてもおもしろいなって思っております。ためになるなと思っております。本当に変化の激しい時期なんですよね。こういうときにどうやって日本の人はちゃんと医療を受け、亡くなる環境が整えられるか。こういうことが医療者と行政に問われていると思っています。そういう意味では、高橋先生のプレゼン、本当にいい締めになったなと思っていますし、私は地ケア病棟にとても期待しています。
以上です。
小熊豊
どうもありがとうございました。
無理やり要求したみたいで、申し訳ございません。
それでは、これで本シンポジウムを終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
