第9回地域包括ケア病棟研究大会
【パネルディスカッション】
コロナ禍の振り返りと今後の取り組み~マルチモビディテイへの対応を含めて~

【座長】加藤章信
それでは、時間となりましたので、パネルディスカッションを開催いたします。
私は、御紹介いただきましたように、この協会の副会長で、盛岡市立病院の院長をしております加藤章信と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、2020年に国内で確認されました新型コロナウイルス感染症でありますが、2021年12月末からはオミクロン株へと変異いたしました。感染により入院となる患者さんの多くは90歳代の超高齢者の方たちで、受け入れられてこられました医療機関では、医療とともに介護も提供しなければならない状況で、医療スタッフの皆様方の御苦労や御負担はさぞかしであったと拝察いたします。
一方で、医療機関を取り巻く環境には大きな変化が見られます。不要不急な受診は控えることが、いわばニューノーマルと言われるようになりました。また、人口減少と相まって、患者が減るポストコロナ時代が到来していると言えます。地域包括ケアシステムの推進役であります地域包括ケア病棟・病床を使って、逆風ともいえるこの状況に負けることなく運営していく必要があります。
5月8日からは季節性インフルエンザと同等の5類になり、新型コロナウイルス感染症がなくなったわけではないのですが、今回の学術集会で区切りとして振り返り、さらに今後の展開を見据えるという観点で、鬼塚研究大会長からこのテーマが示されたものと思います。本日は4名のパネリストに御登壇いただいておりますが、いずれもそれぞれの地域でトップランナーとして御活躍されておられ、今後の展開を含め、実践的かつチャレンジングなお話を伺えるものと期待しております。
会の進行ですが、初めに加藤から簡単なスライドをお示しし、その後、演者の先生から御発表いただき、時間を見て総合討論ができればと考えております。
それでは、初めに、加藤から司会者のスライドを数枚お示しします。
今日は、新型コロナウイルス感染症の対応の振り返りと、ポストコロナ時代に求められる地域医療ということになります。
新型コロナウイルス感染症、今さらでありますけれども、これはいわゆる新興感染症ですので、どういうライフサイクルがあるのか、治療効果のある薬剤がないといった、様々なことがございましたので、当協会の参与をお務めいただいております小山秀夫先生が、2020年に社会医療研究所の社会医療ニュースという中にお示ししておられます、いわゆるゲーム理論でいうところのMaximin戦略だと。これはどういうことかというと、勝つためではなくて、負けを少なくする決断だということで、こういった中で、それぞれの医療機関の皆様方は大変な御苦労をされてきたわけであります。途中からいろいろ状況がわかってきたわけであります。
これは2020年の国立がん研究センター松田先生のコメントでありますけれども、年間100万人ががんと診断されて、そのうちの37万人が亡くなっていると。日割りにすると、1日2,500人の方ががんと診断されて、1,000人以上が命を落としている。このときに検診をためらった人とかが結構あったので、今後問題になるんじゃないかという提唱があったわけであります。
事実、横浜市立大学の中島先生たちのJAMAにあった論文を見ますと、確かにこの時期は、こちらが胃がんですけれども、ステージⅠの発見率が下がりましたし、大腸がんではステージⅢの、いわゆる進行した大腸がんの見つかる頻度が高くなったといったこともございます。
今後、5類感染症に移行しても、感染対策は怠らない必要がありますし、いわゆる超高齢者の超過死亡を防止する必要もあります。院内の感染クラスターに注意しながら、本来病院がやらなければいけない病院機能を進めていく必要があろうかと考えております。
これは当協会の仲井先生のスライドをお借りしているのですが、午前中の基調講演、特別講演のお話のとおりでありまして、生活支援型の医療を提供するためには、院内外でのいわゆる多職種連携を持った地域包括ケアシステムをさらに進める必要があるんだということが言われているわけであります。
また、これは東京大学の秋下先生の論文から拝借していますけれども、今様々なガイドラインが用いられておりますけれども、このガイドラインというのはいわゆる成人とか若年のガイドラインでありまして、高齢者対象というものはあまり十分ではないということもありますし、高齢者の方たち、75歳以上の方たちは、身体機能の回復とか家族の負担軽減とかQOLの改善といった、いわゆる生活支援型の医療を確かに期待しているということが言えると思います。
そして、この高齢者、今日のタイトルにもなっておりますけれども、コモビディティという言葉がございます。これは、例えば糖尿病があって、腎症があって、網膜症があると。糖尿病が中心になったものでありますけれども、一方で、マルチモビディティと言われていることをマルモと。複数の疾患が同時に、糖尿病があって、心不全があって、骨粗鬆症があって、認知症があって、うつ病があってと、どれがメインだかよくわからないといった状況で、十分な対応をしないとポリファーマシーになるよということが言われているわけでありますので、こういったことに対して、それぞれの演者の先生がどういうふうに今後展開していくべきなのかといったことを拝聴できることを期待したいと思います。
「急性期ケアミックス・重点医療機関の立場から」


石川賀代(社会医療法人石川記念会HITO病院理事長)
皆様、こんにちは。本日はこのような機会を与えていただきまして、鬼塚先生はじめ皆様、どうもありがとうございます。
私が今日お話しさせていただくのは、主に私どもの病院、急性期ケアミックス型で、コロナは重点医療機関という立ち位置でしたので、それらを中心にお話しさせていただきたいと思っています。
本日の内容ですけれども、私どもの地域包括ケア病棟の紹介と、時代の転換期だということ。高齢者の見守りを含めた病棟の体制、2024年から医師の働き方改革が施行されますので、そういったことを踏まえたタスクシフト・シェア、経営的な視点を最後にまとめさせていただきます。
当院は、急性期ケアミックス型で257床の病院を運営しております。実際に地域包括ケア病棟入院料2を53床。愛媛県の東の端で、人口8万3,000人、高齢化率33%というところになりますので、全国の地方都市が直面している課題を持っている病院だと思います。
コロナの重点医療機関でしたので、急性期1病棟を一時期コロナ病床に転換していたときがあるので、昨年の病床稼働率は全体で89%、平均在院日数12.8日という結果でした。当院は、2013年に新病院になりましたが、昨年、年間救急搬送件数2,230件と、10年目にして初めて2,000件を超え、コロナと通常医療の両立ができたことは非常に大きな成果として感じております。
石川ヘルスケアグループで、医療、介護、福祉の複合体として、今現在1,400人のスタッフが働いてくれています。全てのコンセプトにおいて、ひとの『いきるを支える』を掲げています。Humanity、Interaction、Trust、Opennessと言われる英語の頭文字を取って、HITO病院と命名しております。これからは、スタッフも働きながら、介護や育児の両立が求められ、多様な働き方を実現しながら、スタッフにも選ばれる病院にならなければ、今後の地域医療の中で残っていくことは難しいのではないかと考えています。
超高齢社会、生産労働人口減だからこそ、地域医療において現状に加えての人員増ということは難しいと私は考えています。であれば、限られた労働時間の中で業務の効率化とケアの質をあげていくということの両立がなければ、私どもが掲げている「いきるを支える」ということは実現できないと思いますので、ケアに専念できる時間をいかに創出するかということが重要ではないかと考えております。
今、まさに時代の転換点です。病院医療から在宅医療へ、キュアからケアへということが言われています。先ほど加藤先生からもありましたとおり、地域包括ケア病棟では高齢者のマルチモビディティ患者を受け入れる地域診療拠点であり、多職種協働で高齢者のアウトカム向上を実践する場でもあると考えております。それを多職種で実践することで多くの加算がついていると思います。また、高齢者医療を支えていくためには全人的なケアが必要です。その中で、多職種で学ぶ環境が必須だと思っていますし、総合医療や老年医学のマインドを持つ医師の育成にも非常に寄与できるのが地域包括ケア病棟の特性と考えております。
当院は、地域包括ケア病棟を2014年から開設しておりまして、開設当時から多職種協働ということを掲げてまいりました。メディカルスタッフがお互いに学べて、その経験を活かすことができ、また、生活の視点を持ち退院支援を行うことができます。合併症予防や認知症、SST、リハビリ栄養など、急性期医療だけを見据えているだけでは決して支えられないということが当初からありました。
また、2017年からICTの利活用に取り組んできたことも、生産年齢人口減に対する一つの手段だと考えています。後ほど御説明させていただきますが、現在、全病棟において多職種協働セルケアシステムという体制を取っています。
もちろん、施設基準をクリアするというところもありますが、この2年間は、直入院のサブアキュート患者の受け入れを強化し、総合診療医による内科救急のトリアージや、専攻医を終えた総合診療医である6年目の医師が病棟のマネジメントに取り組んでくれています。診療科を越えたタスクシフト、様々な職種である専門職、非専門職が協働してケアに当たらなければアウトカム向上に寄与できないと思っていますので、そういった取り組みをお話しさせていただきます。
地ケア病棟は次世代に対応できる医療環境を十分担えるような病棟であると感じております。
2013年にHITO病院を開院いたしまして、2014年から地ケア病棟を開設し、2016年から集団リハビリ、協働リハビリ、ICTの活用。2018年からは腰HAL等の装着型サイボーグの活用。現在はVRのリハビリなど、様々なテクノロジーを活用しています。テクノロジーは、活用する側の人間が使いこなせる知識と技術を持たないと、取り入れるだけでは効率化を図ることができず、アウトカムも出ないので、使えるようになるための年数が必要になってくると思います。2020年から、看護師とセラピストを中心とした多職種協働セルケアシステムを取っています。2020年から2021年にかけて、総合診療医のフロアマネジメントを地ケア病棟で展開しています。
地ケア病棟の現状ですけれども、平均在院日数20日で、患者さんの平均年齢は76歳。2022年は入院診療単価が最も高く、昨年と比較し3,000円ぐらい上がっています。サブアキュート5割、ポストアキュート患者が半々ぐらいで、それ以前は6割・4割とポストアキュートが占めていましたので、かなりサブアキュート患者を増やしている現状になるかと思います。
これが多職種協働セルケアシステムといわれるもので、病棟を幾つかのセルに分け、このセルに対してセラピストを固定し日勤帯2名、看護師も固定で3~4名配置しています。そうすることで廊下や部屋の中で見守りができます。認知症の方も非常に多いので見守りとケア、またこのような形で廊下でミニカンファレンスを行っています。例えばWOCや、他の職種へのコンサルテーションはチャットで行いますので、ナースステーションに戻る必要はありません。
現在は、総合診療医が病棟全体を週一回回診しています。
このセルケアのメンバーが外出訓練等も実施しますので、一人の患者さんの退院まで一環してラインで関わることができます。これによって、申し送り時間の短縮や移動距離を減らすことができ、看護師の一日あたりの本来業務にかかわる時間を100分創出できました。ケアの時間に活かすことができるということで、2019年から2020年にかけては看護師の時間外が年間で6,000時間短縮できたという事例になっています。
チームチャットを活用した、それぞれの地ケア病棟での情報共有です。動画や説明が難しい装具の着用方法等については、それぞれの職種で情報共有します。グループ内の老健に対しても、医療介護連携の中で、どうしても医療用語が難しくて介護の者が分からないということが多々ありますので、こういった申し送り等で伝え切れないところを動画や写真で可視化し多職種で共有することでケアの統一化を図っています。これにより、誤嚥性肺炎等の再入院が減っている状況もございます。
これは、MSWがカメラのついたグラスをかけた状態で患者さんのお家へ伺います。実際のやり取りを動画にしておりますのでご覧ください。
[動画]
このように患者さんとご家族を巻き込みながら一緒にやり取りすることで、「早く帰りたい」、「ペットに会いたい」というように、患者さんのモチベーションが上がります。今までは看護師やセラピストが自宅に出向いていたのですが、MSW一人がご自宅へ伺い、そこから院内のスタッフと共有できることが可能になりました。
現在当院には、地ケア病棟に特定技能実習生が9名と、シニアサポーターと呼ばれる地元にお住まいの60歳以上のシニア世代の方が非常勤で勤務されており、こういった方たちが一緒になって体操やレクリエーション、排便体操に取り組んでくれています。専門職と非専門職にはそれぞれの強みがあり、シニアサポーターの方は患者さんとの年齢が非常に近く、よい相談相手になると、人生の経験値から若い技能実習生に対しても親のように親身に対応してくださり、互いにいい効果を生んでくれています。技能実習生については、地ケア病棟ではフィリピンの方たちが多いのですが、彼女たちは家族思いで、もともと明るく、周りにポジティブに接しています。語学的にはまだまだですが、こうやって音楽が流れて参加者が同じ動きの中で一体感を持って行えると、40代50代の患者さんも一緒に入ってこられ、非常に明るい雰囲気になります。デイは認知症の方など限られた人に対して行うというものではなく、スタッフも技能実習生たちも入り、お互いにモチベーションを上げ、全員参加の取り組みになります。こうしたことを最初から考えていたわけではなかったのですが、実際にやってみて素晴らしい効果があることがわかってまいりました。
診療科を超えたタスクシフトにおいては、地ケア病棟の患者さんは、圧迫骨折や大腿骨頸部骨折の術後も、ほぼ術後の経過がよければ内科的な支援で、あとは在宅調整が主ということが多いので、術後の状態が安定した時点で総合診療科へ転科します。転科後も、チャットで様々な情報のやり取り、週一回のカンファレンスは整形外科医師と共に行います。そうすることで、整形外科医師は忙しい中で手術に専念できますし、実際には先ほどの多職種協働セルケアシステムと総合診療科医師の病棟マネジメントにより、非常にスムーズな退院支援がなされています。チームチャットでのやり取りは総合診療科医師と整形外科医師も入っており、チームの中に医師事務作業補助者も入っていますので、予約や書類作成などお願いしたいことがあれば、医師事務作業補助者が作成し医師は確認するだけとなっています。どちらもストレス軽減になりますし、タスクシフトが容易に進むという一例になります。
最後に、経営的な視点を少しお話しさせていただきます。
今年の法人の目標は、「Next Normal、未来へ向けて今を生ききる」を掲げています。地ケアチームの中では、2023年度の「真心を込めて人を診る~関わるすべての人から学びを得る姿勢で~」という目標は、彼らがチームで掲げています。昨年は「マインドを変える」でした。
単に加算を取るということが目的ではなく、身体拘束を外していこう、ACPに対しての意識を高めていこうというように、自分たちで目標を決めています。実際に経営数字はこのようにクラウド上でほぼアップされていますので、みんながこのデータを見ながら、どうすれば目標をクリアできるかということを話して実行しています。
実際には、2022年度の診療報酬改定ではポストアキュート6割未満という制限ができましたので、私たちもそれに対して対策を立てないといけないということになりました。
まず、MSWからこういう状況ですというのを先ほどの、医師も含めた看護師等のチームチャットに配信します。今月はクリアできそうにない場合、地ケアのチームから医局会のチャットを活用し、「今月、直接入院割合が減っていますので、先生方、入院受け入れをお願いします」と、該当患者の患者像をイメージできるように医師へアプローチします。そうしますと、実績状況を見ながら医師にタイムリーにチャット上で配信できますし、これによって、各々意識を持ち行動することが徐々に定着してまいりますので、それほど頑張らなくてもこの条件をクリアできるということになります。現場が経営的な視点を踏まえてスピード感をもってアクションを起こすことが一番重要だと思っていますので、今後も取り組みを進めていきます。
実際にチームの中では、退院支援の質の向上ということで病棟のマネジメントをする、コアメンバーで定期的に運営のミーティングをする、スタッフ教育も自らが取り組み、課題を自らが考え実践しています。その結果、達成できたのか、達成できたらみんなのモチベーションが上がりますし、チームで実践していくことでそれぞれ一歩踏み出せる、考えられる組織、チームの一員になっていくのではないかと思っています。
本日、外にSmart-Bed Controlの担当者がいらっしゃいます。こうしたツールも活用しています。今まではMSWがエクセルで患者リストを作成していましたが、電子カルテからリアルタイムに自動で患者のリスト化ができます。氏名をクリックすると様々な情報が出てきます。当院は急性期ケアミックスですので、病床の最適解がリアルタイムでわかるということで、月全体では収入に数百万程の差が出てきますし、これからさらに病床の最適解を見出していかなければならないとは思いますが、こうしたツールを使って、みんなで考え実際に動ける集団にするということが非常に有用だと思っています。
最後のまとめになります。この青いグラフが時間外数です。2018年から2019年にかけて、日勤帯のスタッフに一人一台の業務用iPhone、という体制で取り組んでまいりました。多職種協働セルケアシステムを開始後、モバイルとのカルテ連携が始まり、病棟看護師に一人一台の貸与となりました。
コロナの受け入れが今年の3月までで208人、急性期での受け入れを行っています。一病棟を感染病棟に転換、第7波のときにかなり大きな波が来ましたので、このときには地ケアの直入の受け入れを過去最高で頑張りました。
地ケア病棟でクラスターが発生しましたが、それほど時間外は発生しておらず、去年は救急車も2,000件以上受け入れることができました。また、通常医療とコロナへの対応とかなり忙しい状況でしたが、患者数が減ったことも影響していたのか時間外はそれほど多くならず、段階的にスタッフ自らが、効率と質を両立しながらこの実績を出せたのではないかと、自信も深めているところではございます。
回リハクラスターが発生したときには、やはり地ケア病棟ではポストアキュート患者を増やさざるを得なかったので、このような状況になっております。
2030年を見据えてとありますが、地域包括ケア病棟・病床の活用というのは、やはりこれからの高齢者のマルチモビディティ患者を支えるということ。そして、実際に多職種協働の支援体制を。これは医療介護連携、在宅連携というところも含まれるかと思うのですが、これらを実践していくために、私はやはりICTの基盤は欠かせないと思っておりまして、これから時代の転換期においては、様々な働き方改革だけではなく、その人がその人らしく働きがいを持って働けること、そういった環境づくりが必要になってきます。
高齢者の方たちのマルチモビディティを支えていくために、どうやって効率化するのか、どうやって質を落とさずに医療を提供していくのか、皆さんの病院ではどのように考えておられますか。私は、やはりICTとテクノロジーの活用だと思っているのですが、やはり今、時代の転換期に考えなければいけないことだと思います。
変わらなければならないということはよく言われるのですが、どう変わったらいいかわからないというのは、皆様方も抱えている課題かもしれません。今できること、また、既に社会で活用しているものをうまく使っていくというのが私たちのやり方です。
一人一人のスタッフが自らの理念や自分たちが掲げている目標に対して、常に医療現場の中でもジャッジしながら取り組んでいるわけです。高速に意思決定し、課題を解決してアクションを起こし、それでどうだったかを振り返ること、それがOODAループの手法になります。そうしたことを実践しながら、持続可能な病院運営を自分たちで実践していく。それが今の医療には求められていると思っております。
勝手なことを申し上げてすみませんでした。
私の発表はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
加藤章信
先生、ありがとうございました。
様々な、iPhoneを用いたとか、チームチャットですか、あとはセルケアシステムとか、そういったICTを含めたものを用いながら、院内外の連携、スタッフからの自主的な目標設定などを用いて、地ケア病棟が次世代のニーズに対応できる病棟の特徴があるんだということをお示しいただいたと思います。後ほどまた登壇いただきたいと思います。
先生、ありがとうございました。(拍手)
「コロナ禍で得た富家病院のマルチモビディティ対応」
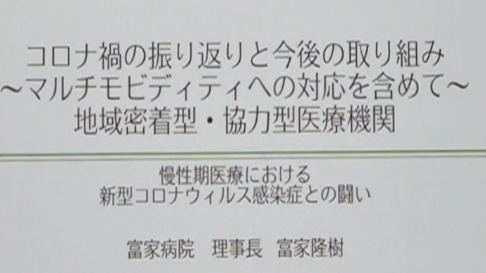

富家隆樹(医療法人社団富家会富家病院理事長)
皆さん、こんにちは。富家病院理事長の富家です。
私からは、「地域密着型・協力医療機関として、慢性期医療における新型コロナウイルス感染症との闘い」と称して話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
まず、自己紹介です。帝京大学出身で、1999年に富家病院の院長になりました。今は埼玉県慢性期医療協会の会長、そして日本慢性期医療協会の事務局長をさせていただいております。
また、変わったところでは、2021年にJCHOの城東病院がコロナ病院に全床替わるということで、日慢協として、スーパーバイズとして城東病院に行かせていただいておりました。
次に、富家病院を紹介させていただきます。富家病院は、埼玉県ふじみ野市にある、ベッド数261床の、回復期から慢性期の病院です。医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟、特殊疾患病棟、障害者病棟、地域包括ケア病棟と、回復期、そして慢性期を中心としたベッド構成になっております。
これが富家病院の外観です。茶色い建物が本館、白い建物が新館。この裏に地域包括ケア病棟のある別館があります。この桜の花はCGで盛ってあります。
富家病院の患者の内訳です。
気管切開の患者様が122名、胃ろうが128名、腸ろうが2名、人工呼吸器が46名、ITBポンプ、いわゆるバクロフェンの痙縮治療を行っている患者様が8名、入院透析が65名と。これだけ見ても、重度の患者様を積極的に診ている病院だというのがおわかりいただけるかなと思います。
私どもの富家病院の最も大きな取組の一つが、身体拘束・抑制の撤廃でございます。
例えばこの写真はインターネットからですが、胴体抑制。これは四肢抑制で、かつ抑制着といわれる、自分では脱ぎ着することのできない服を着させられております。僕が院長になったときから、こういった身体抑制をゼロにしていこうと取り組んで、2009年12月にやっと院内の抑制患者数がゼロになりました。それ以降、10年以上になりますけれども、今までこのゼロが1になったことはなくて、また、抑制回避率っていうのは、前の病院で抑制をしていた患者様が抑制をしなくて済んでいる率、富家病院で抑制をしなくて外せている率が100%。つまり、全ての患者様の抑制を外すことができております。
ここで、慢性期病院の一般的な感染症対応の背景です。
まず、コンプロマイズドホスト(感染症弱者)を多く抱えております。マルチモビディティ(多疾患併存)で、特に認知症を高率に合併しております。また、介護施設を併設している医療介護複合型の施設が多くあります。
そして、慢性期病院は医療資源に乏しくて、例えば検査体制が不十分で、外注が中心です。療養病床は包括診療になりますので、処方薬剤に制限があります。また、急性期の病院と比べると、医師・看護師の人員配置が低い施設基準になっております。
感染リテラシーの低いスタッフ、例えば介護士、看護補助者。PT・OT・STをここに加えるとセラピストから怒られるかもしれませんけれども、このような感染リテラシーの低いスタッフを急性期の病院と比べて多く抱えております。
そんな中で、富家病院の新型コロナウイルス感染症対策ポリシーを2020年の当初から考えてきました。まず、考え方ですが、新型コロナウイルス感染症というのは、世界的にも専門知識や対策が横一線ではないか。つまり、新型コロナウイルスの感染症症例を100例、1,000例経験した施設は世界的にもなくて、経験としては皆が横一線ではないかと考えました。ということは、診ようと思えば誰でも診られる。薬も治療もそんなに経験を重ねていないので、極端なことを言えば、誰でも診られると考えました。
また、東日本大震災のときを思い出しました。停電したら自分で自家発電機を用意して人工呼吸器を回す、患者の送迎車のガソリンがなかったら自分たちで買いに行く。誰かが、役所の人が助けに来てくれるわけではない、物資を届けてくれるわけではない。自分たちで用意しなければいけない。誰も守ってくれない。国や保健所や医師会や市が病院を助けにきてくれるわけではない。つまり、患者やスタッフは病院が守るというスタンスでいかないとこのコロナ禍は乗り切れないのではないかと、そういうポリシーを当初から持っていました。
そもそも、できることは限られていますから、できることは何でもやる。経験の浅い新興感染症ですから、常識は後からついてくると思いました。実際にいろんなことが、朝令暮改でころころと常識が変わっていきました。ですので、そのときそのときできることは何でもやろうというポリシーでこのコロナ禍に立ち向かっていきました。
実際の富家病院のコロナ対応として、PCRの検査機械は2020年8月に初号機を導入しました。このとき、慢性期の病院でPCRの検査機器を入れている病院はほとんどなくて、いろんな知り合いの病院から、どんな機械を入れたのかなどとたくさん質問されたのを覚えています。最終的には、5台が、第7波、第8波のときには24時間365日フル稼働しました。そして、新規入院患者全例にPCR検査、かつ、5日後に追いPCRと称して、発症前からPCRに陽性になって感染性を持つというのがコロナの特徴でしたので、追いPCRを行いました。そして、全職員に毎週1回PCR検査を義務づけました。グループの施設も同様に、全職員週一回の検査を行いました。
感染症対策としては、全職員にN95マスクを供与しました。そして、直接コロナに対応するスタッフには、全員、この写真にあるようなタイベック防護服を着用させました。すごく暑いので、バーサフローという、服につけるエアコンのようなものをつけて対応してもらいました。ECMOも購入しましたが、実際に使用することはこの3年間ありませんでした。
実際に富家病院の陽性者ですが、第1波から6波まで、陽性者の散発はありましたが、クラスターは起きませんでした。第7波まではよかったのですが、第8波でクラスターが発生してしまいました。富家病院のコロナの闘いを振り返ると、2021年8月、第5波にはデルタ株で施設入居者5名、全員透析患者様でしたが、コロナユニットで診て全て亡くなるという非常につらい思いをしました。第8波でクラスターが起きて、入院患者56名、職員144名のクラスターが起きましたが、誰も死ななかったのはよかったです。
2023年5月8日、5類の移行日まで、人工呼吸器の患者のコロナ罹患はゼロでした。気管切開の患者のコロナ罹患は22名でしたが、入院患者のコロナ患者の死亡はゼロでした。そして、非常に過酷な職場環境でしたけれども、コロナが理由の職員の退職者がゼロだったのはすごくうれしかったです。
PCR検査は4年間で2万1,800件にも上って、ピークの2022年のときには1万3,000件PCRを行いました。もう一つのコロナ対応として、新型コロナウイルス感染者対応ユニットハウス病棟というのを、いわゆるプレハブですけれども、5床だけ病院の隣の駐車場に建てて、一般の軽度から中等度までの方の対応を行いました。
このコロナユニットのメリットは、ワクチンの優先供給があって、初回は2021年3月12日に初ロット4本だけ届いて、通常の接種より1か月だけ早かったんですけれども、コロナユニットに対応する医師や看護師にワクチンを打つことができました。
感染症対応の経験値が上がったのは大きなメリットでした。このユニットでは、第3波のときには40人ぐらいの患者を診ましたが、CTを撮ると約90%に肺炎像があって、呼吸苦のない低酸素血症(Silent hypoxia)を目の当たりにしました。D-ダイマーを取るとかなりの患者様が高値を示して、いわゆる血栓をつくる新型コロナウイルス感染症が具体的に経験できたのはとても大きかったです。
そして、対応薬の早期導入に対して、アビガン、ベルクリー、ラゲブリオやステロイドなどを使う経験を得ることができました。
ここからは、富家病院の地域包括ケア病棟について話をします。
令和元年の4月に、30床の増床という形で地域包括ケア病棟ができたんですけれども、その30床の病棟は全室個室でございます。その地域包括ケア病棟の延べ入院患者は1年間で576名です。平均年齢は89.5歳で、また、当院では新規入院患者全例に長谷川式を行っていて、地域包括ケア病棟の入院患者の入院時の長谷川式は16点でした。
入院経路の内訳は、サブアキュートが6割を占めています。富家病院の地域包括ケア病棟がほかの病院と異なるのは、認知症が多いことではないかと思っております。サブアキュートの症例321例のうち、主病名が認知症となる患者は35例で、認知症の急性増悪や認知症のコントロール目的での入院になります。そのため、BPSDの合併数は31例、88%になります。BPSDは、夜間不穏、昼夜逆転、徘回、暴言、暴行、看護拒否、介護拒否などでございます。
また、ポストアキュートでは255例で、主に感染症治療、リハビリ、在宅復帰が目的で転院されます。このうち、前院で何らかの身体拘束を抑制されていた患者数は60例、23%でした。
ここで富家病院の地域包括ケア病棟とコロナについて整理すると、富家病院の地域包括ケア病棟のほとんどの患者が認知症の合併や認知機能の低下を擁しています。患者自身、居室内隔離も困難で、マスクもつけていられない方がほとんどでした。さらに、認知症患者は拒薬や点滴の自己抜去などがあり、コロナになったとしても、治療に抵抗する可能性が予測されます。そして、これは埼玉県特有かもしれませんけれども、ほかのコロナ対応病院のほとんどが、認知症を併存していると受け入れが困難になりました。そうなると、病棟でコロナが発生すると容易にクラスターになるのが想像できて、転院先もないので自院で対応しなければならない。こちらでできることは、さきにも説明した、徹底した水際対策しかありませんでした。コロナが地ケアに入ったら終わりだと、いつもどきどきしておりました。
そんな薄氷を踏むようなコロナ対応でしたが、スタッフの努力のかいあって、第7波までコロナ発生をゼロに抑えることができました。第8波は残念ながら陽性者が出てしまいましたが、全病棟に広がらずに済みました。これは、陽性者のほとんどがコロナの症状でADLが落ちて病棟内徘回することなく、何とか病棟の3分の1の10名のクラスターで抑えることができたと思っております。
第9波というか、先々週、5類になって初めて2名の陽性患者さんが地域包括ケア病棟で出ました。この2名は御夫婦で、2人とも認知症を併存していました。妻のほうはもともとADLが低かったのですが、夫は、コロナでも妻を気遣って妻の病室に行ってしまいます。ちゃんと行ければいいんですけれども、ほかの患者の部屋に間違えて入ってしまっていました。ですが、コロナの感染力が弱かったからか、幸いなことに、ほかの患者には広がらずに収束しております。
最後ですが、コロナ禍で得たものを考えてみました。
2020年3月に芸人の志村けんさんが70歳で、手厚い医療を受けられるはずの著名人にもかかわらず、あっさりと亡くなりました。この訃報を聞いたときに、私自身、理事長として、院長として、両肩にプレッシャーがすごくかかりました。デルタ株のときにコロナユニットで受けた患者がなすすべもなく状態が悪くなっていく、感染が拡大して、第4、第5、第6、7波と陽性者が増えて、自分にかかってくる電話がどんどん増える。眠ると悪夢を見るので、抑肝散を僕自身飲み続けた夜もありました。重圧がかかればかかるほど、何としても誰も死なせたくないという思いが強くなって、患者に対して、そして職員に対して強い責任感が、私がコロナで得たものだと思いました。所属長たちにもヒアリングしました。不思議なことに、全ての所属長が同じことを言いました。それはチームワークでした。コロナで倒れた同僚の穴を職種の垣根を越えて埋め合えたのは今までにないと、全ての所属長が言っていました。例えば、患者様の入浴を介護士の代わりにセラピスト、理学療法士が手伝い、医療事務が病棟の手伝いに上がってきてくれました。まさに全病院、全グループ体制で乗り越えたコロナ禍だったと思います。
以上です。御清聴ありがとうございました。(拍手)
加藤章信
富家先生、ありがとうございました。
認知症を含めた、非常に重症な疾患をお受けされている病院ですが、先生のフィロソフィーで身体拘束なしで受けていると。そういった慢性期の病院で新型コロナウイルス感染症を積極的にといいますか受けて、それに対して自分たちがどういうふうに取り組んできたか。PCRを非常に頻回にやるとか、様々な工夫をされて現在に至っていると、その中で得たものも多々あったという御発表だったと思います。後ほどまた総合討論でお願いします。
先生、ありがとうございました。(拍手)
「ポストアキュート連携型の回復患者受け入れと取り組み」
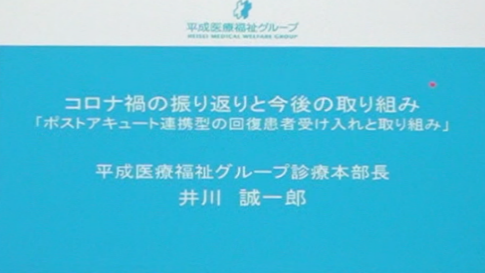

井川誠一郎(平成医療福祉グループ診療本部長)
ありがとうございます。
平成医療福祉グループというグループで診療本部長をしております井川でございます。私に与えられましたテーマはポストアキュートということで、コロナが終わった後ということですので、前のお二人のように華々しいお話はできませんし、愉快なお話も多分ほとんどないということを御了承の上、お聞きください。
それでは、始めたいと思います。
平成医療福祉グループというグループは、現在、東は千葉県から西は山口県にわたります、病院数としては26病院、1診療所、老健が11施設、特養が27、グループホーム12、有料老人ホーム7、訪問ステーション・複合型サービスを22施設。そのほかもろもろを持っておる、かなり大きなグループでございます。
その中で病院というものが、先ほどお出ししましたように、ちょうどアルファベットと同じで26ございます。26ある中で、見ていただいたらよくわかりますように、急性期というものを持っているのはほとんどないです、2つの病院だけです。基本的には、地域密着型の多機能病院をそれぞれの地域で目指しているグループでございます。
その中でありますのが、地域包括ケア病棟を持っている、ここの10病院でございます。10病院が持っておりますけれども、特徴的なのは何かと申しますと、回リハ病棟を9つの病院で持っております。1病院だけ持っていないんですけれども、そこの病院は、実を申しますと地ケア病院でございます。ほかの病院は、全て回リハを併設しているということが特徴でございます。
地ケア病棟を有する病院、もう一度お出ししますけれども、AからJまでございます。入院料としては1、2、管理料1、2など幾つかございますけれども、療養から来たものが3つ。あと残りは一般から来ているところでございます。病床数としてはこのぐらい。
他病院からの紹介割合によってポストアキュートが決められておりますので、その数字を示しますと、50%を超えているのがB、Cと、管理料を取っているところのF、それからあともう一つ、Iという病院がございますけれども、ここは一般の急性期の4を持っておりまして、結構急性期なんかからも救急車が来たりとかいうことで、形としては急性期ケアミックスと我々は判断している病院でございます。したがいまして、このBとCが今回お話をさせていただく2つの病院、ポストアキュート型でどういう形でコロナを受け取り、コロナの方々がどういうふうな状況であったか、もしくは、その後アウトカムはどうであったかというお話をさせていただこうと思っております。
もう一度、BとCの2つの病院をお出ししております。
一つの病院は、地ケア病院以外に回リハ病棟だけでございます。Cの病院は、同時に療養病棟も持っております。この3つを併用した地域多機能病院となっております。が
受け入れポストコロナの患者状況でございます。
2020年4月から2023年5月まででございますけれども、B病院にはポストコロナの患者さんは132名、年齢分布としましては35歳から103歳、平均81歳ぐらいで、男女比は、53人と79人と、女性優位でございました。コロナ発生から入院受け入れまでの平均日数、発症からは8日から281日。8日といいますと、ぎりぎりポストコロナとして扱えるぐらいのレベルで、急性期病院に入られて、割と早目に取らせていただいている。平均しますと48日ぐらいかかっています。入院時のFIMは18点から114点、平均しますと51。入院日数としましては3日から170日、人によっては170日ぐらいおられた方もおられますが平均しますと67.2日。
一方、C病院のほうは、69名の入院を受けまして、年齢分布は大体同じぐらいで、平均すると79歳。男女比が、男性がこちらは40名、女性が29名と、なぜかわかりませんけれどもB病院と逆転しているんですね。こちらのほうは男性が多いという結果が出てきております。コロナ発症から入院受け入れまでの平均日数も12日から195日と、平均すると45.3日と、B病院とそれほど変わらない。入院時FIMも18点から111点、平均しますと50点台というところでございます。入院日数も、こちらのほうは療養病床がございますので、5日から184日とちょっと長目のものがございました。
B病院の入院元は92.4%が急性期病院でございました。あと、精神科病院、慢性期病院から搬送されてこられた方もおられます。それから、居住系の施設におられて、そこでクラスターが起こった後に来られた方が1名おられました。自宅・宿泊療養施設、いわゆるコロナホテルから廃用みたいな形になって、ポストコロナとしてその先生から御紹介いただいた方が6名おられます。
C病院は69名ですけれども、そのうちの82.6%が急性期病院。東京都は医療支援型施設というのがあるんですね、都がつくったような施設ですが。大阪でいうと、インテックス大阪みたいなところにでっかい1,000床ぐらいのベッドをつくったんですが、実際は30床しか使わなくて、えらい税金を無駄遣いしたなと言われた、そういう施設だろうと思うんですけれども、そういうところから3名ほど来られています。あと、介護保険施設から、これもクラスターが起こるところでございますけれども、そこで3人。6名が自宅・宿泊療養施設、コロナホテルなどから搬送されてまいりました。
この患者さん方のもともとの状態でございますけれども、入院時のアルブミンと我々の病院に入院された日数を比較しております。
赤い点は死亡退院で、青いのが生存で退院です。転院というのは、中には慢性期病院に移られた方もおられますけれども、症状悪化ということで早くに帰られている方が、中には急性期の方、ここら辺の方は割と急性期病院に帰られている、ここら辺はどちらかというと慢性期病院に移られた方が多いです。そう見ますと結構ばらばらで、入院時のアルブミンとはそんなに関係なかった。よく我々は、入院時の低栄養というのは非常に将来の死亡率に関わってくるんだということでお示ししますけれども、今回、コロナに関してはあまり関係なかったのかなという感じはいたします。
入院時の血液検査、全体をお示しします。
先ほどお示ししましたように、アルブミンはB病院で1.7から4.8、平均3.1です。相変わらず急性期病院から来る中で、BUN240とかいう超脱水という方がおられますけれども、非常に少なくて、平均しますと19.6ぐらいのBUNでございました。クレアチンが割と正常値の方が多くて、平均しますと0.8。電解質に関しては、このBUN 240の方が同時にNa180ぐらいありましたので、お一方すごい方がおられましたけれども、やっぱりちょっと低ナトリウムの方が多かったですかね、123.3から180.2、平均139。ヘモグロビンも、割と貧血は進んでおられない方が、今までの我々の慢性期のほうに移ってこられる方のデータからすると少ないという印象でございます。
C病院もほぼ同様です。割と脱水のほうは軽いです、52.9ぐらいしかなかった。クレアチンもそれほど悪化せずに送っていただきましたし、貧血もそれほどひどくないというのが現状でございました。
入院元別の入院日数、これは箱ひげ図で示しております。
ぺけの部分が平均値になります。棒線が中央値でございます。それぞれ比較しますと、その他のところだけ少し異常な形になりますけれども、これ、病院の形態が、精神科病院とかいろいろ入っている、B病院のほうに入っていますので、N数が極端に少ないために、何も言えないと思いますけれども、大体あまり変わらない。入院元別でどこどこから来られた方々が非常に入院日数が長かったとか、そういうことは言えませんでした。
一方、入院日数とFIM利得。ほとんどの方が廃用症候群ですので、FIMを測定しております。入院時と退院時に測っております。
その利得を見ますと、B病院、C病院ともにまあまあ、ちょっと曲線的には上がっていくかなと思いますけれども、きっちり測りますと係数は有意ではないというレベルで、見た目、少し日数が増えればFIMは上がっているというところでございます。
受け入れ先の病棟です。ここで問題なのは、今お出ししたのは全ての病棟、回リハ病棟に入った者も、地ケア病棟に入った者も、一緒くたにお出ししています。こういうふうに見ますと、問題は、回リハ病棟に入った者と地ケア病棟に入った者がどれだけあって、どのぐらい違うのかという話ですけれども、実を申しますと、回リハ病棟に入った方が84.1%です。地ケア病棟に入った方は、B病院では15.9%しかありませんでした。C病院は約半々で、あとさらに医療療養に直接入られた方が17%ぐらいありました。それぞれで、B病院の死亡率とか転帰を見てみますと、あんまり変わらないかな。死亡の方が少し全体としてはおられましたので、転院と生存退院を比較するとあまり変わらない。
入院元別で見ても、そんなに遜色はありませんでした。死亡率は全体として3.8%、急性期病院から来られた方だけです。やはり少しADLやら何やら、栄養やらが少し低かったのかなという気はいたしますけれども、そういう状況でございました。
C病院も同じく、全体として4分の3ぐらいが生存退院、それぞれ8分の1ずつぐらいが、死亡、転院ということでございますけれども、地ケア病棟に入られた方も結構亡くなられているということでございました。これも同じく入院元別で比較しておりますけれども、それほどB病院と変化はなくて、急性期から来られた方が8人中7人は、やはり死亡患者としては多かった。
そういたしますと、どうやってこの病院に、どこの病棟に入れるのに決めたのという話が出るわけですね。実はこの2つともの病院、東京の病院でございまして、私、大阪に住んでおりまして全然わからないので、それぞれの事務長とかに電話で問い合わせて聞いてみました。そうすると、どうやって決めているかという基準は、結構曖昧ですけれども、彼らの意見、話を聞きますと、廃用として回リハで取るのがまず大原則ですということです。中心としてやっぱりやります。長期入院の希望者はやはり療養病棟で受け入れるようにしています。コロナ特例のために多くの施設基準が緩和されておって、割と病棟選択の自由が高いので、ぶっちゃけて言えば儲かるところに入れますということになっておるわけですね。さらに、全ての病床が満床の場合どこに取るのという話を聞きますと、やはりこれは回リハ病棟をオーバーベッドにして使いますというお話でございました。
とすると、地ケア病棟での受け入れはどういう患者さんか。リハ疾患がつかない、医療区分がつかないというか、1ですね。長期入院を希望しているけれども、療養病棟が埋まっていなくて早期に取らないといけない。あとは、短期で退院したい、1週間ぐらいで帰りたいとおっしゃっている方。あと、回リハ、療養が満床ですぐに受け入れが必要。回転がいいので、受けやすい地ケアで受けるという意見もございました。
そうすると、この地ケアと回リハで受けた患者さんのアウトカムといいますか、そういうものは同じでないとおかしいんですね。でないと、患者さんを選択した理由にならない。そういうものをちょっと見ていこうと思って、幾つかデータを出しています。
先ほど、ベースとしてアルブミンを出しておりましたけれども、入院時のアルブミンは、実は、B病院で回リハ病棟こんな感じ、死亡の感じはこれです、変わりません。地ケア病棟にはこんな感じで、値もばらついているということです。
これは、入院時のFIMです。入院時のFIMは、B病院は、回リハと地ケアの間に有意差は特になかった。C病院も同じく、こんな感じですね。ただ、こうやって見ますと、療養病棟だけ異様に低いんですね。全体的に見ますと、回リハはやっぱり2.5以上、入院時アルブミンあるんだけれども、地ケアはもう少し低いのがばーっと混ざっていて、療養に至っては3以下ぐらいばっかりになっているという。その中で恐らくきっと入れる、連携室の人たちのバイアスみたいなものが無意識のうちに多分入っていたのではないかなという気はいたしております。
その中で入棟病棟別で入院時のFIMを見ますと、B病院だけやっぱり低いんですね、療養だけが極端に低い。これ「NP」、間違いですね、「NS」です。回リハと地ケア、この間は変わりませんけれども、この療養との間は明らかに低い。FIM利得をB病院で見ますと、赤いのが地ケア病棟です。一方、回リハはこちらです。この2つを比較しますと、実はp<0.001の有意差が出てきてしまいました。つまり、B病院における回リハ病棟に入られた方と地ケア病棟に入られた方は、回リハ病棟に入られた方のほうがFIM利得が高かったという結果が出たわけでございます。
C病院でも同じことを見てみますと、回リハ、地ケア、療養、あの場で見ていましても有意差がそれぞれ、一つの群から出たことがないということになりまして、地ケアを中心に検定を行いますと、回リハ、地ケアで0.005、地ケアと療養でも0.05という感じで、実はおもしろいのは、療養が非常に高い。非常に長期入院なんですけれども、結果的には、すごくゆっくりゆっくりですけれどもFIM利得取れているんですね。それに比べて、この赤いところが地ケアですから、結構低いところに群として存在する。
我々のグループ、この2つとも、先ほど申し上げましたように東京のグループ病院でございますので、回復期リハビリテーションというのは基本的にできる限り9単位ぎりぎりやっています。大阪とか山口になりますと途中で、特に脳血管以外のリハビリ、疾患別リハは切られるんですけれども、東京は切られませんのでほとんど9単位に近い。一方、それに対して地ケアっていうのは、どうやっても3単位から1.4単位ぐらいまでというのが現状でございます。倍ぐらいの差があるので、やっぱりこの差はどうしても出てくるのかなという気がいたしております。
そういうところから考えますと、地ケア病棟と回リハ病棟を併設する場合、ポストコロナ患者の受け入れは原則として回リハ病棟で行われておりましたけれども、一部患者は状態によってバイアスが入っていたような気がいたします。あと、地ケア病棟入院患者では、回リハ病棟、療養病棟に入棟した患者に比べてFIM利得が少ないということがございますので、今後、これからどうしていくかというのはやはり皆さんと一緒に考えたいと思いまして、この題材をまたディスカッションに加えていただければなと思っております。
私の発表は以上でございます。ありがとうございました。(拍手)
加藤章信
先生、ありがとうございました。
平成医療福祉グループ26病院の中で、ポストアキュート受け入れの2病院にフォーカスを当てて、コロナの患者さんをどういうふうに受け入れてきたか。アルブミン値とかFIM利得とか、項目を立てて、そしてどういう特徴があったかということをお示しされましたし、今後どういうふうに使っていくかということの一つのヒントもお示しされたのかなと思っております。
先生、ありがとうございました。
また後ほどよろしくお願いいたします。
「地域包括ケア病棟が地域に果たせる役割と挑戦」
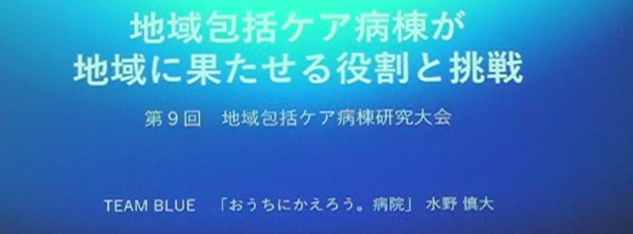

水野慎大(医療法人社団焔おうちにかえろう病院院長)
よろしくお願いします。
今回こういう御縁をいただきまして、仲井会長はじめ、鬼塚先生含め諸先生方からこのような機会をいただいたこと、大変ありがたく思っております。
我々の病院は、今まで御発表あった先生方の御施設と違って、歴史も非常に浅い、開院してまだ2年の病院ですし、規模としても、たった120床。かつ、地域包括ケア病床しか持っていない、ほぼ丸腰で戦っているような病院になります。
恐らく今回お声かけいただいた一つの要素として、もともと在宅診療を中心にやっていた診療所が病院をつくったという、在宅屋がつくった地域包括ケア病棟ということで注目していただいて、お声かけをいただいたのかなと認識しておりますので、在宅とのつながりというところも含めて、我々がどのようなことを今考え、そしてどのようなものが少しずつ見えてきているのかということをお話しさせていただければと思います。そのため、今回、コロナという部分に関しては強く打ち出せる部分が決して多くありません。そもそも、コロナの真っ最中にできた病院ですので、コロナ前後の違いが私の中で全くわからない状況です。ただ、コロナを通じて、地域とのつながりの中で、地域包括ケア病棟がやはりこういう役割を果たせるといいよねというのが自分の中で見えてきた部分もありますので、そういったことを最後に御紹介できればと思っております。
今回お話しさせていただく内容に関しては、最初に法人の紹介をさせていただきまして、その後、我々が取り組んでいる地域包括ケア病棟における在宅復帰支援、在宅というものを見据えた支援に関しての御紹介、それから、その内容になりますけれども、患者・家族にとっての果たすべき役割、医療人育成という観点で考えたときに果たすべき役割、そしてコロナとの関連を含めてというところで御紹介させていただきます。
まず、法人の紹介を最初にさせていただきます。
我々の法人、開設して10年ちょっと、11年目に入ったところになりますが、代表の安井が板橋区の団地の一部屋を借りて開設した訪問診療所がスタートになります。その当初から、「自宅で自分らしく死ねる。そういう世の中を作る。」ということを理念として掲げてまいりました。医療法人として死というものを前面に打ち出すことにいろんな御意見があることは十分承知しておりますけれども、あえて終末期に近い方との関わりが多い在宅診療の人間として死から目を背けないということ、そして、そこに最後まで走り切るんだという決意も含めて、このような理念としております。
最初、法人開設当初は、この世の中を作るということに関しては、ぴんとこないまま、言葉を一旦置いてみたところでありますけれども、結果として、今回病院をつくるきっかけとなったのは、我々が世の中づくりにおいて何のトライができるんだろうということを考えて、一つ、病院をつくるという解を得たというところで、私自身にとっては非常に大きな一文になっております。
概要です。
先ほどお話ししたように、10年前にやまと診療所という在宅診療専門の診療所を開設いたしまして、そのときは3人でスタートしております。私が入職したのが4年半ほど前になりますけれども、そのときにはまだスタッフ数65名ぐらいでした。ここから4~5年の間で、今350名まで増えております。病院単体のスタッフ数でいきますと130名程度となっておりますが、常勤医の大半、非常勤医の大半は在宅の医者です。開院当初は私一人で病棟全部を診ていたような状況ですので、病院単体としての医者の数は3名から4名程度と御認識いただければと思います。ただ、一方で、看護師やセラピストは多くが病院所属であります。
診療所としては、患者数1,000名強という規模感でありまして、板橋区内では同様の規模がもう1か所ありまして、区内ではトップクラスの患者数となっております。
また、当院の特徴として、在宅でのお看取りをさせていただく患者さんの数は、単一の診療所としてはかなり多いほうだと認識しておりますけれども、年間で550名、1日に1人から2人の方を御自宅でお看取りさせていただいているという現状です。昨日の夜も私、在宅の当番でしたけれども、お一人の方をお看取りさせていただいてという形で、スピード感をもって対応できる。これだけの規模感があるのでというところで、がん末の方が多いということで、結果として御自宅での看取り患者数が増えているという現状です。
事業体としては、10年間で大分拡充してまいりました。当初は、左下にありますやまと診療所からスタートしました。最初からこの絵を描いていたわけでは全くありません。浮かび上がってきた課題に対してどう取り組んでいくかと考えた結果、今はこのような3事業体となっております。
我々の中では、おうち事業、やまと事業、ごはん事業と呼んでおりますけれども、病院を開設するに当たって何よりも優先すべきは看護師さんを確保するということで、看護師さんを確保する目的が裏テーマとしてあって、「おうちでよかった。訪問看護」というところを開院1年前に設けております。結果として、こちらに関しては、看護師が病棟を経験し、かつ在宅を経験するチャンスを得る、そういったフィールドを用意することにもつながりまして、後ほど御紹介します人材教育としては非常に有用なものとなっております。
また、やはり自宅に帰るということを見据えたときに、食べるということが非常に大きなテーマ、もしくは障壁となりがちですので、そういったところにコミットする上で、摂食嚥下に特化した訪問歯科は非常に少ないという実態がある中で、摂食嚥下を得意としている歯科医師を呼びまして、彼を中心に、「ごはんがたべたい。歯科クリニック」というところを開設して、この歯科クリニックが病院の中にも訪問の一件として回ってきてもらっているという立てつけとしております。
そもそも、病院開設に至った経緯でありますけれども、これはほかの病院の先生からお話を伺っても大体同様の数字だったんですけれども、我々の診療所で診ている患者さんが、どれだけ数が増えてきても、常に毎月5%程度の方が入院を必要とされております。下から2行目のところ、6.1%、6.25%というところですね。こういった5~6%の方のうち、結果としてまた在宅療養に戻ってこられる方、在宅復帰率は60%前後でした。裏を返せば、5%入院したうちの4割程度は在宅に戻ってこれないということを見せつけられた数字であります。
単純計算で、我々1,000人規模の診療所ですと、毎月30名程度が在宅療養から脱落を余儀なくされているということになります。戻ってきたい方が全員だとは思いませんけれども、例えば半分の方が本当は戻りたいとすると、15名掛ける12か月で、200名弱の方が戻れない、1,000人規模で200名弱が戻れないとなると、全国で在宅療養を受けている100万人という患者さんに関してその数字を当て込むと、どれだけの方が戻りたいけれども戻れないということになっているんだろうというところで、ここを何とかつなげられないかということを考えておりました。
我々、がん末の患者さんが多いと先ほど御紹介しましたけれども、がん末の方、やはり2~3か月の短期集中型の、ある種の急性期在宅のような形の関わりで、御自宅で最期を迎えられる方は非常に多いですし、それに向けてのノウハウは当診療所の中でも多く蓄積してきました。なので、こういったケースは大体御自宅で過ごせるということは見えてきた一方で、我々の弱点としては、フレイル、認知症の方、もしくは現在世の中を席捲しております心不全パンデミックの患者さんをどのように支え切ったらいいのかという、この長期戦略としての在宅療養への向き合い方がわからないというのが正直なところでした。
これが診療所を開設してから5~6年の間で少しずつ自分たちの中で課題感として見えてきて、どうやってここを突破するかと考えたときに、やはり病院から帰すときの、帰せる帰せないという医療者のフィルターが大きな要素ではないかと考えていました。しかも、在宅屋としては、病院でどういうフィルターがかかっているかを知らない。相手を知らなければ、自分たちもそこに対する関わりを考えられない。だったら病院をつくろうということで、病院をつくることにしました。なので、そもそも選択肢としては、地域包括ケア病棟以外の選択肢は我々の中ではありませんでした。ということで、2021年4月、コロナ禍の真っ最中ではありましたけれども、地域包括ケア病棟単独として120床の病院を開院させていただく運びとなりました。
ここで我々が最もやりたかったことは、そもそもの課題感として感じていた、病院から家に帰すということ、ここに対する関わりをどのように工夫していったら、もしくはどのような人を育てていったら、それがよりスムーズになるんだろうということでしたので、在宅復帰支援にはかなり力を注いでまいりました。
まだ発展途上ではありますけれども、今の私の中での考えを紹介させていただければと思います。
こちらは、地域包括ケアの先生方にとっては当たり前のことだと思いますけれども、「ときどき入院、ほぼ在宅」というものを支える上で、つまり、おうちということの生活を支える手段として地域包括ケア病棟を考えたときに、ポストアキュート、サブアキュートという、この二大機能は決して外せないものだと認識しております。ここで、ポストアキュートというところが、在宅復帰の上で壁になることが比較的大きいと考えております。サブアキュートは、もともと在宅で過ごされていた方が中心になりますので、帰る上での障壁は少し低いのかなと思いますけれども、急性期から在宅に移行する、そういったときに地域包括ケア病棟を介することによってどのようなことができるんだろう、そもそもそこでの時間は何が必要なんだろうというのを考えてまいりました。
急性期医療機関では、当然ですけれども、患者さんも医療者も命を守るということを中心に掲げて、それに向けて全力を注いでいきます。ただ、在宅療養においては、必ずしも命を守るが正解でないということを在宅屋としては実感することが多かった。その中で、命を守る思想から暮らしを守る思想へ思想の転換をする。そこは急にはできないので、やはり地域包括ケア病棟という時間を使うことによって思想の転換を進めていくことができるのではないかと。そのときには、患者さんたちにとって、もしくは家族にとっては、急性期医療機関では、できなかいことをできるようにしよう、頑張りましょうという思想が中心になっていますけれども、一方で、在宅に戻る上では、今の不自由を抱えた体という現状を受け止めた上で、それでも、まだできることを積み上げていくことに患者さんや御家族の思想も転換していただくことが大事なのではないかなと考えております。
また、急性期医療機関と在宅療養では、登場人物、主役が全く替わります。医師、看護師、セラピストが中心になりがちな急性期医療機関から、本人、家族、もしくは介護者が中心になってくる、そういった登場人物、主役の交代の時間も当然必要になってきます。当たり前のことではありますけれども、私自身、時々忘れがちなこととしては、使う保険も主役が変わるということです。医療保険から介護保険へ主役が交代する、こういったところも、退院調整という中で使う制度を無意識のうちに変えてはいるんですけれども、あえて意識することで何が必要なのかという視点の切り替えもやっていく。そういったバトンをつなぐ時間と場所が提供できるのが地域包括ケア病棟だと、私の中では理解しております。
そういったことを考えたときに、そのバトンをつなぐためには何が必要か。先ほどの二本柱を今度役割で考えたときに、家族や患者さんがおうちというものを想像できるようになる、そういったために必要な時間というものがあります。そこを提供するという柱と、あとは、おうちで何が行われているのかというのを医療者が想像できないことが多いと思うんですけれども、そういうことを想像できる医療人を育成するためには地域包括ケア病棟ほど適した病棟はないと考えておりますので、この医療人の育成というのも決して外すことができない柱だと考えております。
まず1点目、患者さんが、家族がおうちを想像できる、そういったことにつながる関わりというもので我々の模索していることを御紹介させていただきます。
テーマとしては、不安をどれだけ小さくして希望をどれだけ大きくするか、そこに尽きるんだと思います。不安を小さくするのであって、ゼロにすることを目指さないというところは、やはりスタッフの間でも、患者さん家族との間でも合意をすることが必要だと思います。
当たり前ですけれども、我々、先生方も含めて、不安がゼロで生きている人はいないんですけれども、帰るときには不安がゼロでなければ帰らないと、帰れないと決めつけている方は意外と多いです。ただ、不安というものは付き合っていくものだけれども、小さくできる不安は小さくしましょうというところが一つ。それから、不安は残っていても帰るという場合には、これは心配だけれども、これがしたいから帰るということが必要になってくる。動機づけになるかと思いますけれども、その希望を大きくする関わり。
不安を小さくする関わりとしては、先ほどの御発表の中でも御紹介ありましたけれども、スタッフ含めおうちに行って家屋調査をする、家を見ることによってモチベーションも上がっていく。それから、御家族にはリハビリを見学していただくことによって、こういう状態になっているんだ、これだったら思ったよりいけそうだなと思ってもらうとか。
あとは、我々の中で時々チャレンジとして使っているのは、一晩泊まり込み介護体験というものをやっています。個室を用意しまして、そちらに御家族に泊まり込んでもらって、極力看護師は行かない。ナースコールを自主的に押してください、それが家に帰ったら訪問看護師さんを呼ぶことになりますというところをお伝えした上で、家族に介護手技の指導をした上で、一晩泊まり込んでやってみてもらう。夜がやはり家族にとっては怖いので、泊まり込んでもらうことによって、どういうときに呼べばいいのか、こういったことが起きるんだ、これは意外といけそうだ。これを通じてやっぱり無理ですと言う方もいます。ただ、それも大事なトライだと思います。トライした上で駄目です、それはいいと思っています。
また、希望を増やす関わりとしては、家族に会っていただく。これがやはりコロナ禍で奪われた最大のデメリットだと思っていますけれども、当院では、開院当初から面会は一切禁止しておりません、常に受け入れ続けております。それは、我々の果たす役割としてとても大きなものであると考え、リスクは承知の上です。これによってクラスターも起きました。ただ、それを通じて得るもののほうが圧倒的に多いということを考えて、これは貫き通しております。
また、帰る上では、一人では生きないですし、家族だけでも生きていけません。地域を意識してもらうことも必要ですし、日常を取り戻すというよりも思い出してもらう。そういった関わりによって希望が少しずつ増えていくと考えております。
そうすると当然必要になるのが、これまでどうやって生きてきたんだろう、これからどうやって生きていきたいんだろうという、自分の過去を振り返り未来を考える、こういった関わりです。それは簡単にその人たちだけではできないと思っていますので、それを一緒に考えるスタッフがそこにいるということがやはり大きな武器になると考えております。
そのために必要な要素として私の中で考えたものは、この3つだと思っております。曖昧さ、コミュニケーション、時間の共有。
ちょっとわかりにくい部分があるかと思いますけれども、どの職種だからこの仕事というところの切り分けは必ずしも明文化しない。立場、役割も含めてわかりにくくする。コミュニケーションに関しては、家族と患者さんも当然ですけれども、スタッフと家族、スタッフと患者さん、スタッフ同士、こういったところでコミュニケーションが多く生まれなければ一緒に考えることは不可能です。なので、こういったところを生みやすくする。それから、面会、泊まり込み、家屋調査を通じて時間を共有することによって合意をしやすくなるというところがあると考え、これを建築のテーマとして空間デザインに落とし込んでつくってまいりました。
こういった空間ができてこういった人たちが育ってくると、医者と看護師、セラピストと関わったというよりも、何々さんが一緒にあの病院で話を聞いてくれて、こういう相談に乗ってくれて、だからこうしようと思ったんだよねっていう形で、人と人との交わりが生まれて、そうすれば、「おうちにかえろう。」と家族や患者さんが言ってくれるだろうということを考えて病院づくりを進めてまいりました。患者さんや家族のセリフなので、当院の名前には「おうちにかえろう。」と「。」が入っております。帰ろう、医療者によるレッツゴーではないです。
そういったものを意識したときに、まず一つ、地域とのつながりというところで、1階フロアをつくってまいりました。外から丸見えのリハビリ室にしました。恥ずかしいと思われるんじゃないかということをよく聞かれますが、恥ずかしいと思ったらめっけもんだと思っています。恥ずかしいということは、外に対する意識が生まれてきたということで、外を意識し始めたら、どうやって生きていこうかって考え始めたんだろうなと思います。
また、外部の人が気軽に使えるカフェを1階フロアの真ん中に用意することによって、リハビリをしている人の脇で外の人がコーヒーを飲んでいるという空間をつくることができています。この近隣、幸いカフェがありませんので、お客さんの半分は外部の、全く病院と関係がない人という、立地にもある意味恵まれたということにはなっております。
また、病棟の中では、患者さんや家族、スタッフがつながりやすくするために、ナースステーションをあえて極力最小限のスペースにしました。ナースステーションが大きくあると、医者にせよ看護師にせよ、その中にこもってしまってガードを固めてしまうので、最小限のスペースにすることで外に押し出して、石川先生の御発表にもありましたけれども、廊下にいっぱいスタッフが散らばっているということで、ちょっとした声かけがお互いにしやすい状況が生まれています。
また、病室の中にできるだけ病院っぽいものを排除することによって、落ち着いて考えるということ。内省の時間も必要だと思いますので、そういったものを生みやすいような病室にしてまいりました。
そのために、ナースコールシステムは、有線のナースコールしか今までなかったと思うんですけれども、無線のナースコールシステムを新たに開発しまして導入いたしました。ベンチャー企業と共同開発したんですけれども、これによってナースコールの赤やオレンジ色の、ピッと線が出ているボタンがない状況がつくれた。また、いろんなものを、思い出の写真とか枕元にいっぱい張ってもらえるように、こういった穴の開いたボードを用意しました。人によっては、お仏壇の写真をかけて毎日拝んでいる方もいらっしゃいましたけれども、そういったもので日常に少しずつ近づいていってもらおうということを意図しております。
こういったことから、コミュニティが発生しやすくなったと実感しています。患者さんのキャラクターに大分依存するんですけれども、時としてこういった井戸端会議をずっとやっている人たちというのが、パワーのあるおばあちゃんが3人ぐらい集まるとこれができるんですけれども、朝、リハビリにみんながここから出かけていって、お帰りなさいとここに帰ってくる状況ですとか、隣にいる人がちょっとむせ込んだときにすっと立ち上がってケアしてくれるというところで、普段の生活ってどうだったかなというのが少しずつ思い出してもらえるようなコミュニティができているのではないかと思います。
また、もう一つの軸である医療人の育成ということに関して御紹介させていただきます。
先ほど申し上げましたように、急性期医療機関では命を守る、そして在宅医療機関では暮らしを支える。そういったことで会話をしていても、やはり言葉が通じない、考えていることがよくわからないと時々思われる先生方も多いかと思いますけれども、そもそも言語が違うんだと考えたほうがいいのかなと思っております。地域包括ケア病棟に関わる医療スタッフ、医療人に関しては、ここの通訳者になるということが一つの要素として大事なのかなと考えています。
そのために活用しているもの。これはコミュニケーション量を増やすことでしかなし得ないと思っておりますので、左側に御紹介したのは、やまと診療所の在宅の各エリアのチームと病院スタッフとがひたすら書きまくっているチャットです。チャットなので、ある程度秘匿性は担保されている状況はありますけれども、ここに、患者さんがどんなふうなことを大事にして家で生活しているんだということを在宅側から書いてもらい、病院スタッフはここに、入院中、実はこんなことに反応したんですとか、こんなことで怒っちゃいましたとか、家族がこんなことを漏らしていましたということを書き込む。それによってお互いの見ている目線を少しずつ少しずつ合わせていくという作業をしております。
また、今回、病院を立ち上げるに当たって、新たに電子カルテを、クラウド型のカルテシステムを開発しております。もともと在宅でのカルテ、モバカルネットというかなり普及しているカルテシステムがあるんですけれども、こちらの病院版をNTTと共同開発しておりまして、これを立ち上げることによってカルテがスムーズにお互いのぞき合えるという連携の形を最終的にはつくり上げたいなと考えております。双方に行き来ができますので、双方のいろんな背景ですとか、サマリー情報の部分もそうですし、あと、患者さんが漏らした言葉ものぞき合えるという形で、人として見ていくことがしやすくなるということが実現できているかと思います。
また、新たな試みとして、人を循環させるということもやはり重要なことだと思っておりますので、積極的に行ってまいりました。看護師に関しては、病棟と訪問看護のローテーションを1年交代でやっているスタッフは、まだ4~5人程度ですけれども、おりますし、人によっては、週3病棟、週1訪看という人もいます。また、病棟看護師が訪問看護に同行させてもらって、家でどうやってみんな生きているんだというのをのぞかせてもらうことで、今までわかっちゃいたけれども想像でしかなかったことが現実として見えてくるということも得られています。
また、セラピストに関しては、これはセラピストが勝手に自分で開発してくれたプログラムですが、訪問リハと病棟の勤務の移行もそうですし、逆もそうです。また、病棟リハのメンバーに訪問を体験してもらうプログラムとして、1年コースと3か月交代コースというのをスタッフ自らつくり上げて、循環を進めております。
さらに、そこが難しいのは医者にはなってくるんですけれども、総合診療科専門研修医の育成プログラムを今年度から開始いたしました。在宅の診療所と共同で、みんなで考える医師になる、そういった医師を育てるということをテーマに掲げたプログラムをつくり始めました。
この中では、スタートアップコース、スキルアップコース、キャリアチェンジコースと称しまして、後期研修というコースから、ちょっと在宅を、1年間でいいから経験したいというコース、また、開業を見据えてそれに向けて勉強したいというコース、そういったものをそれぞれ用意して、いろんな入口から医師が入ってきてもらいやすくなる形。決して在宅医にならなくてもいいけれども、在宅を知っている人になってねというコースをつくってまいりました。
また、当院は丸腰の病院ですので、急性期に関しての深い考察ですとか検査がやはりチャンスとしては少ないです。なので、ここに関しては急性期病院の力を借りて、IMSグループの総本山である板橋中央総合病院が歩いて15分のところにありますので、そこの総合診療科専門医の子たちも3か月常勤として当院で受け入れをして、一方で、うちのプログラムの子たちを3か月間板橋中央に派遣して、それぞれでどっぷりつかってきてもらうという、たすきがけのコースを用意してやっております。
当然その中に、やまと診療所、在宅経験のコースと地ケアを経験するコースというところで役割分担をしながら、定期的にそこの指導医たちとのカンファレンスを行いながら医師の育成を行っております。
最後に、コロナ禍での関わりについて御紹介させていただきます。
先ほど申し上げましたように、コロナ禍真っ最中につくって、最初から面会を止めるという選択肢もあったんですが、そもそも私たちは何をやりたいのかという中で、面会は決して止めないということを貫いてまいりました。また、家屋調査に関しても止めない。これによって、1人この間発症してしまいましたけれども、それでも止めないということを続けていますし、先ほどのようなコミュニティを生むためにも、患者同士の交流もできるだけ阻害しないということを貫いてまいりました。
急性期の真っただ中のコロナの患者さん、体制的にも受け入れることはできていない状況です。その分、急性期がもううちじゃなくていいといった患者さんに関しては、速やかに無条件に受け入れるということを続けてまいりました。これによって、結果として生まれたメリットとしては、急性期がうちの在宅の患者さんをスムーズに受けてもらえるようになる、そういったベッドが空く。うちの診療所じゃなくてもいいですけれども、という形で間接的にでも在宅を支えるということにつながったのかなと考えております。
当院の受け入れ実績になります。
第4波、第5波は少し受け入れたという程度だったんですが、やはり第6波、第7波、第8波というところで受入数がかなり増えました。赤星をつけたところが、その途中で院内でクラスターを起こしてしまったところではありますけれども、それでもこのアフターコロナの受け入れに関しては続けてまいりました。
一例、印象的なケースを紹介させていただければと思います。
93歳の男性で、認知症ベースの方で、御自宅で過ごされていた方ですが、第5波でコロナに罹患されて、近隣の急性期病院、板中ではないですけれども、そちらに入院されて、nasal high flowまで使われて加療されていた。経鼻胃管でミトンを装着して当院に転院してまいりました。
当院に転院してきたときに、うちのスタッフが非常に悩んでいました。ミトンを取るべきか取らざるべきか。患者さん御家族は、つけててくださいと言っているんですが、ちょっとでも食べ物を口にして家に帰りたいと言っているんだけれども、家に帰ってミトンつけるわけでもないから、つけてても意味がないんじゃないかというので悩んでいたので、本人に任せました。そうしたら、外すという判断をして、その結果、自己抜去したんですけれども、そうすると、家族もそりゃ嫌だよねということになりますし、じゃあちょっとでも食べてみましょうかっていうトライをしていくと、見る見るうちに回復されて、2週間で手引き歩行で病棟内を歩かれるまでになって。これを見ると、御家族は勝手に「おうちにかえります」と言ってくれるので、ここには何の退院調整も必要がないというので、チャレンジを後押しする。家族と本人が時間を共有することがいかに大事なのかを痛感した一例でした。
もちろん、こういったチャンピオンケースだけではありません。失敗したケースもあるんですが、こういったものがあるから、やはりチャレンジは続けていきたいと思わされた一例でした。今でも安定して、御自宅で穏やかに過ごされています。
コロナ禍から見えてきたもの。
先ほども少しお話ししましたけれども、急性期医療機関に在宅チームとして依頼せざるを得ないケースもあります。在宅で診切るシステムも板橋区と共同でつくり上げたんですけれども、それでもやはり力を借りるところは当然出てきます。その中で、回復された方を速やかに地域包括ケア病棟で受け入れをする、そして回復をしてもらってお家に帰すという役割を発揮することによって、結果として急性期のベッドの回転をスムーズにして、在宅チームとしても、在宅医療機関にとってもメリットがある。そういった形で橋をかける役割が地域包括ケア病棟にできるのではないかと考えました。回復期の受け入れで地域医療を支えるということを、コロナ禍を通じて勉強させていただきました。
我々が最終的に目指すものは、「最期まで 自宅で 地域で 「非」健康寿命を安心して生きてもらう」。そういう世界を目指してこれからもチャレンジを続けていきたいと考えております。
少し長くなってしまいましたが、御清聴ありがとうございました。(拍手)
加藤章信
先生、ありがとうございました。
自宅で自分らしく死ねる、そういう世の中をつくるという理念の中で、新たな発想といいますか、地ケア病棟をどういうふうに活かしていくかといった取組。施設全体の取組も含めて、考え方も含めて、詳細に御説明いただいたと思います。
ありがとうございました。
コロナ禍の振り返りと今後の取り組み~マルチモビディテイへの対応を含めて~
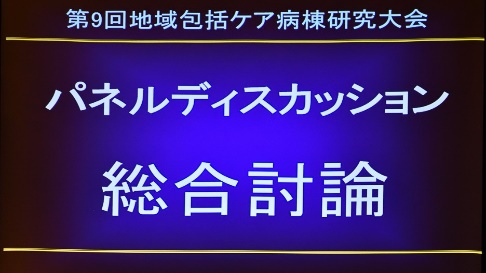

討論
それでは、若干時間を残していただきましたので、演者の先生方には壇上に御登壇いただきまして、1~2御意見をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
[演者 登壇]
加藤章信
初めに、コロナのことを少しお伺いしたいと思います。
国も今後、ポストコロナの時代にはなりましたけれども、新しい新興感染症ができた場合にどういうふうにしていくか。即時性を持った対応が各医療機関とかでできるようにしたいということで、御参加いただいておられます地域でも、行政との連携が始まっているかと思います。
今回、様々な形態で地ケア病棟を使ってコロナの方を診ておられたということもありますけれども、今後、新興感染症が出た場合に、地ケア病棟とか地ケア病床っていうのは活用していくべきものなのか。もしそういうふうにするならば何が必要なのか。あるいは、やっぱり新興感染症がはっきりしない場合には急性病棟で診て、その後で、受け入れが可能になった段階で地ケアを利用するほうがいいんだとか、様々な意見があるのかなと思って期待はしているんですが、石川先生から順番に。
新興感染症、次にどんなのが来るかも何もわからないわけですので。国はコロナみたいなものということで想定してやっているわけですけれども、自由な意見を言っていただければと思います。
石川賀代
難しいです。
やはり地域によってかなり差があると思っておりますが、これから高齢者の方たちが増える中で、私たちが全て急性期にそういった患者さんを入院させるのは、トリアージ機能をどこが果たすのか。ゲートキーパーというところも、新興感染症に関わらないことかもしれませんけれども、地域の中でのすみ分けをどうしていくのかを平時からきちんと考えて、連携を図ることが必要ではないかと考えております。
加藤章信
ありがとうございます。富家先生、いかがでしょう。
富家隆樹
新しい新興感染症についてはしばらく考えたくないなっていうのが正直なところですが。
スペイン風邪は1800年代ですかね、それも4年ぐらい続いたそうです。最近でいうと新型インフルエンザ、2009年ぐらいに私たち大変な思いをしましたが、そういうふうに考えていくと、あと10年ぐらいは新しい感染症ははやらないんじゃないかなって期待したい部分ではあるので、今のポストコロナ、アフターコロナのこのコロナ明けをもう少し満喫したいなと思っているところでございます。
ただ、病院づくりにおいては、先ほど石川先生からもありましたけれども、やっぱりそれに対応した病院をこれからつくっていくときには考えていかなきゃいけないのかな。例えばHEPAフィルターとかですね。昔は、結核病棟では陰圧室とかもつくっておりましたが、そういったことも改めて考えた病院づくりというのをしていかなければいけないかなというふうには思っております。
加藤章信
ありがとうございます。井川先生、お願いします。
井川誠一郎
これから来る新興感染症に対してどう対応するかということですけれども、地ケア病棟として考えるならば、例えば今回のコロナでいえば、デルタは駄目でしょう、だけれどもオミクロンなら対応できたでしょというのが結果だと思うんです。そういう意味でいいますと、新興感染症がどの程度のものなのかという把握ができるまでは、やっぱり地ケアが最初からファーストタッチで手をつけるというのはちょっとリスキーかなという気はしています。以上です。
加藤章信
ありがとうございます。
水野先生のところは、使い方というか考え方がちょっと違うとは思うんですけれども、御意見がありましたらいただきたいと思います
水野慎大
先ほど石川先生がおっしゃられていた平時からの急性期医療機関との意思疎通、情報共有というところに尽きるのかなと考えております。
そういう中で、状況が変わった、潮目が変わったとなれば、我々もチャレンジをするからバックアップをお願いしたいという形でお伝えしての役割分担ということができてくるのかなと思っております。
もう1点は、聖路加の先生とお話ししたときに感じたことですけれども、あちらは基本個室だから、クラスターはそこまで心配していないみたいなことをおっしゃっていたので、これから個室というものをどういうふうに位置づけて、病院運営、設計の基本としていくのかどうかというのも、いずれテーマになってくるのかなと考えております。
加藤章信
ありがとうございます。
地域の医療は地域で守るという地域包括ケアシステムをこれから推進していく上で、演者の先生方がお話しになられましたように、まず地域で連携してどういう役割分担をするのかということは、今回のコロナで、非常にいい感じなのかどうかわかりませんけれども、そういう連携は高まったと思います。
その中で、井川先生がお話しなされたとおりで、正体のわからないものを無制限に受け入れるから偉いという話ではないわけで、やはり最初はよく用心をして、そしてその中で、今の段階だったらば個室対応で対応できるよねということがわかってきた段階で、初めて地ケア病棟、病室っていうのが使えるのかなという意見だったと思います。これは今回のコロナで得た新しい知見だったと私も思っておりまして、先生方の御尽力のたまものと理解しております。
それから、「マルチモビディティへの対応を含めて」というサブタイトルをつけたんですけれども、どこの病院も全て、マルモの状態の方たちをお引き受けされているということが非常によくわかったと思います。
その中で、改めてマルチモビディティの人たちは一般病棟と比べてやっぱり地ケアなんだよねというところがもしあれば、地ケアでやっぱりよかったなというのがあれば教えていただきたいですし、もし可能であれば、補完代替リハを含めたリハビリの重要性というものも強調されていると思いますが、そういったことについて何か自由な意見といいますか。石川先生、すみません、順番にお願いします。
石川賀代
地ケアで直接入院で受け入れる患者像というのが、個々の病院によっての違いももちろんあると思うのですが、特に今から85歳以上の方をどう支えていくのかというのがかなり大きな課題かと思っております。誤嚥性肺炎や尿路感染症など、高齢者特有の病気に対してどこまで多職種協働で取り組むことができるのか。そういったことを実践する病棟としては、非常にすばらしい、懐が深い機能を持っていると思います。
これから、恐らく在宅への連携をどう図っていくのか。急性期でぶつっと治療が終了して、その後は知らないという、そこが連携ということになるかもしれませんが、超高齢者をどう支えていくのかということを地域でそれぞれ考えていく。その中で、やはり多職種が活躍できる、自分がここまでできたということをそれぞれが実感して、自らがチームで動いていくということが在宅までしっかり繰り広げられるというところに、チーム力と、あと、やはり垣根を越える。富家先生もおっしゃっていましたけれども、そこの垣根を越えないと働き方改革は決してうまくいかないですし、医療職は医療職でケアできる時間をどうつくっていくのかということを、高齢者だからこそ、支える時間というのが非常に多く必要になると思いますので、そういったことを考えなければならないと思っております。
加藤章信
先生のところは特にICTを駆使して、ない時間をどうやってつくるかというところを非常に大事にされていますし、チーム力ですね。そういうところの先生のお話として大変貴重だと思います。
富家先生、いかがでしょう。
富家隆樹
先ほどの水野先生のお話にもありましたように、地域包括ケア病棟っていうのは在宅を見据えていかなければいけないという大命題があるような気がしておりまして。例えばマルモでも、認知症があっても、御飯を食べて、そして歩いて在宅に帰ってもらう、帰りたいと思ってもらう。そんな病棟にしていくためには、今のこの地域包括ケア病棟のシステム、例えばリハビリが包括になっておりますけれども、逆を返せば、回復期リハビリよりも9単位以上のリハビリをしたって別に誰に怒られるわけではない。そうすればお家に帰れるチャンスが広がるのであれば、そういった選択肢も取ることができる。それだけ懐の深い病棟なので、これからもそれを見据えて、今のこの地域包括ケア病棟のすごく懐の深いシステムをこれからも使っていきたいなと思っております。
加藤章信
ありがとうございます。井川先生、お願いできますか。
井川誠一郎
マルチモビディティを考える上で、ドクターの姿勢っていうのが非常に重要であると思うんです。
午前中の講演で眞鍋課長がおっしゃったみたいに、ADLを下げるのは、2番目には急性期入院だっていう話で、急性期入院で入ったらなぜそれが下がるかというと、結局、専門医というある一種の特化したものに対して、ほかのものを診れないということから起こってくるわけで、それが実は回リハ病棟のリハビリ医っていう専門医にもある程度見てとれるという気が私最近しております。
そうすると、地ケアのような、それこそ総合診療医的な立場の人間がどんどんそういうふうなリハビリをしていって、同時に合わせて、先ほど富家先生がおっしゃったように9単位やると、さすがにリハビリ職どんだけ雇うねんっていう話になって、大赤字になるとは思うんですけれども、多少でも増やして差し上げて、しかもそれでマルチモビディティを診て治療していくのが、結果的には一番早くその人たちをほぼ在宅に持っていけるんじゃないかなという気はいたしております。以上です。
加藤章信
ありがとうございます。
水野先生は非常に新しい発想の、スタイルの違う利用の仕方といいますか、考えてなさっていますけれども、つけ加えてお話ししたいことがあればお願いしたいと思います。
水野慎大
マルチモビディティも悪いもんじゃないなっていうのをこの2年で感じていて。
あまりにも疾患が多くある、それが高齢者だし当たり前になるので、もはや疾患名で患者を語らなくなるというのがスタッフの中で出てきている。毎日、カンファレンスを全病棟でやっているんですけれども、疾患名から話し始めるスタッフはほぼいないんですね。何とかさんなんですけれども、相変わらず家族がけんかしててみたいな話が中心になってくるので、おのずと、いっぱいあるがゆえに、そっちよりも、本当にこれからどう生きるかに目が行きやすくなるのかなという点では悪くないのかなって。何も答えになっていないんですが、思っております。
加藤章信
ありがとうございます。
十分な時間ではありませんでしたけれども、先生方から今思っておられる、本当にキーになるお言葉を御意見としていただけたのかなと思います。
オピニオンリーダーとして今日登壇されていらっしゃる方、それぞれ、インパクトのある御発表をされています。
今回参加されておられます聴衆の皆さん方のバックグラウンドはそれぞれ違いますので、今日、それぞれの施設の中で、ここは自分に使えるぞといったところがあったんじゃないかなと思います。ぜひそういった形でそれぞれの御施設のレベルをさらに高めていっていただければと思います。
最後まで熱心に参加いただきました皆様に御礼を申し上げて、このセッションを閉じさせていただきます。
今日はありがとうございました。(拍手)
