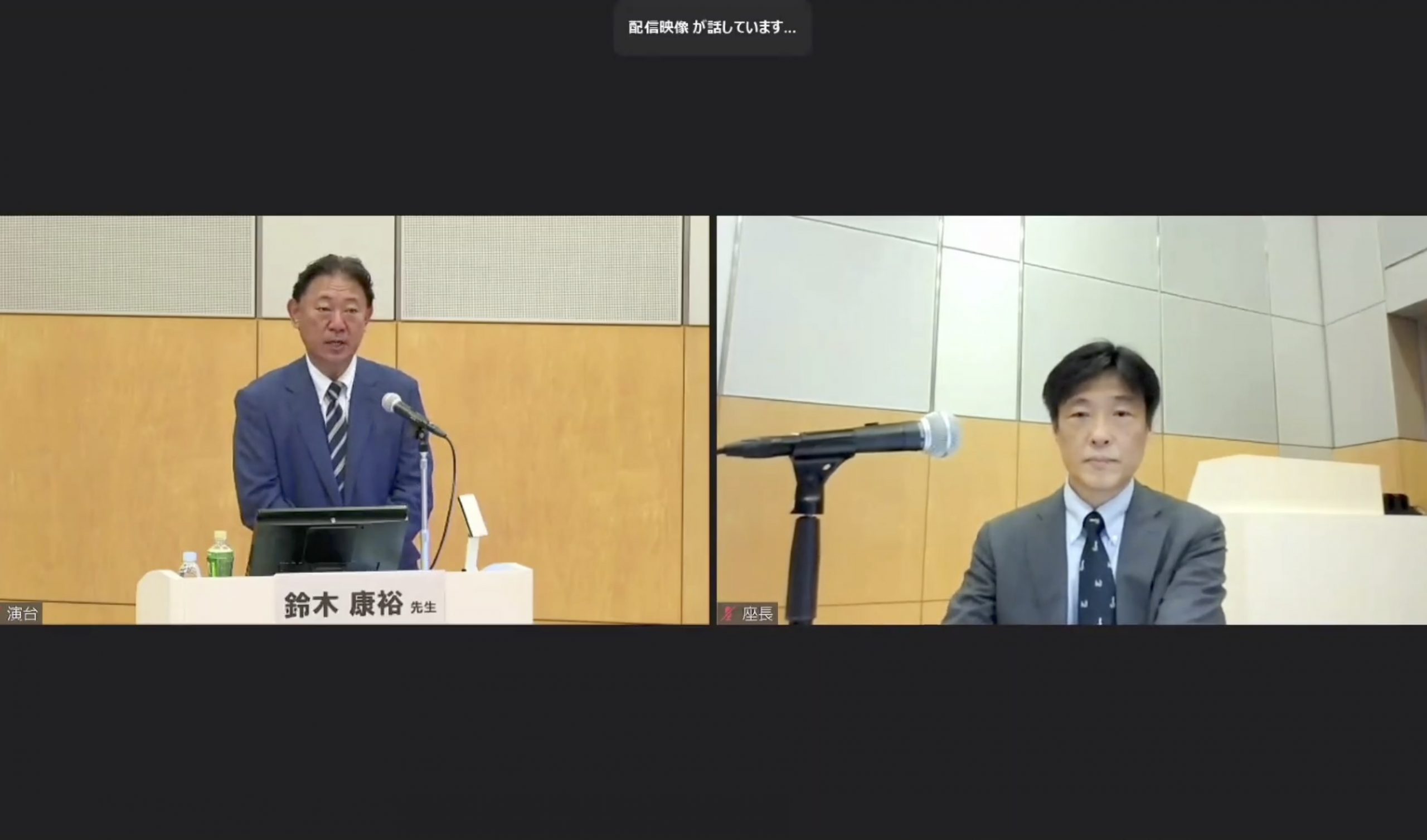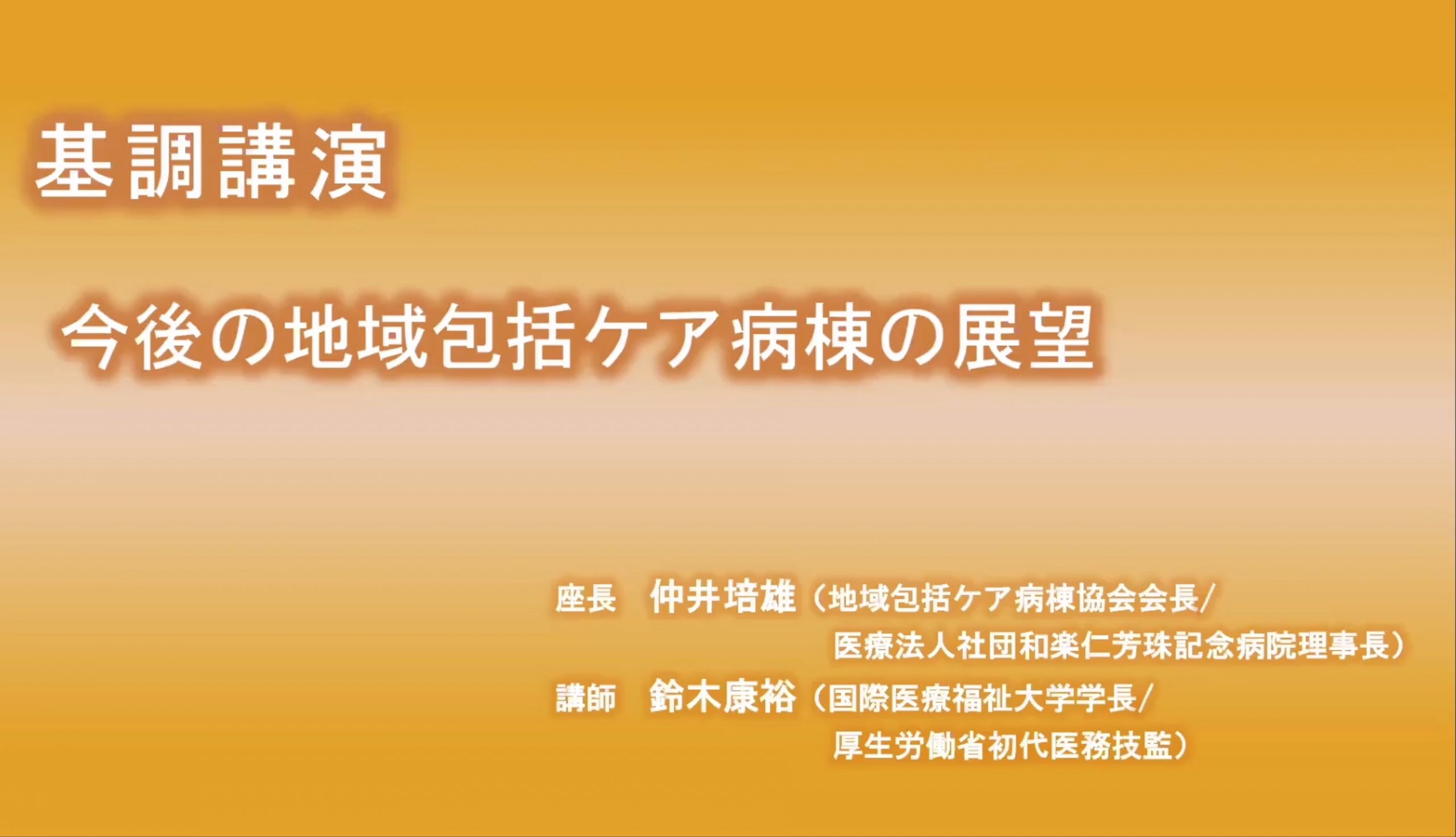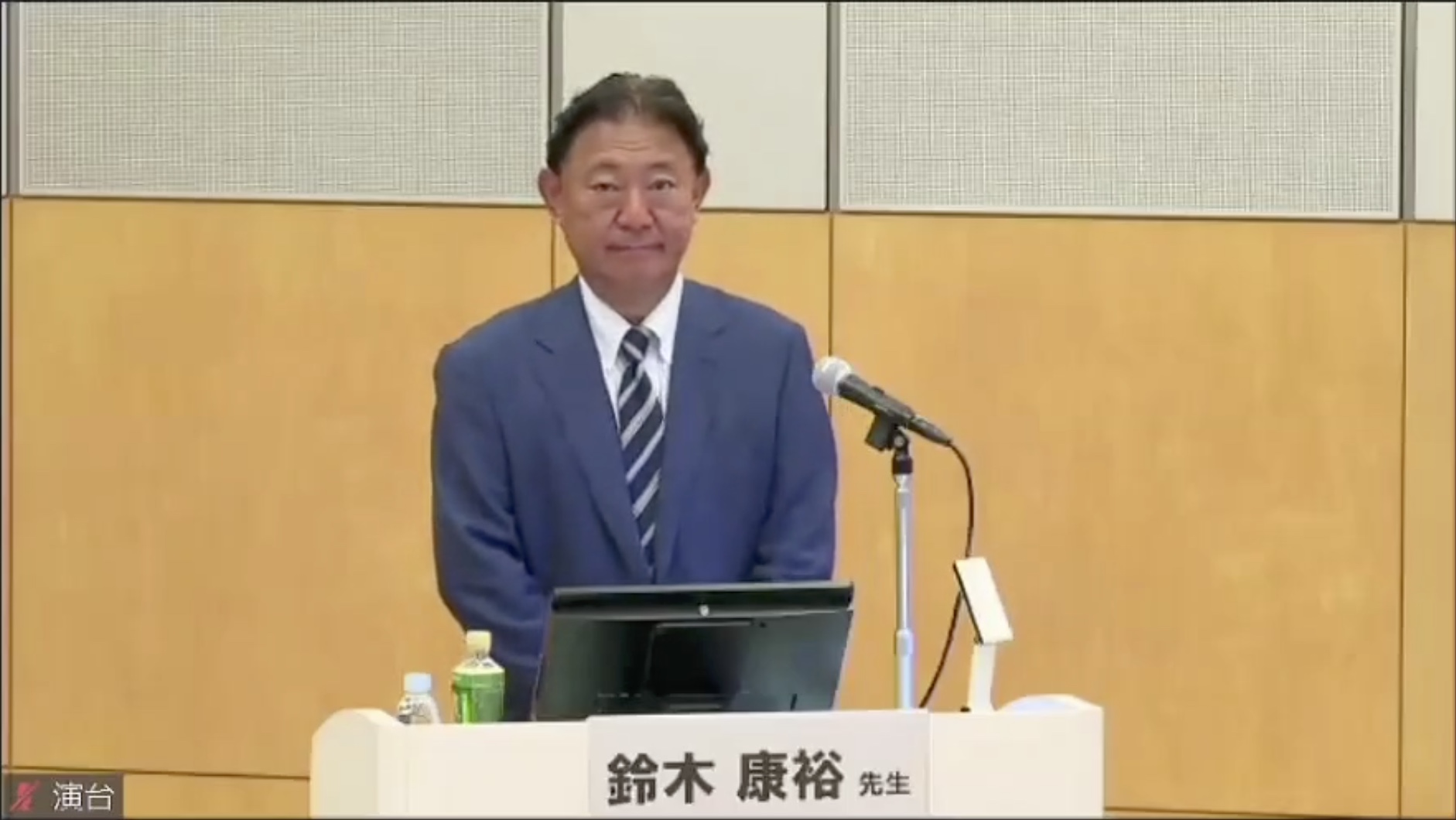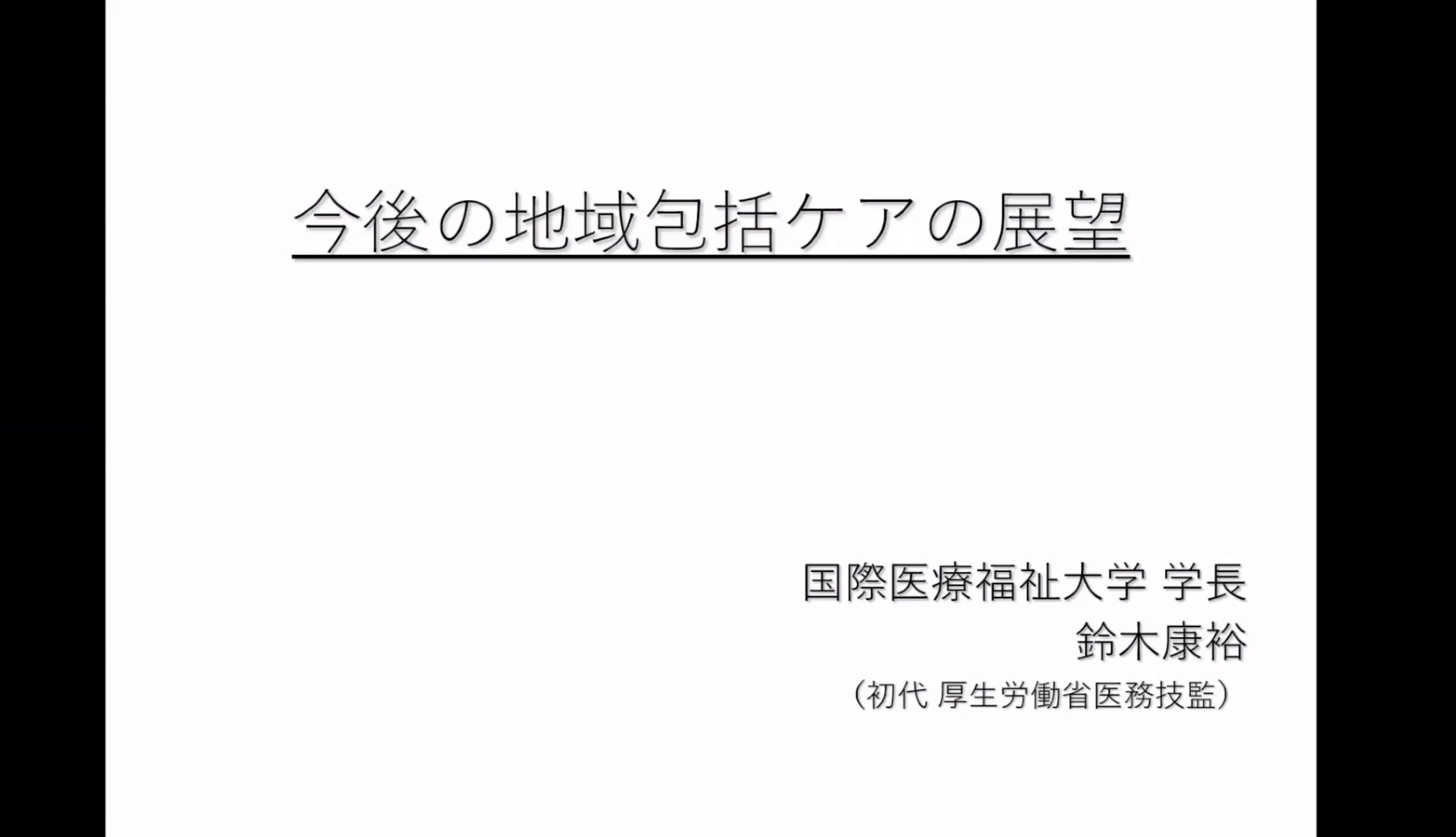- TOP
- 活動
- イベント(活動報告)
- 【基調講演】第8回研究大会
【基調講演】第8回研究大会
【基調講演】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「今後の地域包括ケア病棟の展望」
【座長】
仲井 培雄(地域包括ケア病棟協会 会長/医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 理事長)
【講師】
鈴木 康裕(国際医療福祉大学 学長/厚生労働省 初代医務技監)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
皆さん、こんにちは。先ほども御挨拶いたしましたけれども、第8回地域包括ケア病棟研究大会の基調講演を始めたいと思います。
講演に先立ちまして、まず、演者の先生ですが、鈴木康裕先生です。皆様よく御存じ、前医務技監をされておられまして、現在は国際医療福祉大学の学長をされています。
1984年に慶応大学医学部を卒業されまして、その後、様々な要職に就かれました。お時間がもったいないので、詳しくは抄録を御覧ください。
それでは、早速ですけれども、鈴木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
仲井先生、ありがとうございます。 ただいま御紹介いただきました、国際医療福祉大学の鈴木でございます。
この第8回の研究大会のお話を田中先生からいただいたのは、多分去年だったと思うんですけれども、私、2年前に厚生労働省を退任して、久しぶりに田中先生や仲井先生にお会いできるということで非常に懐かしいなと思って、喜んでお引き受けした次第ですが、今年4月の診療報酬改定を見て、これはまずいと。非常に厳しい改定だったので、先生方のお怒りの顔が頭に浮かびました。今日はたまたまリアルじゃなくてZoom会議なのでよかったなと。リアルだったら、卵をぶつけられていたんじゃないかと思います。
何を話そうかで非常に悩みましたけれども、医療課の担当者とも何回かヒアリングしましたし、中医協での議論とかいう話もしたいと思います。全身サンドバッグになるつもりでお話しさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
講演の中でも申し上げますけれども、一般病棟急性期から転棟したポストアキュートと、在宅から何かあったときに収容するサブアキュートと、在宅療養の復帰支援とか療養支援、この3つをきちっと三脚の脚のようにバランスよくやっていただきたいというのが恐らく厚生労働省医療課のメッセージだと思いますので、その道筋をきちっとフォローしていただければ、重要な地域の資源として厚生労働省に必ず支援してもらえると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
ちなみに、先ほどちょっとお話もありましたけれども、私、2年前に厚生労働省を退官しまして、昨年の3月から国際医療福祉大学の副学長、今年の4月から学長になりました。正直申し上げて、退任モードで少しのんびりできるかなと思っていたんですけれども、後でうちの大学の高橋泰先生も出られますが、理事長はなかなか人使いが荒い人で、朝から晩まで割と忙しく過ごさせていただいております。
それでは、講演させていただきます。
最初は、全体のバックグラウンドみたいな話を少ししようと思います。
これが日本全国の人口の推移です。2000年ぐらいの1億2,700万人ぐらいがピークで、今は下降フェーズにあります。
私が勘違いしていたのかもしれませんが、江戸時代が始まったときは1,000万人ちょっとしかいなくて、新田開発が起こって3,000万人ぐらいになりました。それ以降、明治になるまでずっと3,000万人ぐらいだったんです。太平洋戦争が終わったときも、一億火の玉とか言っていましたけれども、7,000万人ぐらいしかいなかった。その後、急速な高度経済成長に伴って5,000万人以上人口が増えたというのが日本の人口推移なので、今、確かに下降のフェーズにありますけれども、2050年でもまだ9,500万人はいるということからすると、後の話とも関係しますけれども、健康な高齢者の方が、働く気がある方が社会に貢献していただければ、それなりに回っていく社会じゃないのかと思います。
これは、私がよく使う、人口動態をもうちょっと近視眼的に見たものです。一番上が高齢者人口、真ん中が生産年齢人口、一番下が年少人口です。
今までを見ると、一番上の高齢者人口が1950年から2019年で実に9倍になっています。絶対数が増えていますから、私はこれを絶対的高齢化と呼んでいるんですけれども、この時期に我々がしなければいけなかったのは、サービスの絶対量を増やす。病院や施設を増やし、働く人を増やさなければいけなかったんです。
これからを見ていただくと、高齢者の絶対数は変わらない。ただし、若い働く人が40%減る。比率的に高齢者が増えていますから、私はこれを相対的高齢化と呼んでいるんですが、この時代に何が起きるかというと、1つは、税金や保険料を払う人が40%減るので、医療や福祉の財政はより厳しくなるという、ちょっと厳しい話です。それから、恐らく先生方にとってもっと厳しいのは、働く人が40%減っちゃうということです。多分お医者さんは大丈夫だと思いますけれども、看護師さん、介護職の人、その他の職種の人はかなり数が減る。そういう方たちをいかに確保するかということとともに、65歳定年をどう考えるかということもあります。センサー技術やAIやICTを使ってどううまく人力を代替するかということも同時に考えなきゃいけないと思います。
これは英語で恐縮ですけれども、1950年から2060年まで、100年ぐらいの高齢化のスピードで、左側の縦軸が高齢化率を見たものです。
日本はものすごい勢いで高齢化しているのがわかります。日本を20年ぐらいのスパンで追いかけているのが、韓国です。この韓国で私が最近心配していますのは、日本は合計特殊出生率という、女性が一生の間に産む子供さんの数が1.4ぐらいで、先進国では非常に少ないと言われていますけれども、この間、韓国を見たら0.9です。人の国の話なのであまり言えないですけれども、0.9のままでいったら、本当に国として成り立つのが難しくなってしまうかもしれません。
話を戻しますと、高齢者が人口の7%が高齢化社会、14%が高齢社会、28%が超高齢社会で、7・14・28になっています。7から14%の間のダブリングタイムにスウェーデン、フランスが何年ぐらいかかったかというと、ほぼ100年かかっています。ところが、日本は25年で達成しています。達成しているという言い方がいいのか、なっちゃったという言い方がいいのかわかりませんけれども。ということは、家族にも本人にも、年金や介護、医療の社会制度にも、スピードのプレッシャーがものすごくかかっているということです。
実はアジアの国というのは、韓国だけじゃなくて、中国も、一人っ子政策の影響とかがあって早く高齢化していますから、そういうところに、地域包括ケア病棟も含めて、介護保険も含めて、我々がどういう形で対応したのかを示していく責任があると思います。
変な世界地図ですけれども、これはMap Ballooningという名前らしいです。要は、各国に住んでいる高齢者の数でその国の面積を膨らませています。
これを見て明らかにわかるのは、世界の中で高齢化人口が集中しているのは5つの地域しかない。つまり、北米とヨーロッパとインドと中国と日本です。中国とインドは高齢者率がまだ高くないけれども、母数の人口が多いので、高齢者の絶対数は多い。ですから、この5つの地域がどう高齢者に対応していくかが世界にとって大きな問題になります。
特に右側のグラフを御覧いただきたいんですけれども、高齢者がどういう世帯で暮らしているかというグラフです。
昭和50年(1975年)、今から約47年前を見ていただくと、半分以上が三世代で同居しています。つまり、おじいちゃんおばあちゃんがいて、お父さんお母さんがいて、孫たちがいるという世帯です。昔のテレビドラマはみんなそんな感じだったと思います。今はどうかというと、6割ぐらいが1人で住んでいるか夫婦のみで住んでいます。夫婦のみということは、お互い年を取っているし、もしかしたら片方、もしくは両方が認知症ということです。これが何を意味するかというと、もはや家庭の中で具合が悪くなった人の面倒を見る人がいないということです。つまり、社会が面倒を見なければいけない。
これは私のグラフじゃなくて、亡くなった石川誠先生のグラフですけれども、病院と施設の収容人員数の合計の推移です。
何が言いたいかというと、家庭の世帯規模が小さくなる、家庭内で面倒を見られなくなる、女性はどんどん働くということになると、家庭の外で面倒を見なきゃいけない高齢者を病院・施設で収容しなければいけないということになる。
1995年ぐらいまではどうしていたかというと、一番下の薄い水色のところ、つまり病院の病床が拡大して、そういう人たちを収容していた。
後でもちょっと言いますけれども、日本の人口当たりの病院病床は明らかに多いです。それは、医療機関の経営者が儲けようとか自分を律するためにやっていたというよりは、病気がありますから地域で面倒を見られない高齢者を預かってくれと言われて、やむを得ず病床を拡大していったというのが本当だと思います。
2000年以降どうなったかというと、濃い緑が老健、薄い緑が特養ですけれども、介護保険ができたので、ここがぐっと膨らんできてそういう高齢者を吸収してきた。
しかしながら、2010年以降どうなってきたかというと、介護保険は非常に冷徹に、パイが大きくなると高齢者の保険料負担部分もどんどんどん大きくなっていくので、今、かなり多くの自治体が、介護保険料が1か月1人1万円以上。そうすると、夫婦だと2万円払わなければいけない。年間24万円。これもかなり大変だということで、住む部分、ホテルコスト部分が私費であるサ高住とか有料老人ホームのところが膨らんで、そこで吸収してきた。
つまり、我が国の過去50年ぐらいの、家の中で面倒見切れない人をどこで収容していたかというのを歴史的に考えると、まず病院、介護保険施設、最後は私費用の施設という3段階に分かれていることがわかります。
ただ、日本の高齢者を考えるときに、否定的なことばかりじゃないなと思うのは、これは平均寿命と健康寿命を男性と女性で各国で比較したものですけれども、平均寿命にしろ健康寿命にしろ、日本が最も長い部類に入っている。本当は、この平均寿命と健康寿命との差をもっと縮めて、なるべく長い間人の世話にならないで暮らせるのが一番いいとは思いますけれども、健康寿命が長いというのは医療の成果でもあるし、国民の健康への努力でもあると思います。
これはなかなか興味深いなと思ったんですけれども、文部科学省が高齢者に体力調査をしています。特に男性を見ていただきますと、薄い青が2016年、灰色が1998年ですから、18年差があります。横軸が年齢ですけれども、何が言いたいかというと、男性の2016年の70歳から74歳の人の体力ポイント38.9は、1998年の65歳から69歳の体力ポイント37.7よりも高いということです。つまり、18年たつと我々は生物学的には5歳若返っているということです。
これがこのまま続くかどうかはわからないけれども、少なくとも、荷重な肉体労働が減り、健康づくりが増え、様々な支援制度も増えたことによってこういう結果になっていることを喜ぶべきだと思います。
特に右側を見ていただきたいんですけれども、65歳から69歳で働く人の率。法定では65歳が定年ですので、通常は定年になってもおかしくないという人です。ところが、日本では、男性で半分以上、女性でも3分の1以上が働いている。もちろん、働かないと生きていけないという人も一部にはいると思いますけれども、インタビューとかアンケート等を見ると、むしろ働くことが生きがいだと。働きたい、なるべく子供の面倒にはなりたくないという人も結構多いです。
フランスなんかを見ると完全に引退モードで、男性でも8%、女性では5%以下しか働いていない。社会全体の高齢化との関係で考えると、このフランスモデルはなかなか厳しいと思います。
ここからは、厚生労働省の捕らぬタヌキの皮算用ですけれども、左が2017年、右側が2040年の推計です。
このままいくと、15歳から64歳の働ける人は7,600万人から6,000万人ぐらいに、1,600万人減ってしまうので、日本の活力、経済力というのはどんどん落ちてしまう。もしこの65歳から74歳の人が健康で働いてくれる、社会に貢献してくれるということになれば、ほぼ違わない人数が社会の中で働く、もしくは社会に貢献してくれることになるので、私たち保健・医療・福祉に関係している者の責務としては、こういう65歳から74歳の健康な人、働きたい人が社会に貢献できるような社会を一緒につくっていくことではないかと思います。
次に、お金の話をしたいと思います。
高齢者人口の伸び率で、青いのが65歳以上です。赤いのは75歳以上です。65歳以上は伸び率がずーっと減っていって、割と安定的ですけれども、75歳以上を見ると、2021年でがくっと減って、2022年でがくっと増えているのがわかります。
これはなぜか。2021年に75歳を迎える人は何年に生まれたかというと、1946年です。1946年に生まれた人というのは、多分1945年に受精しているので、恐らく終戦直前か直後なので非常に少ない。ところが、翌年になるとベビーブーマーで伸び率が8倍に増えるということです。これはこれで、そういうことなのかなということですけれども、実はこれ、医療財政的にものすごい意味がありまして。
というのも、現役並み所得者は除きますけれども、74歳までは医療費の自己負担が2割、75歳以上は自己負担が1割ということなので、75歳になる人が急に増えると、公費負担部分が急に増えるんです。
後でちょっと話しますけれども、今年の改定はちょっと厳しいなと思われたと思いますけれども、それは何もコロナというだけではなくて、人口学的な変化が、財務省に少し脇を締めないといかんと思わせていたということです。
もう1つコロナの話をさせていただくと、新型コロナウイルス対策での予備費が7兆円ぐらいありました。残額がまだ2兆数千億円残っていますけれども、今年の第7波の流行でこれを相当使うことになると思います。飲食店の支援等に2兆円、医療機関等々に1兆6,000億円、持続化給付金とかワクチンで使っています
この結果何が起こっているか。青が歳入、国に入ってくるお金で、赤が歳出、出ていくお金です。バブルの頃までは、赤字はあったけれどもそれなりにバランスしていたのが、その後どんどん大きくなって、安倍政権でその差は随分閉じ気味になってきたけれども、2020年に先ほどのワクチンとか持続化給付金とか医療機関とか飲食店に対するもので支出ががんと増えた。収入はもちろん増えませんから、棒グラフで示すところの赤字国債がものすごく増えた。したがって財務省としては、これを取り返すために、ここ数年は相当厳しいことをやっていかなきゃいけない。これは一般的で、医療だけじゃないですけれども。
国民負担率の国際比較です。国民所得に対する社会保障支出を示したものです。
これをどう見るかですけれども、全体の背丈の高さを見ると、日本は米国に次いで低い。
米国というのは、御存じのように基本的には年金も医療も民間保険でやってくれということなので、社会保障支出はあまり高くない。そのほか、イギリスやドイツやスウェーデンやフランスに比べても、日本の背丈は低い。しかも、後でちょっと出てきますけれども、日本の高齢化率は最も高いということを考えると、今の日本の社会保障支出は、財務省がおっしゃっているほど高いわけでないと思います。
ただし、課題は0の下の部分です。これは毎年の借金です。ドイツやスウェーデンは借金をせずに社会保障を回しているけれども、日本は毎年12.2%は借金をしているということです。はっきり言って、あと30年すれば我々は死んでいますからこの借金は多分払わなくていいと思うんですけれども、私たちの子供たちや孫たちはこの膨大に積み上がった借金を背負いながら各国と競争しなきゃいけないということなので、それはそれで、子孫にとっては不公平かなという気はします。
これも英語で恐縮ですけれども、年齢階層別に、下が払うお金です。緑が保険料、赤が自己負担で、青が給付として受け取るお金です。
子供の頃は、もちろん保険料を払っていません。ものすごく小さい子供さんは病気もするのでこうなって、年齢とともにずーっと持ち上がっているということです。何を言いたいかというと、積分すると、0から上の面積と下の面積を比べると、4割ぐらい赤字です。保険料と自己負担合わせても4割負担。
それをどうしているかというと、これも英語で恐縮ですけれども、基本的には国の補助金か地方自治体の公費で4割ぐらいを補填しているというのが今の財政構造です。財務省がなぜこれだけ医療費の増とか個々の診療報酬点数なんかにもうるさく言っているかというと、全体のパイが広がると、この4割の部分が自動的に増えていっちゃうんです。それは財務省の負担になります。
今日はこの話じゃないですけれども、財務省に首を突っ込ませないためには、国や自治体の公費の部分はあまり増やさないで、保険料とか自己負担を何らかの形で増やす。もしくはこれ以外の収入源を医療機関にして、パイの増えた部分は財務省にあまり迷惑をかけないというのも一つの戦略ではないかと思っております。
これは歳入、国に入ってくるお金の話です。赤が所得税、青が法人税、黒が消費税です。
御覧いただきますと、所得税はピークのときに26.7兆円ありました。ところが、最悪のときには12.9兆円で、半分以下です。法人税は、ピークのときには19兆ありましたけれども、リーマンショック後、最低のときには6.4兆円、3分の1になりました。
私はいつも皆さん方にお聞きするんですけれども、今年は景気がちょっと悪いから医療とか福祉は2分の1か3分の1でやってくれと言ってできるかといったら、絶対できないと思います。5割から6割が人件費率の世界だからです。
ところが、消費税を御覧いただくと、3%のとき、5%のとき、8%のとき、10%のとき、はかったかのように収入は上がっています。もちろん、逆進性とか議論はいろいろありますけれども、もはや全ての税収の中で最も多いのが消費税になっているので、私はやっぱり、医療とか福祉、介護は消費税に依拠するしかないと思っています。
これは、2000年を100とした場合に、2000年から2017年に各支出項目がどう変化してきたかを見たものです。
例えば公共事業、橋を造ったり道路を造ったりするものは、一時は5割を切り込みましたけれども、今でも平成12年レベルの3分の2になっています。教育の2割減は、子供の数が減ってきたというのも多分あると思います。防衛費は安倍政権時代に少し増やしたので4%増ぐらいになっていますけれども、それとものすごい対比を示しているのが社会保障関係経費です。全体でも94%増。
ですが、私が言いたいのはもう1つあって。
緑色の三角が年金です。丸いのが医療です。医療は、医療費亡国論みたいなものがあって、医療費が増えることが国の財政を厳しくしている、とんでもない費用だという議論も一部ありましたけれども、見ていただくと、マクロスライドを導入しています。マクロスライドというのは、物価、賃金の上がり以上に増えないということですけれども、医療費は、それを導入した年金とほぼ同じ、増額していないということです。つまり、改定ごとに厚生労働省と財務省がかんかんがくがくの議論をして、官邸を巻き込んで改定率を決めて、先生方にも御努力いただいてやっている結果、何とか年金と同じぐらいの伸びに収まっているということだと思います。
介護はちょっと違います。介護は、高齢者の数ががーんと増えたのでちょっとコントロールできずに、240%になっています。
国民負担率がOECDの中でどうかというのを高齢化との関係で見てみると、高齢化率をX軸に取って、縦軸に国民負担率を取ると、お年寄りが増えれば国民負担が増えるので、右型上がりの線上にほとんどの国は来るんですけれども、日本を見ていただくとここにあります。国民負担率という点で見ると、非常に高齢化しているにもかかわらず、OECD42か国の中で下から3分の1ぐらいじゃないですかね。つまり、日本の社会保障というのは財政論者から目の敵にされていますけれども、高齢化率との関係でコストパフォーマンスは結構いいんじゃないかと私は思います。
医療費ですけれども、2020年の医療費は、先生方御存じのとおり、4から12月の実績で1.3兆円減っています。8か月ベースで1.3兆円減っているということは、年間ベースでは1兆7,000億円か1兆8,000億円減っているということです。これは、多くは受診減です。当然病院も、コロナ病棟に変えて補助金は入るけれども、医療費としては入らないという場合がありました。
これを言うと財務省の人は怒るかもしれませんが、私はオオカミが来たグラフと呼んでいます。上が医療費、下が介護費用です。緑とか青とか黄色は、このぐらい増えていっちゃうぞという事前の推計です。実際は赤です。つまり、何が言いたいかというと、どの推計を見ても過大推計になっているということです。こんなに増えるぞ増えるぞというのが、警告の意味はあったとは思いますけれども、実際にはそれより相当切り込んで抑えている。
細かい表で恐縮ですけれども、所得再分配というのがあります。豊かな方から豊かではない方に所得を移して、社会の格差をなるべくなくしていこうというものです。これは税金によってできる場合と社会保障によってできる場合がありますけれども、どの年を見ても、社会保障によってなされる部分のほうが税金によってなされる部分よりも5~6倍大きいということです。つまり、社会保障が高い高いと言って、そこをぶった切っていけば、社会の格差は拡大してしまうと思います。
次に、医療の中身の話をしたいと思います。
これは年次はちょっと古いですけれども、今でも同じような傾向です。厚生労働省が患者調査というのをしていまして、どういう病気で皆さんが医療機関を受診しているかを分析すると、何と患者さんの半分ぐらいが3つの病気で医療機関を受診しています。
高血圧、糖尿病、高脂血症の3つの病気は、恐らく2つの共通点があって、1つは、放っておくと大変なことになる。脳卒中になったり心筋梗塞になったり、透析が必要になったりします。もう1つの特徴は、最初は恐らく自覚症状もあまりない、数値の異常だということです。
問題は、この数値の異常の段階、もしくはその前で遺伝子の異常もあるかもしれませんが、そういうものの段階でいかに早く見つけて対応して、それ以上進ませないかというところをしっかりやれば、日本の医療需要は割とコントロールできると思います。
これは病院病床ですけれども、左側が施設数、右側が病床数です。
例えばドイツの病床数では、85%が公的病院です。日本では、病床数でいうと30%、施設数でいうと20%しか公的病院がない。多くは有床診療所が拡大して病院になっていったという日本の歴史的推移からそういうことになると思いますけれども、これはいろんな面があると思います。民間が多いということは、診療報酬をはじめとする様々なシグナルに非常に鋭敏、すぐ反応していただけるという点がありますけれども、大臣や知事の命令下すぐ動くかというと、オーナーはやっぱり民間人ですから、なかなかそういうわけにはいかないという面があると思います。
これが外来です。年間の外来受診回数は、日本は13回、OECD平均の倍ですけれども、1回当たりの費用はOECD平均の半分ぐらいです。外来の頻度と1回当たりのコストを掛けた外来総費用はほぼ変わらないけれども、日本は、ある意味でいうと、お医者さんにとって大変だと思います。午前中に50人とか80人診なきゃいけない外来になっているということです。
医療機器。左側がMRI、右側がCTですけれども、人口当たりの台数を見ると、両方ともOECD平均の3倍から4倍あると思います。
ある意味でいうと、各病院の競争に任せておくとこういうことになります。必ずしも悪いわけじゃないと思いますけれども、ただ、台数がOECD平均ぐらいしかないということが、撮影頻度が少ないがゆえに医療上のマイナスが生じているかというと、必ずしもそうではないと思いますし、台数が多いと、元を取るためにどうしても枚数をたくさん撮る、撮りやすいということになってしまうと思います。
この2つは、これだけ普及しているから変えられないと思いますけれども、今後、重粒子線とか陽子線とかPET/CTとか、ダビンチとかいうものがますます小さくなって使いやすくなって、病院にも入るようになったときに各病院が争って入れられるかというと、もはや多分日本の財政はそこまで余裕がないので、どう病院間で連携をして、例えば地域医療連携推進法人を活用すれば良いと思います。
人口1,000人当たりの臨床のお医者さん。私みたいに医者だけれども臨床をやっていない人を除いて、臨床だけをやっている人を取っています。日本は一番少ないけれども、他の国の3分の1、4分の1ということはない。
ただし、人口1,000人当たりのベッド数を見ると、日本は圧倒的に多い。さっきの具合が悪くなった高齢者をどんどん吸収せざるを得なかったので、例えばアメリカ、イギリスに比べると5倍ぐらいあるわけです。単純な算数ですけれども、医師数があまり変わらずにベッド数が5倍あるということは、100床当たりのお医者さんの数は、日本はアメリカ、イギリスの5分の1ぐらいということです。
単純な比較はできないけれども、日本のお医者さんはある意味で言うと5倍ぐらい忙しいということです。さらにこの上に、アメリカは様々な職種が日本以上にいますから、医者は本当に医者じゃなきゃできないことに特化できると思います。
ちょっとまとめますと、生産年齢が減ってきて、働き手も減るし保険料等の払い手も減る。75歳以上が急激に変化するので、財政上に厳しいポイントがある。住まい方も変わっていく。財政赤字は続くけれども、かつ医療費は伸びるけれども、政府財政を爆発的に破壊させるほどではないし、所得再分配の役割はよく果たしている。ただし、今現在病床が多くなってしまっているということが医療従事者の過重労働を生んでいて、2024年の医師の働き方等々にも結びついていると思います。
今後、医療財政がこのままうまくいければいいと思いますが、もしかすると、入ってくるお金が少なくて出ていくお金は変わらないということで、より重点化しないといけない場合が出てくると思います。そういうときに私たち日本人はどっちの医療を選ぶのか。ここに書いてある、Catastrophic保険という、ある意味でいうと、1人では払い切れないような事態、例えばオプジーボが必要だとかいうときにこそ医療保険を使うということになるのか、それとも、そういうのは民間保険でやってくれと。むしろ腹痛とか風邪とか水虫とかいう、毎日使う医療こそ保険を使わせてくれという混合診療にいくのかという議論になると思います。
それからもう1つ、今日の本題とは関係ないですけれども、可変給付率というのも、財務省が言っているからというわけじゃないですけれども、将来は可能性があるかなと思っています。医師には処方権がありますのでどんな薬でも処方できる。ビタミン剤でも処方できるわけですけれども、フランスの場合、ビタミン剤を処方した場合には自己負担は100%、保険給付はなし。ところが、抗がん剤を処方した場合には自己負担はなし、給付が100%。その間が幾つかのグレードに分かれているということです。どこに入るかは、製薬会社ですごく争いになると思いますけれども、ここでめり張りをつけるということもあるんじゃないかと思います。
日本の医療が悪いかというと、私は全然悪いとは思っていなくて。これは、大腸がん手術後、5年後の生存率ですけれども、どのステージを見ても、青の日本は、赤のアメリカよりも優れている。しかも、費用は恐らく3分の1から5分の1ぐらいということです。
今年の改定です。
これは厚生労働省の資料です。0.43%プラスだということですけれども、私はここをよく考えなきゃいけないと思っていて。実は、薬価1.35と材料価格0.02、医薬品と材料でへこんでいるわけです。もちろん、これが全部医療機関側にかぶるわけじゃありません。今は調剤薬局でかなり薬を出していますから、薬の費用の減というのは、医療機関でかぶるのは大体4割ぐらいということを考えると、1.35足す0.02の1.37の4割ぐらいなので、実質0.55あれば、医療機関としてはプラスマイナスゼロということです。
実は、ここにイアマークと真空斬りという要件があります。どういうことかというと、看護の処遇改善で0.2、不妊治療で0.2と、使途を限定した、イアマークというんですけれども、この2つの0.2をやっているということは、残りは0.03しかないということです。いやいや、実はリフィル処方箋を導入したし、小児の感染予防加算をやめたから、0.1と0.1が戻ってくるぞということですけれども、これは本当かなということで、改定内容としては実質かなり厳しいと思います。
岸田総理による「新しい資本主義」だと、看護等の賃上げは、女性が多いということ、労働集約的なので、人に投下するということは将来必ず増えていくし、産業のない地域も支援できるという様々な意味で、これは意図的にやっています。公共価格を上げるということで、医療とか介護、福祉の費用を上げているということだと思います。
医療提供体制の課題。
コロナで2年半ぐらい厚生労働省の様々な見直しも止まっていましたから、地域医療構想とか医師の働き方改革を以前に決めた工程表のままでやるのは難しいなと思っています。
例えば、地域医療構想だと、今回、ヨーロッパを見たときに、イタリア、スペインの死亡率の出方とドイツの死亡率の出方がえらい違いますね。EUの国というのは、国境阻止はできない。EU圏だと自動車で自由に移動できちゃうし、国境で検問もありませんので。ということになると、感染症対策はどこが違ったかというと、私は病床数だと思います。イタリア、スペインは、アメリカ、イギリスほどに低くしたけれども、ドイツは日本とアメリカのちょうど中間ぐらい。しかも、ICU病床が割と多かったということから見ると、日本はどこをターゲットに病床を集約化していったらいいのか。そのレベル感といい、種類といい、ある程度見えてきたのではないかなと思います。
医師の働き方も、もちろん大義は、お医者さんが過労で医療過誤を起こすようではいかんというのはそのとおりだと思いますけれども、先生方もおわかりのように、在院時間と実質労働時間というのは必ずしもイコールじゃないけれども、今は在院時間しか測るものがないです。そうすると、病院の中にいて、例えば専門医を取る研修をしているとか学会の発表の準備をしているというのも、実は労働時間に入っちゃっています。そこをどうやって除くのかということになります。それから、寝当直として宿日直が認められるのか、それとも全部勤務時間になるのかで医療機関の負担は全然違います。そこも先生方の声を聞くと、労働基準局によって判断が違うみたいなことがありますから、気をつけないといけないです。
場合によっては、地方の病院はお医者さんが少ないだけにより過重な勤務を先生方にお願いしなきゃいけなくて、それがまたお医者さんを遠ざけることになってしまって、どんどん医療過疎が悪化してしまうんではないかという懸念もちょっと持っています。
最後、財務省の人は、NHSのようなゲートキーパーをかかりつけ医に法的に義務づけて、人頭制でやらせたいということを思っているんですけれども、私は、これを今の日本でこれからやるのはどうかなと思っています。50年前の医療だったら、聴診器一本持って、打診、聴診やりながらある程度当たりをつけてというのはできたかもしれないけれども、今の医療でそれで患者さんに信頼されるかというと、なかなか難しいんじゃないか。しかも、今の自由に行ける段階から変更するということになると、むしろ私は、先生方のような病院、急性期を持つけれども、地域包括もあって、慢性期もあるという病院では、CTもあるし、フロントラインホスピタルになって一定に診断までつける。もちろんがんの遺伝子診断なんかは大規模病院へ行けばいいと思いますけれども、そこで診断をつけてある程度診療方針を決めた上で、地域に返してかかりつけ医にやってもらって、何かあったらまた入院してもらうという。まさに地域包括ケア病棟のようなものが外来と地域のやり取りの中心になるのが本来の姿ではないかなと思います。
人生100年時代の国民皆保険(維持)について。
幾つか書いてありますけれども、1つは、さっき申し上げた生産年齢人口の減は、実は40%と言われています。実はもう1個、40%減というのがあって、これは何かというと、AIを入れると40%失業すると言われています。
この2つ、全く同じ40%で、これも全く捕らぬタヌキですけれども、生産年齢が少なくなった分をAIで代替すれば、ほぼ無傷でいられる可能性はあるということだと思います。医療でも、カプセル内視鏡にしろ、病理診断、放射線診断にしろ、AIが代替できるところは相当程度見えてきたので、これもやっぱりやるべきだと思います。
それから、民間保険との段階的導入、併用というんですかね。今、先進医療でがん等できますけれども、私はそこをもうちょっと広げて。美容整形を医療保険に一部入れるというのはないと思うんですけれども、先進医療でまだこなれていないなというものについては指定をして、それは民間保険で給付しておいて、一定程度こなれてくれば保険に入れるという段階的なやり方もあるんじゃないか。
あと、地域や診療科をいつまで自由に選べるのかというのは、例えば、1人当たり公費の導入が非常に大きい国立大学出身の人が初期研修が終わった後すぐ美容整形に行ってしまうというのを、自治医大とか特殊医な大学を除けば許容しているわけですけれども、それが本当に正しい姿なのかというのはやっぱり考えるべきかなと思います。
これは、後で太田先生が多分言われると思うので、簡単に触れますけれども、私、この2年半ぐらいですかね見ていて、例えばコロナで感染を恐れて受診減がある。それから、補助金はありますけれども、空床確保のために医療費としてはどうしても減ってしまう。それから、院内感染が起これば、当然従事者も減ってしまうし、診療を縮小せざるを得ないし、様々な工事で減ってしまう場合がある。ただ、ある程度うまくやっているところとそうでないところというのはかなりあるような気がします。院内動線とか、駐車場を利用してそこに発熱外来をつくって、場合によっては移動式のCTも設置してとか。今はあまりないと思いますけれども、当初は、看護師さんのお子さんが保育園で登園を拒否されるみたいなこともありましたので、そういう心理的なサポートも必要だと思います。
これは一般的な話で、先生方直接という意味ではないですけれども、なぜ日本でこんなに病床が多いのに医療崩壊が起きやすいのかみたいなことを言われていました。これは病床数の絶対数が少ないことが問題じゃなくて、さっきも言いましたが、病床当たりの従事者が少ないので、非常に負担の大きいコロナみたいな患者さんが来ると、ある意味で相当プレッシャーがかかってしまうということです。
この間日経新聞に載っていましたけれども、200数十万人の看護師さんのうち、70万人が働いていない。我々医師は、三師調査といって、3年ごとに必ず、どこにいるのか、何をやっているのかという調査がありますけれども、看護師さんは、働いている人は一応届けることになっていますが、働いていない人は全く義務がないので、70万人の人がどこにいるのか、働く気があるのかないのか、全くわからない。本来であれば、今回、例えばコロナのワクチン接種とか、忙しい保健所の支援とかいうのをやってもらえたはずですけれども、そこがやっぱりできないということだと思います。
当然ですけれども、病院病床は、例えば今回の第7波が起きたからといって、早急にコロナ病床が広がるわけではないので、どうしても在宅で診なきゃいけない。在宅でパルスオキシメーターや様々なものを使って、アプリを使ってやるという機能がやっぱり弱かった。
2020年の最初の頃は、マスク、手袋をはじめとして、先生方に大変御迷惑をかけたと思うんですけれども、海外からの輸入に頼っていると、海外が輸出禁止にしてしまうと、日本での需要は高まっているのにほとんど供給できないという状況になってしまうので、国内生産、備蓄を経産省と一緒に厚労省はやっています。
ここから、地域包括ケア病棟の話をしたいと思います。
これが有名な自助・互助、公助・共助の話で、下の土のような部分と上の葉っぱのような部分がある。ちょっと違った見方をすると、本人、家族のやる自助と、隣近所やボランティアがやる互助と、専門家、保険でやる共助と、生活保護等の公助というのが社会保障の類型ということになっています。
平成25年の介護保険法改正で、地域包括ケアシステムは私たちも関与してやったわけですけれども、その翌年、宇都宮さんが医療課長だったときに診療報酬改定で地域包括ケア病棟が導入されたと私は理解しています。
急性期の一般病棟からは退棟できるけれども、なかなかすぐに家には帰れない。家にいるけれども、悪化しちゃって。でも急性期病棟へ行くほどではない。どうやって在宅に返すか等、私はこれを新三本の矢と呼んでいます。三位一体と言ってもいいかもしれませんが、この3つを全てこなせるところは今までなかなかなかったと思います。それまで、急性期と慢性期をつなぐ、病院施設や家庭をつなぐというのをやっている病院は幾つかありましたけれども、そこを概念として診療報酬の体系でしたというのは、宇都宮さんの手腕なのか、そのとき筆頭技官だった一戸さんの手腕なのかわかりませんけれども、なかなかの英断だと思いました。
もう1つ課題があったのは、急性期病棟の回転率を上げる、在院期間を短くするためには、どうしても残ってしまう人を院内で地域包括ケア病棟に転棟させるということもありましたし、在宅療養を急性期病棟そのままでは支えにくいので、地域包括ケア病棟をつくるということもありました。当然ですけれども、リハビリテーション以外にも私が大事だなと思うのはソーシャルワークで、特に退院をどう支援するかということと、地域のかかりつけ医の先生方とも連携をとらなきゃいけないし、できれば訪問看護ステーションなんかを持ちながら退院後もサービスを継続できるというところも必要だと思います。
歯科健診というのもやるようになるそうですけれども、口腔機能の維持、栄養管理、フレイル対策。何よりも、1人で住んでいる人が多いので、心理的もしくは精神的な対応というのも必要だと思います。
これは医療課から借りてきた入院料別の届出病床数の推移の表で、医療課にも幾つか話を聞きましたけれども、左側が地域包括ケア病棟で、右側が同じ時期の回復期リハビリテーション病棟です。始まった時期が違うので、必ずしも2つ同等な比較はできませんけれども、地域包括ケア病棟については伸び率が非常に大きい。12倍近くになっています。
どういう傷病で入っているのが多いかを見ると、急性期は、もちろんがんが多いけれども、地域包括ケア病棟は、骨折や外傷。大腿骨頭等かもしれませんけれども、が多いということになっております。療養になると、心臓とか脳梗塞の後遺症が多いということです。
救急は、今回の診療報酬改定で条件の変更がいろいろあったわけですけれども、これは令和2年の調査です。これは令和3年の調査です。やっているやっていないを見ると、2年と3年で違いはあまりないように見えます。
実際にこの青いところと赤いところを見ると、これは地域包括ケア病棟の入院料とか管理料の様々な分類で、ものによって違いますけれども、全部を平均してみると、2~3割が救急告示を行っていないというのが医療課の分析でありました。
それから、地域包括ケア病棟を有する一般病床と療養病床で救急の実施のありなしを見てみると、当然ですけれども、一般病床は救急の実施があるが9割ぐらいですけれども、療養病床の場合には4分の1しかやっていないということです。
自院の一般病棟からの転棟の確率を見た場合に、いろいろありますけれども、恐らく一番多いと見るのは、入院料2です。90%以上がかなり多いということだと思います。逆に、自宅から入棟した患者が多いのはどこかというと、恐らく入院料1、管理料1のところの患者割合が高いということになります。
自院の一般病棟から転棟した割合が90%を超える場合に、どういう病床規模感の病院が多いのかを見ると、オレンジ色の大病院というところはむしろ少なくて、400床未満の医療機関が多いということが分析されていました。
これは医療課がよく言われているんですけれども、自院の一般病棟からの入院が8割以上の病院を抽出して、自宅から入棟している人が8割以上の病院、かなり両極端ということですよね。この2つを抽出して分析したとき、患者の状態がどうかということを見ると、自宅から8割以上の場合と自院の一般病棟からの8割以上を見た場合に、やっぱり自宅から来る人のほうが不安定なことが多い。自院からは、安定して急性期病棟から転棟するということもあるのかもしれません。
医師の診察頻度が本当に医療必要度に関連するのかという長い議論はあると思いますけれども、同じように、自宅からが多い場合と自院の一般病棟からが多い場合で、1日数回の場合はどっちが多いかというと、やっぱり自宅からのほうが多いし、週1回でいいというのは、自院の一般病棟から来たほうが多いということになります。
これは先生方御存じのとおり今回の改定のイメージで、ポストアキュート、サブアキュート、在宅復帰支援というところをバランスよく、三脚の脚のように。どこかがものすごく長いとうまく平衡を保てないということだと思います。
これは先生方既に御存じの、全体の基準です。
先生方が既に御存じのことをあえて繰り返させていただくと、要件項目の追加では、一般病床で二次救を条件化しましたし、許可病床100床以上については、入退院支援加算1の届出を要件化したし、入院料2・4では、在宅の実績等を要件化した。
実績水準の切上げでは、自宅から入院した患者の割合が15%から20%、救急患者の受入れでは、3か月で6人から9人以上、在宅復帰率では、入院料1・2を7割から72.5%。減算規定では、一般病棟から転棟した患者を6割未満とする規定では、400床以上のところを200床以上にしたし、満たせない場合の減算割合を90から85に切り下げた。
地域ケア病棟入院料2・4では、在宅医療の実績等を要件化したけれども、満たせない場合にやっぱり10%減算。
療養病床で地域ケア病棟を届けている場合には、95にした上で、100分の100となることができる実績を設定した。
先生方の見方と全然違うかもしれませんが、私は、やっぱり創設時から見た場合に3つの脚が、それぞれある程度バランスよく取れていることが必要だというメッセージだったんじゃないのかなと。偏っていると相当厳しい減算ということになります。ただし、単に自院の中の急性期の在院期間を維持するために自院だけから転棟するのを主にするというのはやはりなかなか難しくて、地域とのやり取りの中でどううまく機能していくかというのが大きな命題なのかなという感じがしました。
いろんな先生方から医療課に寄せられている様々な声を総合はできていないと思いますけれども、幾つかピックアップすると、ポストアキュート受入れに偏ると相当厳しい。在宅復帰機能とか在宅からの急変時受入れを相当やらなきゃ駄目だなということだし、これは掛け算でいきますので、全てを満たせない場合、減算が4割を超えることで、地域包括ケア病棟はなかなか難しいんじゃないですかと言われているに等しいという声もありました。ただし、減算条件を全部クリアして、新設分も含めて加算を取ればプラスになる場合もあるという声もあります。
これは厚生労働省批判の声です。2014年の改定では、こういう言葉がいいかどうかわかりませんが、相当甘い点数がつけられた。予想以上に増えたために、厚生労働省が例の手で「ハシゴ外し」をしたんじゃないかと。これは常套手段だろうというような声で、「手続き民主主義」と二木先生はおっしゃっていますけれども、こういう仁義にもとることをすると、後で大きく信頼関係を損なうよということだと思います。
これは、私実際に、今回の例ではないですけれども経験していて。
介護療養病床、これは介護保険ができた2000年にできまして、私は2009年の老人保健課長の介護報酬改定をしたんですけれども、私の前の改定、2006年の改定のときに、相当介護療養病床に、最初ははっきり言うとここに来てくださいという体制だったのを、いきなり介護療養病床を廃止するということをやった。これは、その後にいろんな対策をしたし、最後は介護医療院みたいな制度もつくりましたけれども、15年以上にわたってこじれて、御理解もなかなか得られなかったという反省点です。
やっぱりそこまでやっちゃ駄目で。もちろんある程度はありますよ。最初は少し甘目にしておいて、なんちゃってみたいなところはやっぱり駄目だよねというのはあると思うんですけれども、そこにも一定の限度というものがあるだろうということじゃないですかね。今回のもそうだとは言っていません。
医療課に聞きますと、中医協における議論は、3つの役割をどういうふうにうまく果たしていたかというところに集中していましたと。救急を実施していない医療機関が一定程度ありましたと。それから、入退院の支援加算1を届け出る機関が4割ぐらいだったと。それから、医療的な状態や医師の診察の頻度が種類によっては結構ばらばらでしたと。特に支払い側は、偏っている医療機関があれば、めり張りをつけるのは当然だろうという議論もありましたし、患者の状態や医療資源投入量の差があることを踏まえた評価をすべきだと。
診療側は、必ずしも均等に果たせればいいというものじゃないだろうと。これは本当だと思うんですけれども、地域によっては、自院の近くに違う施設があれば、そことのやり取りの関係で、必ずしも全国どこでも全く正三角形じゃなきゃいかんということではないだろうと思いますけれども、今回は財源の問題もあって、1号側の意見に近い改定になったということですかね。
恐らく2つのところです。一般病床での二次救の要件化と、在宅復帰率で入院料1・2が70%から72.5%に引き上げられて、さらに、減算規定が多い割に掛け算でいっているというところが相当厳しいと言われていると思います。
今日いただいたお題、本当に将来ブリリアントな展望が開けているかというと、私は、一筋の明かりは見えていると思います。もちろん、なんちゃってというところがこのままいけるかというと、それはなかなか難しいと思いますけれども、26年改定で出てきたものが3つの機能に着目して、かなり数の大きい集団になっているということです。
ただし、患者さんが自分の住んでいた地域で急性期を経た後とか、自宅にいても何かちょっと悪くなったときをきちっと担える中核的な存在である医療機関というのは、患者さんにも必要ですし、行政にも必要だし、医療体制を見守る厚生労働省としても必要と認識しているということだと思います。
大病院が全部、何でもやるということではなくて、やはり中小規模の病院がその他の機能ともうまく合わせながら、もしくはその他の地域における医療福祉支援機関と合わせながらやっていくことが大事ではないのかと思います。
冒頭申し上げましたけれども、生産年齢人口が相当減っていってしまうので、今回の改定の話をちょっと離れると、今後20年、地域で病棟をどう維持していくかということになると、労働力をどう確保するか。これはもしかしたら外国人の話もしっかり考えないといけないということになると思うし、今も介護では実現に向けて相当動いていますけれども、例えばベッドの上にセンサーを置いて、起き出そうするとナースステーションのナースにすぐわかって転倒を防ぐとか、トイレへ連れていくのが、ピーピー押される前に予防的にできるみたいなセンサー技術、もしくはそれをAIで組み合わせてやるとか。それによって、実際に当直しなければいけない人数を減らすことができるとかいうことも大事だと思います。
それから、非常に大きな急性期大病院が自分のところの急性期病棟の在院期間を短くするためにこの制度を利用するだけというのは、私はちょっとどうかなと思います。
もちろん、コロナがありましたので、コロナのクラスターを発生させないというのはどの医療機関でも必要だと思いますけれども、今後、改修とか新規病棟を新設するときには、動線とか隔離とか陰圧化対応というものもある程度考えざるを得ないと思います。
地域包括ケア病棟だけを考えると、大規模な病院が重症、中症な人をやるとして、軽症の人、もしくは既にウイルスを出していないということはわかったけれども、すぐには自宅へ帰れない、すぐには特養へ帰れないというような人を一定期間診るような機能というのを地域包括ケア病棟というのは果たしていただけるということもあるんじゃないかと思います。
今後、見通しが立たないという人も結構おられるんですけれども、私は、2040年というのがすごく区切りだと思っていて。というのは、さっきの生産年齢人口の減というのが、今のままでいけば、2040年ぐらいに定常化するんです。つまり、2040年以降になると、大きな要因がなければ、高齢者人口と真ん中の人口の年少人口は定常的な変化になるので、そこまでの20年弱を私たちはどうやったら乗り越えられるかが非常に大事だと思います。
その中に、2つ書いてありますけれども、ageing in place。つまり、自宅も含めて病院も含めて様々な施設も含めて、住んでいた地域で暮らしていけるということも大事だし、平均寿命だけじゃなくて健康寿命を延ばすというのもありました。それを様々な在宅療養支援の機能も含めてやっていただくことによって、田中大会長がおっしゃっておられる、まさに地域に愛されて必要とされる地域包括ケア病棟になるんじゃないかなと思います。
御清聴、どうもありがとうございました。
○仲井培雄
鈴木先生、すばらしい講演ありがとうございました。
日本の今の状況、人口構成とか年齢構成、財源の問題とか、あるいは諸外国との比較、様々な面から日本の医療の現状を捉えていただきました。また、それとプラスしてコロナのこととか働き方、様々な問題がありますけれども、それをどうやって解決すればいいのか。そのときにどうやって地域包括ケア病棟を使っていけばいいのか。いろんなお話がいっぱい出てきたと思います。本当にありがとうございました。
(了)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
| <<開会式 | 特別講演>> |